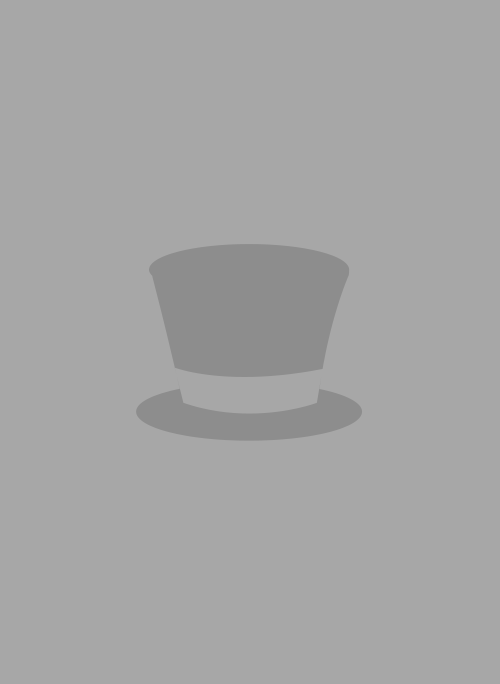「うん、わかった」
そう言って達郎兄ちゃんと別れたが、家には無事に着いた。
家には誰もいない。
父はまだ仕事だし、母も今日はパートだ。
1人は不安だったけど、濡れた姿を見られずに済んだから良かった。無用な心配はかけたくない。
あ、でも手のことは隠せないか。
そんなことを考えながら着替えを終えると、あたしはベッドに身を投げ出した。
なんか昨日今日と色々あって疲れてしまった。
殺害予告のような手紙に階段での事故、どっかの誰かに投げつけられた水風船。
こんだけ続けば誰だって気が滅入る。
すべて同一人物によるものだろうか。
それとも複数の人間の仕業だろうか。
どっちだろうかと考えてみた結論。
―どっちも、ヤだ。
じわりと目頭が熱くなってきた。
達郎兄ちゃんにやられた様に鼻をつまんでみる。
でも、涙は止まらなかった。
あたしはうつぶせなって枕に顔を押しつけた。
そして思い切り声をあげて、泣いた。
そう言って達郎兄ちゃんと別れたが、家には無事に着いた。
家には誰もいない。
父はまだ仕事だし、母も今日はパートだ。
1人は不安だったけど、濡れた姿を見られずに済んだから良かった。無用な心配はかけたくない。
あ、でも手のことは隠せないか。
そんなことを考えながら着替えを終えると、あたしはベッドに身を投げ出した。
なんか昨日今日と色々あって疲れてしまった。
殺害予告のような手紙に階段での事故、どっかの誰かに投げつけられた水風船。
こんだけ続けば誰だって気が滅入る。
すべて同一人物によるものだろうか。
それとも複数の人間の仕業だろうか。
どっちだろうかと考えてみた結論。
―どっちも、ヤだ。
じわりと目頭が熱くなってきた。
達郎兄ちゃんにやられた様に鼻をつまんでみる。
でも、涙は止まらなかった。
あたしはうつぶせなって枕に顔を押しつけた。
そして思い切り声をあげて、泣いた。