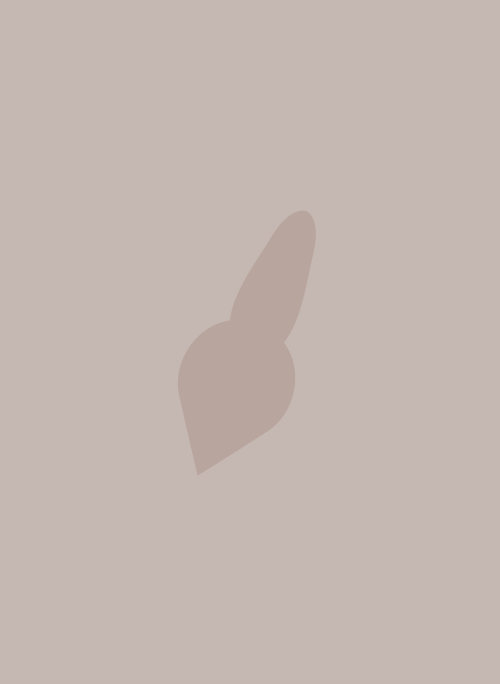そうだよ、タケ兄にだって生活があるんだしこれ以上我が儘は言ってはいけない。
いい子にしていないと離れていってしまう。
暗くなったあたしの顔を見てタケ兄はあたしの頭をくしゃっとなぜた。
「そんな顔すんなって」
タケ兄は少し困った顔をしていた。
あたしが困らせてる――――そう感じた途端体の底から空元気が湧いてきた。
見送るぐらい笑顔でしないと。
「ごめん、あたしは大丈夫だからもう行きなよ。バイトの時間大丈夫?」
「ん?あぁ。今から行けば十分間に合うよ」
んじゃな、とタケ兄は車に乗ってエンジンを掛けた。
助手席にはすでに丹羽さんが乗っていて目があった瞬間ニコリと笑う。
あたしはそれに軽く会釈を返してタケ兄の車を見送った。
その場に残されたのは丹羽さんから預かった白い紙とあたし自身だけだった。
今にも地平線に沈もうとしている太陽があたしをモノ悲しげな夕日色に染めていく。
"あの場所"を飛び出しても見送ることしか出来ない自分に腹立たしさを感じ、同時に諦めが心の中を締め付ける。
いい子にしていないと離れていってしまう。
暗くなったあたしの顔を見てタケ兄はあたしの頭をくしゃっとなぜた。
「そんな顔すんなって」
タケ兄は少し困った顔をしていた。
あたしが困らせてる――――そう感じた途端体の底から空元気が湧いてきた。
見送るぐらい笑顔でしないと。
「ごめん、あたしは大丈夫だからもう行きなよ。バイトの時間大丈夫?」
「ん?あぁ。今から行けば十分間に合うよ」
んじゃな、とタケ兄は車に乗ってエンジンを掛けた。
助手席にはすでに丹羽さんが乗っていて目があった瞬間ニコリと笑う。
あたしはそれに軽く会釈を返してタケ兄の車を見送った。
その場に残されたのは丹羽さんから預かった白い紙とあたし自身だけだった。
今にも地平線に沈もうとしている太陽があたしをモノ悲しげな夕日色に染めていく。
"あの場所"を飛び出しても見送ることしか出来ない自分に腹立たしさを感じ、同時に諦めが心の中を締め付ける。