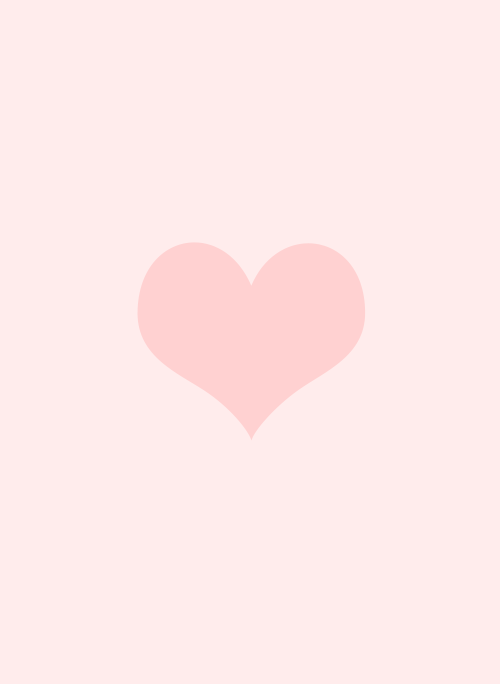何人か、警察の人が来た。普段めったに会わない親戚のおばさんやおじさんも朝からやってきていて、さっきやっと帰っていた。
あたしの知らない、郁の友達も何人か来ていた。
当たり前だけど、郁には郁だけの交友関係もあったんだなと、あたしは薄ぼんやりとそんなことを思った。
今日は、郁の四十九日だった。
あたしは葬式ぶりに会った、おばさんに促されるままに、お父さんとお母さん、そしておじいちゃん、おばあちゃんが眠っているお墓に、郁の骨を納骨した。
悲しみはなかった。
唯、こんなところに入れたら、郁はもう二度とあたしの隣に、本当に帰ってきてくれなくなると思った。
涙は、やっぱり流れなかった。
あたしの最後の砦は、もうずっと、凝り固まったままだった。