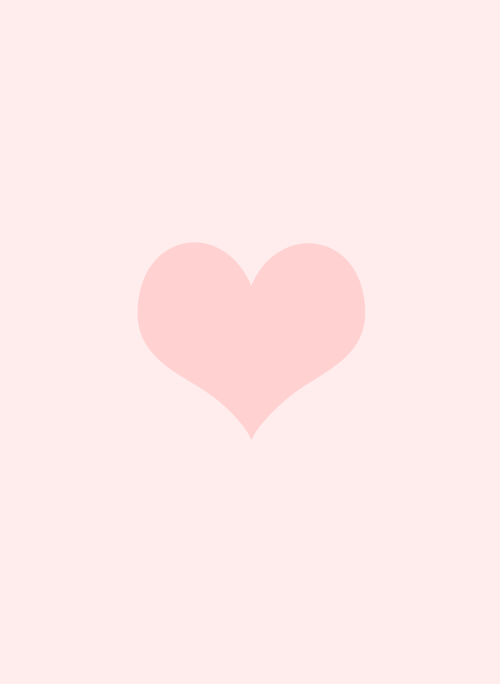目の前にいるのは、確かに郁だった。
郁は、警察の遺体安置所のベッドで寝ていた。
寝かされていた、と思いたくなかった。
郁自身の意思で、ただ睡眠をとるために、その寝台に登ったというのなら、どんなに良かったか。
あたしは認めたくないのと、それでも確かに迫ってきた現実に、今までかすかに抱き続けていた希望をすべてぶち壊しにされたことに、自分の世界が回りそうになるのを、鈍く痛み続ける思考回路でかろうじて知った。
「………間違いありません。私の、姉です」
涙は、出なかった。
まだ認めたくなかった。泣くことは、それと同じだと思った。
最後の、あたしの意地だった。