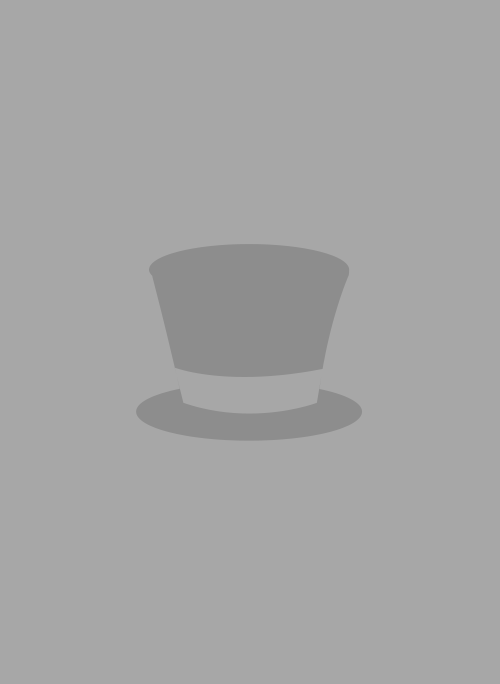荒い息を吐きながら、駅のホームに立った瞬間、
低い声が、私の耳元で、囁かれた。
「やればできるじゃねぇか。」
にやり、と笑って、私の横に並んだのは、
あいつ
だった。
低い声とともに、あいつの熱い息がかかって、
私は、瞬間的にびくりと身をちぢこませた。
「ち、近づかないで!」
心臓の鼓動が早いのは、駅まで走ったせいだ。
でも、本当にそれだけだろうか。
にやり、
と笑った、あいつの笑顔を見ると、
なんだか、怒りでも憎しみでもない、
わけのわからない感情が湧いてくる。
その今までにない感情の正体がわからず、
やっとの思いで、口にした言葉は、
搾り出すような小さな声だった。
しかし、あいつは、
その私の小さな声にちゃんと反応した。
「しょうがねえだろ。親父の命令だからな。
ちゃんと守ってやるから心配すんな。」
え?
今、何て言った?
守ってやるって、聞こえたような・・・。
またしても、あのわけのわからない感情が湧いてくる。
と同時に、胸が締め付けられるような、息苦しさまでもが襲ってきて、
どうしていいか、わからなくなった。
その時、
どこかから、あいつの名前を呼ぶ声が聞こえた。