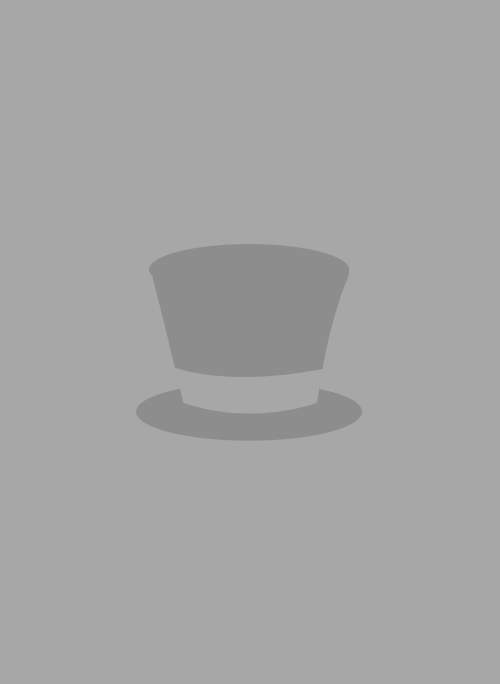「俺さ、多分
あの頃から、
お前に惚れてた。」
「へ?」
脈絡のない唐突な話の展開に、
私の声が裏返る。
こころなしか、
あいつの顔が少し赤らんで見える。
「お前が公園で楽しそうに笑ってるのを見るうちに、
なんか、お前の笑顔が頭から離れなくなってた。
お前に会いたくて、何度も公園に通って、
けど、時々、お前、
公園のブランコで一人で寂しそうに揺られてて、
そんな時は、なんか、守ってやりたいって、
無性にそう思った。」
「だって、あんた、
美人のマネージャーと付き合ってたんでしょ?」
美人だったか、可愛いだったか忘れてしまったけど、
彼女がいたのは確かだ。
「それはさ、
お前を忘れるためっつ~か。
親父が再婚したら、
お前は兄弟になるわけだろ?
それなのに、好きになったらまずいって、
そう思って・・。
告られたから、なんとなく付き合って・・。」
言いにくそうに、しりすぼみな声。