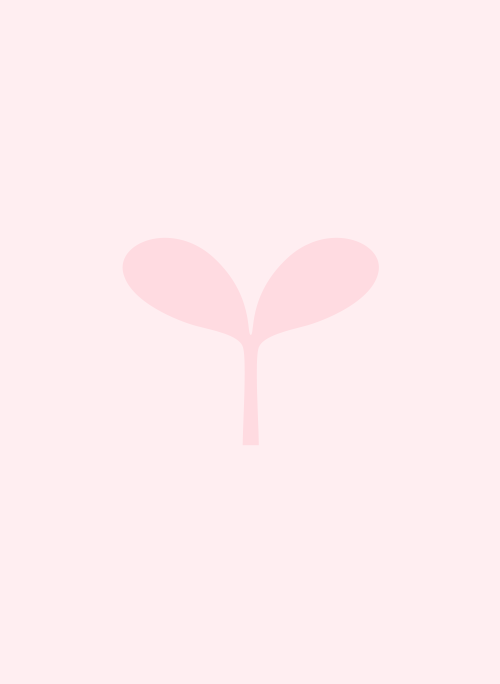青葉の闇に紛れる老梟は、昨晩のやりとりを思い返す。
いつからか機嫌の良い顔など殆ど見せなくなったその影は、いつもの場所から不機嫌そうに自分の名を呼んだのだ。
「メイスフォール」
「此処に」
明るすぎる程の月光の下、硬質であるかのような錯覚をおこしそうになる程静謐な泉の中心、玉座のように突き出た岩の上。
上に向かうにつれて苔や草花が不自然な程生い茂り、その頂点に座す姿は生命を背負っているようにも、周囲に纏わせているようにも見える。
いつもの通り、すぐに返事があることを想定していたのだろう。
主はこちらを向かない。
「いくらお前とて、私は気を長くは持たんぞ」
「まぁまぁ」
不機嫌さを隠さない殺気混じりの声。
溢れる存在と、深く響く声色。
他の者ならば畏怖して身動きすら難しくなるような空間も、メイスフォールにとってはまるで子供が拗ねているかのようで、内心微笑ましい。
「ほんの一時の遊びと大目に見てくださるよう」
いつもの調子で言えば険を削がれた相手は早くもこの件についての発言を諦める。
どうせ人間は森の住人達に喰われるに決まっている。
そう思い直すことにしたのだろう。
冷たく静かなこの王の間を騒がすものは、まだ、いない。