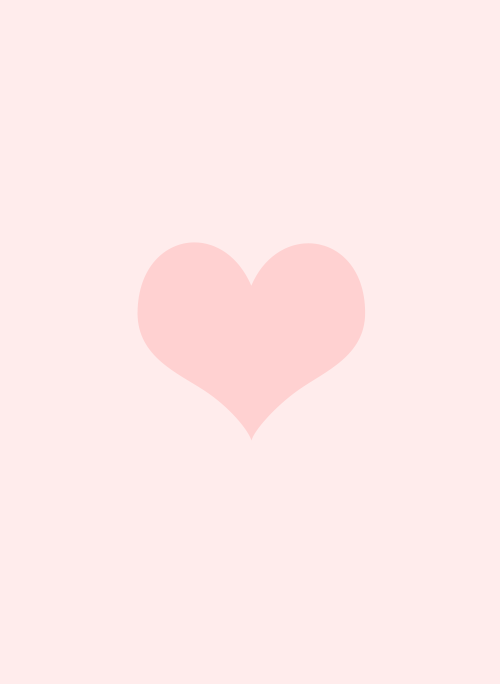「おいルイス、行くぞ。いつまでもトカゲと愛を語らうな」
と、いよいよもってクドクド竜に説教を始めた幼馴染みを呼ぶ。
本当なら置いていってもいいが……そのクドクドがあとで自分に回ってくることを考えると、そちらのほうが面倒だった。
「だってっ、あのっ、でかトカゲがっ、だってっ、ねぇっ、たくっ」
ぶつぶつ文句をぼやきながら追いついたルイスが、そこではたと首を右へ左へ。
「あり? あら? ジョセフィーヌは?」
「知らん」
セリーヌも、ジンと別れたところまでしか見ていない。
と、
「あのう……」
先に行って竜車に小竜を結んできたらしい調教師が、頭を掻いた。
「今見てきたら、車の中に黒猫がいまして」
「「……」」
「すごーく気持ちよさそうに丸まってるんですが、……やっぱりその、追い払うべきですよね?」
その顔には、動物を邪険にできないフーガ民族の悲哀が。
「いや、その必要はない」
と、セリーヌは三度目、肩を叩く。
「それは連れだ。コイツのな」
ルイスが騎竜を苦手とし、結局竜車で行くことを予測して先回りしているジョセフィーヌ。
いくらなんでも頭のよすぎる猫だ、と笑いが止まらないのだった。
と、いよいよもってクドクド竜に説教を始めた幼馴染みを呼ぶ。
本当なら置いていってもいいが……そのクドクドがあとで自分に回ってくることを考えると、そちらのほうが面倒だった。
「だってっ、あのっ、でかトカゲがっ、だってっ、ねぇっ、たくっ」
ぶつぶつ文句をぼやきながら追いついたルイスが、そこではたと首を右へ左へ。
「あり? あら? ジョセフィーヌは?」
「知らん」
セリーヌも、ジンと別れたところまでしか見ていない。
と、
「あのう……」
先に行って竜車に小竜を結んできたらしい調教師が、頭を掻いた。
「今見てきたら、車の中に黒猫がいまして」
「「……」」
「すごーく気持ちよさそうに丸まってるんですが、……やっぱりその、追い払うべきですよね?」
その顔には、動物を邪険にできないフーガ民族の悲哀が。
「いや、その必要はない」
と、セリーヌは三度目、肩を叩く。
「それは連れだ。コイツのな」
ルイスが騎竜を苦手とし、結局竜車で行くことを予測して先回りしているジョセフィーヌ。
いくらなんでも頭のよすぎる猫だ、と笑いが止まらないのだった。