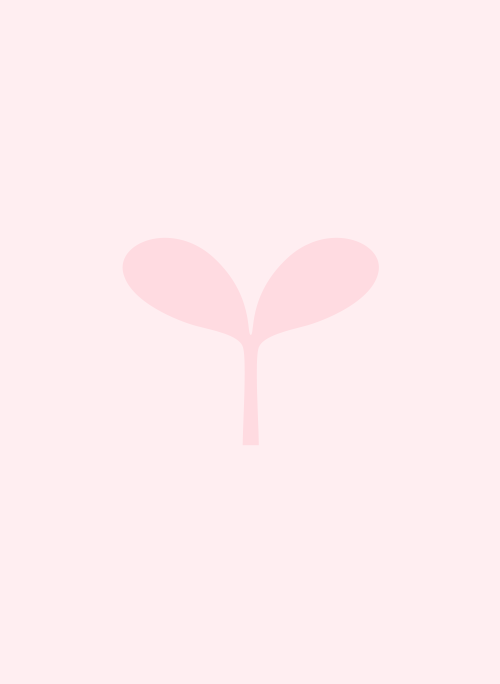「本当に、美味しい!」
「……の割には、あまり進んでいませんね」
えっ、とももは動きをとめる。
「あ……」
自分では、結構食べているつもりだったけれど……。
用意された机の上に乗せられている食事。料理の姿は食べ始めてからあまり変わっていない。
「もも様、やはり具合が悪いのでは?」
「ち、ちがっ……」
脳裏に浮かぶ残像。白銀の世界。純白を鮮明に染めていく、咲き乱れる赤の華。体中を覆う、気持ち悪いもの。
「――っ」
唇を噛み締め、目を瞑る。スプーンを持つ手に、力が込められた。
考えるな。思い出すな。
頭痛がする。吐き気もする。胸の中が、苦しい。
―――――
体の中に流れ込む、何か特別なもの。声でなければ、言葉でもない。
その特別な何かは決して厭わしいものではなくて、むしろ心に響き、奥まで浸透していくもの。
そしてそれは、先ほどまでの苦しい思いを消していく。
目を開き、そっと顔を上げる。辺りは真っ暗で、暗闇の中、たった一人いるだけだった。
―――――
「………」
また、だ。心に響く、この感じ……。まるで私に呼びかけているかのような――。
「あ……」
どこまでも広がる闇の中、〝少女〟が、どこからともなくふわりと現れる。
靡く桃色の髪。揺れる白のワンピース。静かに、彼女は暗闇の中の地についた。
無情であった彼女の瞳が、どこか悲しげに見える。
静かに、彼女は口を動かす。
「 」
「……え?」
彼女の言葉に、目を見開ける。なのに、視界がぼやけていく。