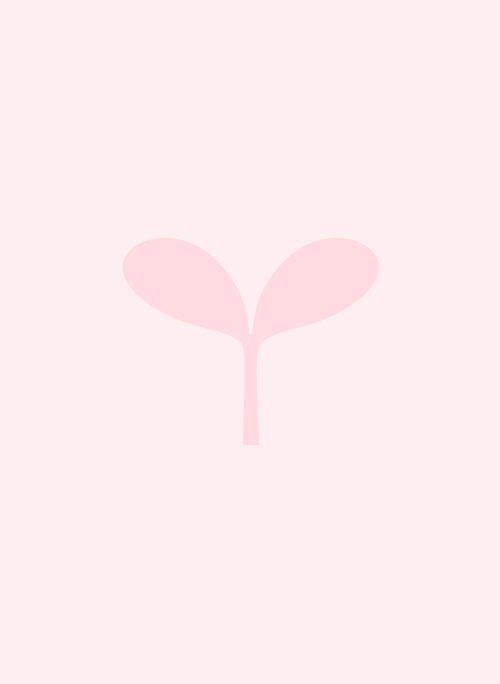が、傘から一歩でも出てしまったら、ずぶ濡れの刑だ。
栖栗は、ぷるぷると何かに耐える肩を震わせ、拳を握る。
そして、バッと顔を上げた栖栗の顔は、この世とは思えないほどの─否、それはさしずめ、般若(はんにゃ)のような顔をしていて。
「───っ!!!」
栖栗は、カァッと顔を真っ赤にすると、髪を押えることも帽子を取り返すこともせず、英から傘を取り上げる。
そうして、ゆっくりと、後退り、涙目で、助走。
「許すまじ我がペット────!!!!!!」
こうして、この度二回目の、栖栗の飛び蹴りが炸裂した。
そんなこんなで、栖栗は、切実に梅雨明けを祈るのだった。
けれども、雨はそれを無視するように、いまだ降り続いている。
雨音に負けない、笑い声と怒鳴り声が黒い空に響く。
こんな風に、笑い、怒ることが如何に幸せなのかを、二人はこのとき、まだ知らなかった。