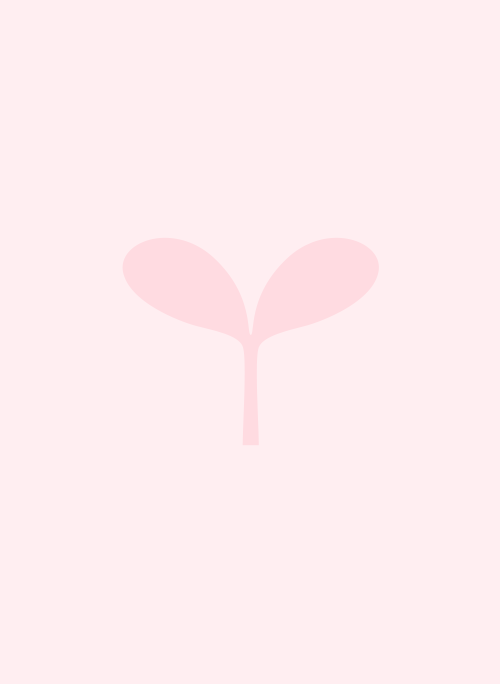英は、頭にハテナマークを浮かべながら、ツン、と人差し指で帽子を軽くつつく。
「‥‥っ!」
軽くつついただけのつもりが、栖栗が大きく目を見開いて、慌ててその手を跳ね除けたものだから、英もまた目を見開いた。
栖栗は、帽子がずれてやしないかと躍起になりながら、手を添えて確認する。
その、あまりに異常すぎる反応に、英は怪訝そうな顔をした。
「朝も帰りも迎えはいらないって‥そりゃあ、オレは助かるけど‥何か、あったのか?」
何かなかったら、帽子なんて被らないし、こんな風に、慌てたりしない。
栖栗はそう思って、察しろよ、と、心の中で舌打ちする。
「‥‥‥」
「‥‥市川?」
英はひょい、と顔を覗き込む。
俯いたままだから、栖栗の表情は何も分からなかったが、ただ、機嫌が悪いことだけは、さすがの英にも察しがついた。
「‥‥‥ご主人さまって言いなさい」
ふと、呟かれた言葉の意図すら分からぬまま、英は素直に従う。
「‥‥‥‥‥‥‥‥ご、しゅじん‥‥さま、?」
正直いって、これを言うのは、抵抗がある。