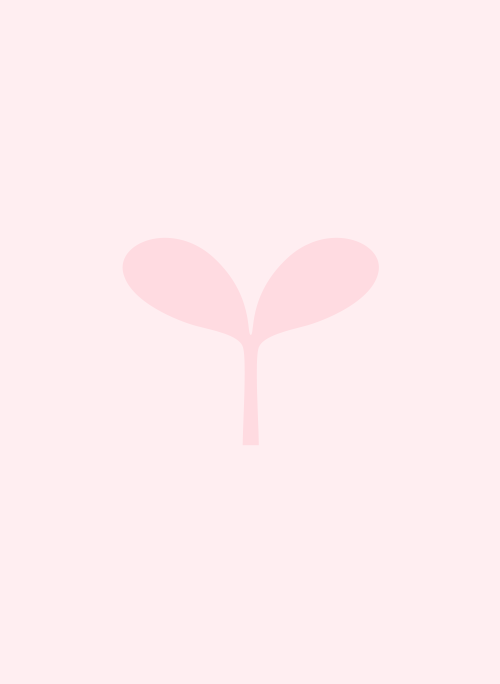けれど、それ以上のことを栖栗は言うつもりはなかった。
むしろ、察して欲しかったから、押し黙ったまま、帰路をスタスタ歩いていく。
しかし、そんなことに英が気がつく筈もなかった。
たしかに、生徒会長として、周囲から好感を得ていることは英自身、ひしひしと感じているだろう。
でも、まさか自分に取り巻きがいようとは、きっと思っていないのだろう、と栖栗は思う。
そうでなかったら、英がこんなに不思議そうな顔はしない。
「まぁいいわ‥それより──‥」
そう思って、諦めたように溜め息を吐いた。
すっかり、脱力しながらも、話を切りだそうと口を開く。
何せ、栖栗には、聞きたいことがあった。
クラスメイトの彼女と、英の関係、だ。
けれど、上手い言葉がなかなか見つからない。
何より、どうして自分が、彼と彼女の関係を気掛かり思わなくてはいけないのか。
「‥‥‥」
なかなか言い出そうとしない栖栗を見て、英は、怪訝そうに首を傾げる。
「何だよ」
「‥‥やっぱ、いい」
「?‥じゃあ、今度はこっちが質問するけど‥何で帽子なんか被ってるんだ?」