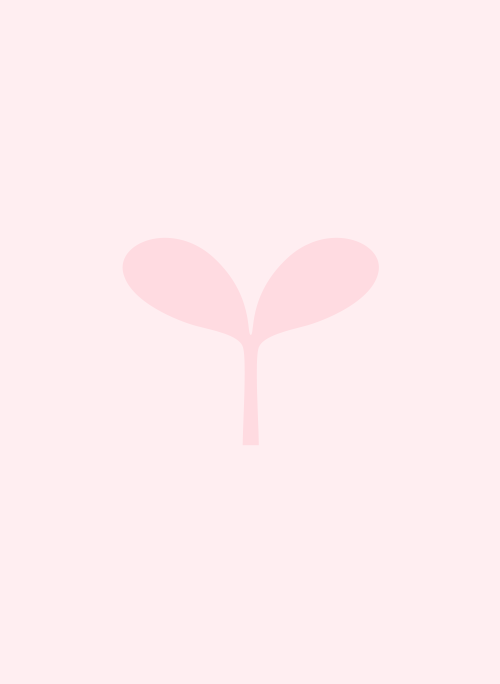温かくて、大きな手。
しっとりと湿り気を帯びた自分の手を掴むそれを、普通は不快に思うだろう。
けれど、栖栗は不快には思わなかった。
むしろ、心地がいい。
そして、胸が先ほどのように、苦しくなるものだから、栖栗は反射的に心臓に手を当てた。
でもこれも不快ではない。
心地いいのだ。
「‥‥‥私、傘ない」
栖栗は試すように、そう言って英の反応を伺った。
すると、英は笑って、栖栗の頭を撫でた。
そのせいで帽子が少しずれてしまったので、栖栗は不機嫌そうに唇を尖らせる。
「折り畳み傘があるのでご安心を」
スクールバックから出されたのは、セーラー服と同じ濃紺の折り畳み傘だった。
栖栗はそれと英を交互に見る。
「‥‥入っていいの?」
「‥置き傘ある場所、教えてやるか?」
悪戯に笑う英に栖栗も同じように笑った。
そして、スクールバックを漁り、“アレ”を取り出す。
ソレは鈍く光る真っ赤な赤い首輪だった。