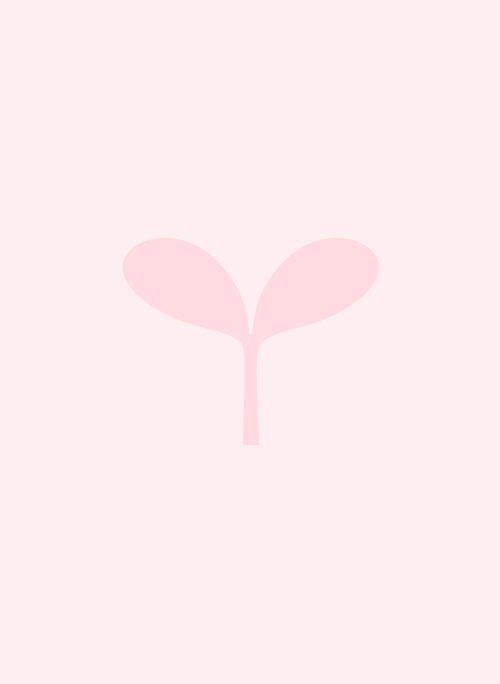優しく頭を撫でる、少女より、幾分か大きな手。
日に焼けている健康的な小麦色の肌と、ゴツゴツと骨張っているその手は、とても強くて、優しい。
彼は、少女が好きだった。
少女は、彼を慕っていた。
どんなに勉強ばかりしていても、それがあれば、疲れは飛んでいってしまうものだから、少女は魔法みたいだと思った。
“魔法の手”だ、と。
でも、彼女がそれを彼に言うわけがなかった。
何せ、彼女は素直な人間ではないし、彼とは幼い頃からの付き合いだから、照れくさいのだ。
「お前さ、高校、どこ行くか決まったのかよ?」
彼が言う。
少女は、山積みにされた参考書の中から一冊取り出すと机に広げ、カチカチ、とシャープペンシルを鳴らして芯を出す。
そして、純白のシーツが張られたベッドに横たわる彼に振り向くと少女は大きく頷いた。
真っ直ぐな、瞳。
答えを聞かずとも、彼は何となくだが、それを察した。
「‥うん。私、悦司と同じ高校に行きたい」
悦司、と呼ばれた彼は、穏やかな笑みを浮かべる。