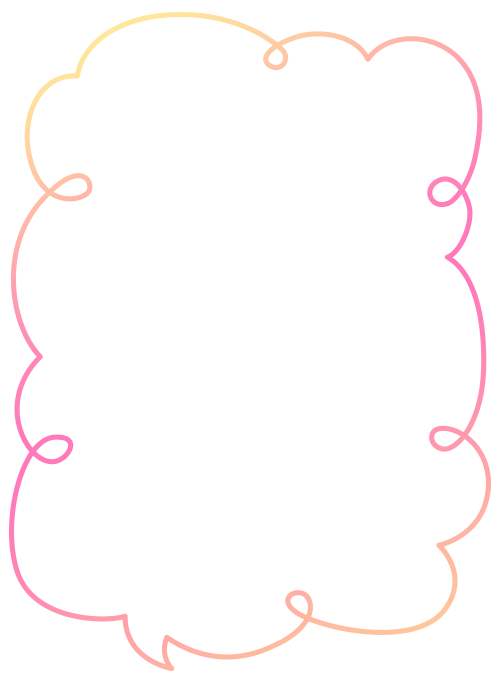タナカのお兄ちゃんは、二十代前半。
惣菜部門で、揚げ物担当。
声が大きくて、動きが雑で、
でも誰よりも長く売り場に立っている人だった。
ある日の夕方、
惣菜コーナーの奥で、油の音がいつもより荒れていた。
「……あれ?」
ハルトは立ち止まった。
コロッケの衣が、いつもより濃い色をしている。
表面だけが先に焦げて、中が火を通す前の色。
タナカのお兄ちゃんが、眉をひそめていた。
「油、今日なんか変なんだよな……」
ハルトは少し迷ってから、言った。
「……温度、上がりすぎてるかも」
タナカは振り返った。
「え?」
「レンジでも、最初に強すぎると、外だけ固くなります」
沈黙。
タナカは一度、温度計を見て、
深く息をついて、油の火力を下げた。
数分後、
コロッケは、いつもの色に戻った。
「……助かった」
タナカはそう言って、
揚げたてを一つ、紙に包んだ。
「これ、試食」
ハルトは首を振った。
「家で食べます」
タナカは笑った。
「そっか。
じゃあ、“料理仲間”な」
タグチさんは五十代。
寡黙で、魚の話しかしない人だった。
ある日、ハルトは鮮魚コーナーで立ち尽くしていた。
サバ。
安いけれど、臭みが出やすい。
火を使わない料理では、扱いが難しい。
「……どうする?」
タグチさんの声だった。
ハルトは正直に言った。
「レンジだと、くさくなります」
タグチさんは少し考えてから、
一匹のサバを手に取った。
「下処理で、ほぼ決まる」
そう言って、
酢と塩の量、ラップの仕方、
レンジに入れる前の待ち時間を教えた。
ハルトは真剣に聞いた。
数日後。
ハルトスーパーに戻ってきた。
「……できました」
タグチさんに、スマホの写真を見せる。
レンジで作った、サバの南蛮漬け。
タグチさんは、
一瞬だけ目を細めた。
「……やるじゃねぇか」
それは、最大級の褒め言葉だった。
その日から、少しずつ変わった。
惣菜の味が安定し、
鮮魚のおすすめに「レンジ向き」が増えた。
ジンは、聞かれたら答える。
聞かれなければ、何も言わない。
それでも、
スーパーの空気が、少し柔らかくなった。
その日の帰り、レジに立っていたのはウエハラさんだった。
「今日は、遅かったね」
「はい」
「忙しかった?」
ハルトは少し考えてから言った。
「……ちょっと、仕事しました」
ウエハラさんは、
レシートを渡しながら、静かに笑った。
「じゃあ今日は、
“お給料”もらった?」
ハルトはうなずいた。
「コロッケです」
「それは良い日だ」
家で、ユウイチが言った。
「今日の夕飯、なんか自信あるな」
「うん」
ハルトは、少しだけ胸を張った。
――自分は、
ここにいていい。
誰かの役に立てる場所が、
ちゃんとある