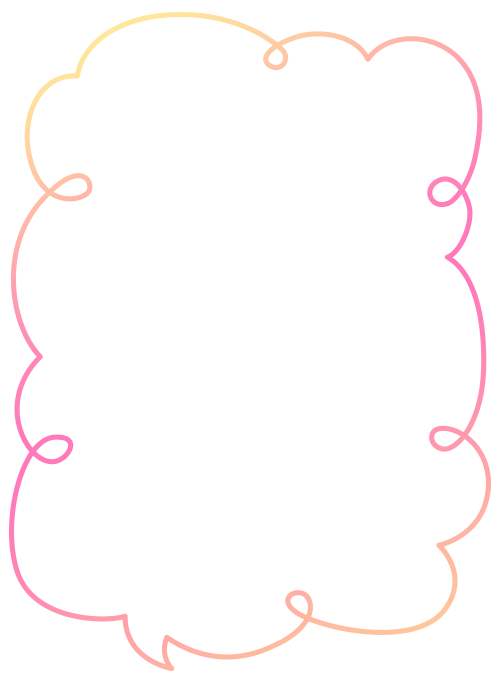ハルトが料理を覚え始めたのは、母親が忙しくなってからだった。
離婚後、母は一人で働きながらジンを育てていた。
帰りは遅く、夕飯はスーパーの惣菜や冷凍食品が多かった。
ある日、母が熱を出して倒れた。
「ごはん、どうしようか」
そう言って笑った母の声が、少し震えていた。
ハルトは冷蔵庫を開けた。
卵と牛乳、残り物のごはん。
火を使うのは怖かった。
だから、電子レンジを使った。
爆発しないようにラップを少し浮かせること、
温めすぎると固くなること。
失敗しながら、ネットで調べながら。
「火を使わなければ、大丈夫」
それが、ハルトの中のルールになった。
母は言った。
「ハルト。すごいね。でも無理しなくていいんだよ」
ハルトはうなずいたけれど、
心の中ではこう思っていた。
――自分ができることは、自分でやる。
――そうすれば、母は少し楽になる。
その母が、もう帰ってこなくなった。
でも、料理だけは、ハルトの中に残った。
給食の時間、ハルトはよく言われた。
「ハルト、今日のメニューどう思う?」
「これ、家でも作れる?」
最初は戸惑った。
でも、質問されるのは嫌じゃなかった。
家庭科の授業では、先生が言った。
「火を使わない調理、誰か知ってる?」
ハルトが手を挙げた。
電子レンジで作る蒸し料理。
炊飯器で作るケーキ。
クラスはざわついた。
「え、小学生で?」
「それ、ほんとに一人で?」
先生は少し黙ってから、こう言った。
「ハルトくんのやり方は、とても現実的で安全だね」
その言葉は、ハルトの背中を少しだけ伸ばした。
ユウイチと暮らし始めてから、ハルトは近所のスーパーに一人で行くようになった。
最初に声をかけてきたのは、レジの女性だった。
「今日は何作るの?」
「……レンジで蒸し野菜です」
「じゃあ、このキャベツ、小さいから使いやすいよ」
次は、惣菜コーナーの若いお兄さん。
「これ、味の勉強になるから食べてみな」
値引きシールの貼られた煮物を、そっとカゴに入れてくれた。
レジの人は、いつも言った。
「今日も料理?」
ハルトがうなずくと、少しだけ嬉しそうに微笑った。
誰も、「かわいそう」とは言わなかった。
誰も、「無理しなくていい」とも言わなかった。
ただ、
一人の料理する人として接してくれた。
それが、ハルトには何よりありがたかった。
ある夜、ユウイチは聞いた。
「……なんで、そんなに料理できるんだ?」
ハルトは少し考えてから答えた。
「できるから」
それ以上でも、それ以下でもなかった。
ユウイチは、その言葉を胸の中で何度も転がした。
――この子は、強いんじゃない。
――強くならざるを、得なかったんだ。
翌朝、ユウイチはいつもより丁寧に、おにぎりを握った。
具を入れて。
離婚後、母は一人で働きながらジンを育てていた。
帰りは遅く、夕飯はスーパーの惣菜や冷凍食品が多かった。
ある日、母が熱を出して倒れた。
「ごはん、どうしようか」
そう言って笑った母の声が、少し震えていた。
ハルトは冷蔵庫を開けた。
卵と牛乳、残り物のごはん。
火を使うのは怖かった。
だから、電子レンジを使った。
爆発しないようにラップを少し浮かせること、
温めすぎると固くなること。
失敗しながら、ネットで調べながら。
「火を使わなければ、大丈夫」
それが、ハルトの中のルールになった。
母は言った。
「ハルト。すごいね。でも無理しなくていいんだよ」
ハルトはうなずいたけれど、
心の中ではこう思っていた。
――自分ができることは、自分でやる。
――そうすれば、母は少し楽になる。
その母が、もう帰ってこなくなった。
でも、料理だけは、ハルトの中に残った。
給食の時間、ハルトはよく言われた。
「ハルト、今日のメニューどう思う?」
「これ、家でも作れる?」
最初は戸惑った。
でも、質問されるのは嫌じゃなかった。
家庭科の授業では、先生が言った。
「火を使わない調理、誰か知ってる?」
ハルトが手を挙げた。
電子レンジで作る蒸し料理。
炊飯器で作るケーキ。
クラスはざわついた。
「え、小学生で?」
「それ、ほんとに一人で?」
先生は少し黙ってから、こう言った。
「ハルトくんのやり方は、とても現実的で安全だね」
その言葉は、ハルトの背中を少しだけ伸ばした。
ユウイチと暮らし始めてから、ハルトは近所のスーパーに一人で行くようになった。
最初に声をかけてきたのは、レジの女性だった。
「今日は何作るの?」
「……レンジで蒸し野菜です」
「じゃあ、このキャベツ、小さいから使いやすいよ」
次は、惣菜コーナーの若いお兄さん。
「これ、味の勉強になるから食べてみな」
値引きシールの貼られた煮物を、そっとカゴに入れてくれた。
レジの人は、いつも言った。
「今日も料理?」
ハルトがうなずくと、少しだけ嬉しそうに微笑った。
誰も、「かわいそう」とは言わなかった。
誰も、「無理しなくていい」とも言わなかった。
ただ、
一人の料理する人として接してくれた。
それが、ハルトには何よりありがたかった。
ある夜、ユウイチは聞いた。
「……なんで、そんなに料理できるんだ?」
ハルトは少し考えてから答えた。
「できるから」
それ以上でも、それ以下でもなかった。
ユウイチは、その言葉を胸の中で何度も転がした。
――この子は、強いんじゃない。
――強くならざるを、得なかったんだ。
翌朝、ユウイチはいつもより丁寧に、おにぎりを握った。
具を入れて。