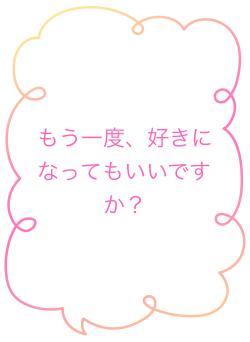晃は知夏が好きだ。
小学生の頃。
「好き」という気持ちの表現がわからなかった。
抱きつけば、わかってもらえる?
それとも、ちゅーすれば?
幼いながら、浅い“好き”という知識を探す。
でも、わからなかった。
だから、あんなことをした。
その日が誕生日の知夏の席には、一つの箱があった。
紙袋の中で揺れていた小さな箱。
リボンの結び目がやけにきれいで、
触れたらほどけてしまいそうだった。
「なにそれ」
軽い気持ちで言った。
からかうつもりで、びっくりさせるつもりで。
「それはね、」
どんなこと言われても、笑ってる知夏の驚いた顔を、見たかった。
手が滑ったのは、一瞬だった。
乾いた音がして、中身が床に散らばる。
散らばったそれは、色とりどりのクッキーと手紙。
手紙には、「お誕生日おめでとう」という言葉と、クラスメイトからのメッセージがあった。
——そうだ。
今日は知夏の誕生日だ。
ざわざわと教室が騒ぎ出す。
「うわ、晃なにやってんだよ!」
「晃くん、謝りなよ!」
「せんせーにいうよ!」
バケツをひっくり返したような非難の嵐で我に帰る。
後悔しても、遅かった。
喉まで出かかった言葉は、最後まで形にならなかった。
代わりに晃は笑って、「わざとじゃないし」と言ってしまう。
知夏は何も言わなかった。
怒らなかったし、泣きもしなかった。
ただ、箱を拾い集める手だけが、少し震えていた。
——ばかだ。
悲しませるつもりはなかった。
そんな顔、させるつもりはなかったのに。
その日から、謝るタイミングは失われたままだった。
数日後、知夏はいなくなった。
先生は「ご両親の事情で引っ越した」と言っていた。
理由を聞く前に。
「ごめん」を言う前に。
晃の中には、壊れたままの箱と、
言えなかった一言だけが、まだ残っている。