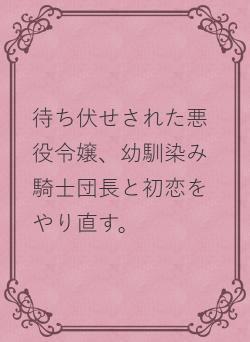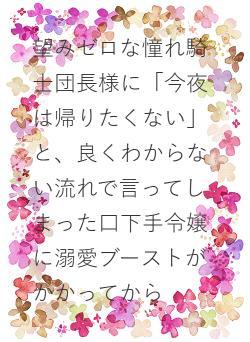絶望しているだろう私と彼が育てた執事クウェンティンを、こんな発言で笑わせて安心させてしまうのだって、彼にはきっと……お手のものなのよね。
「ふふ。なんだか、アーロンらしいわね」
そして、アーロンがそう思わせたのなら、勝算があるのだと思う。そういう人だもの。これまでの彼との時間で、私は夫アーロンのことを十分過ぎるほどに理解していた。
「奥様……笑っている場合ではありません。これは、国中で面白い噂話になりますよ。あの人らしいですけどね」
シュレイド王国では、将軍アーロンは有名人なのだ。下手すると周辺国まで笑い話として、この話は広まってしまうかもしれない。
「けど、アーロンならば、きっとこう言うわ。誰かを守るために勝てるのなら、自分が笑われるくらいどうでも良いことだって」
アーロンならばどんな戦いでも最後に勝って、私の元に帰って来てくれる。そう信じられる。
これまでもこれからも、そうしてくれるだろう。
◇◆◇
テラスでお茶を飲んでいた私と傍で給仕していたクウェンティンは、今では剣の稽古まで出来てしまえるようにまで治ったアーロンを見ていた。
「ふふ。なんだか、アーロンらしいわね」
そして、アーロンがそう思わせたのなら、勝算があるのだと思う。そういう人だもの。これまでの彼との時間で、私は夫アーロンのことを十分過ぎるほどに理解していた。
「奥様……笑っている場合ではありません。これは、国中で面白い噂話になりますよ。あの人らしいですけどね」
シュレイド王国では、将軍アーロンは有名人なのだ。下手すると周辺国まで笑い話として、この話は広まってしまうかもしれない。
「けど、アーロンならば、きっとこう言うわ。誰かを守るために勝てるのなら、自分が笑われるくらいどうでも良いことだって」
アーロンならばどんな戦いでも最後に勝って、私の元に帰って来てくれる。そう信じられる。
これまでもこれからも、そうしてくれるだろう。
◇◆◇
テラスでお茶を飲んでいた私と傍で給仕していたクウェンティンは、今では剣の稽古まで出来てしまえるようにまで治ったアーロンを見ていた。