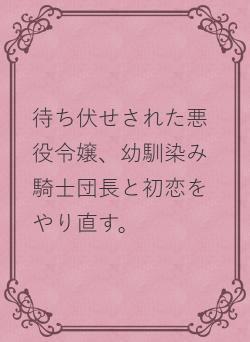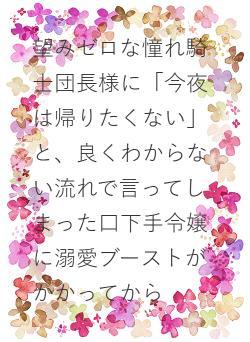朝、食堂を出て出勤しようとしているところ、ヴィルフリートに私は呼び止められた。彼はかっちりとした青色の聖竜騎士団の制服を着ていて、それはそれは格好良かった。
けれど、彼を恋愛対象にする気のない私にとっては、格好良いですね。ただそれだけのことだった。
「ヴィルフリートで良い。庭師になったんだと? 俺はてっきり、女官にでもなるのかと思ったよ。もしくは、メイドとか……城の仕事って、高給で楽らしいし。競争率が高くて、人気あるらしいぜ」
庭師見習いが意外だったらしいヴィルフリートは私が楽な仕事をして、手に職を付けるのだろうと思って居たらしい。
いえ。きっと、彼でなくてもそう思うわよね。私だってこれまでの事がなければ、そうしていたはずだもの。
「人と関わることが、もう嫌なんです」
私がそう言えば、ヴィルフリートは片眉を上げて、なんとも言えない表情になっていた。
着の身着のままで働くしかないのに、『こいつ何言ってんだ』と、思ってそうだけど仕方ない。
これが私の何も隠さない本音だもの。
けれど、彼を恋愛対象にする気のない私にとっては、格好良いですね。ただそれだけのことだった。
「ヴィルフリートで良い。庭師になったんだと? 俺はてっきり、女官にでもなるのかと思ったよ。もしくは、メイドとか……城の仕事って、高給で楽らしいし。競争率が高くて、人気あるらしいぜ」
庭師見習いが意外だったらしいヴィルフリートは私が楽な仕事をして、手に職を付けるのだろうと思って居たらしい。
いえ。きっと、彼でなくてもそう思うわよね。私だってこれまでの事がなければ、そうしていたはずだもの。
「人と関わることが、もう嫌なんです」
私がそう言えば、ヴィルフリートは片眉を上げて、なんとも言えない表情になっていた。
着の身着のままで働くしかないのに、『こいつ何言ってんだ』と、思ってそうだけど仕方ない。
これが私の何も隠さない本音だもの。