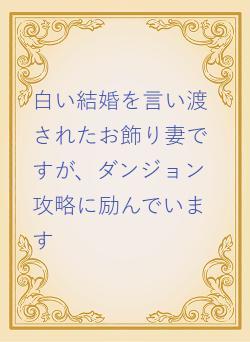王城が真っ赤な炎に包まれている。
滅びゆく母国を、わたしは幽閉されている塔の小窓から見下ろしていた。
胸元のペンダントをギュッと握りしめた時、ズンッと大きな揺れが足元を襲う。
この塔は頑丈な石造りだ。それがこんなにも揺れるということは、大きな爆発があったにちがいない。
「お父様。お兄様……」
わたしは両手の指を組んで祈りを捧げた。
そのさなかに、石階段を駆け上がる複数の無粋な足音が聞こえてきた。
バン!と大きな音を立てて扉が開かれる。
敵国の鎧をまとった兵士たちが狭い部屋になだれ込んできた。
その中のひとり、恰幅のいい髭面の騎士がこちらを睨みつけて言う。
「おまえは第二王子の婚約者、マリア・モナークだな」
「ちがいます」
「嘘を言うな! 青い目に栗色の髪。その工芸品のような見事な縦カールの持ち主は、マリア・モナーク以外にはいないと聞き及んでいるぞ!」
もしかしてわたし、褒められているのかしら?
「わたしがマリアであることは間違いございません。しかし3日前に婚約破棄され、モナーク伯爵からも勘当を言い渡され、ここへ幽閉されました」
だからいまのわたしは、家名すら持たないただのマリアだ。
「よし、マリア・モナークに間違いない! 連行しろ!」
「だから、ちがうって言ってんでしょ!」
モナークじゃないと言っているのがわからないのか。
そこへ高貴な身なりをしたプラチナブロンドの髪の少年が入ってきた。
年齢は12、3歳ぐらいに見える。
しかしこちらを真っすぐ見つめる琥珀色の目には、少年特有のキラキラしさがない。
「見つかったか?」
「はい、シリウス様」
シリウス……その名を聞いてピンときた。
この少年は、敵国アドラ王国の第三王子だ。
公にはほとんど姿を見せないと聞いていたけれど、まだこんなに幼かったのか。
第一王子と年が随分離れているということは、正妃の子ではないのだろう。
それはいいとして、なぜこんな場所に?
わたしの頭の中を駆け巡る様々な疑問は、髭面のひとことでかき消された。
「この女こそが、ロミオ王子の暗殺を企てたというマリア・モナークです!」
「暗殺を企ててなんかいないわ。わたしはただ、ロミオ様に爆弾を投げつけただけよ」
「殺そうとしているではないか!」
髭面のツッコミに、ブフッ!と笑ったのはシリウスだった。
そもそも我が国を制圧したアドラ王国にとって、わたしがロミオ王子に爆弾を投げつけたかどうかなんて、どうでもいいではないか。
「わたしを殺すなら殺してくれてかまわないわ。どうせこの国は滅びるんでしょう?」
髭面がわたしの胸元を見ている。
「そのペンダント……怪しいな」
わたしは伸ばされた手を振り払った。
アクセサリーにしては武骨な形をしたペンダントヘッドだ。
しかし他人に気安く触れてほしくはない。
「やめてちょうだい。おじいさまの形見なんだから」
チェーンを首から外して手に握る。
「もしかして、爆弾だとでも思っているの?」
言い終える前に、ペンダントを石の床に叩きつけた。
髭面がシリウスを庇うように胸に抱く。
しかし何も起きなかった。
金属製のペンダントヘッドが石の床に転がっただけだ。
「馬鹿ね。本物の爆弾だったら王子を庇ったって無駄よ。みんないまごろ粉々になっていたでしょうね」
わたしは拾い上げたペンダントを再び首にかけて、にっこり笑ってみせたのだった。
◇◇◇
馬車の中で、向かい側に座るシリウスがずっと肩を小さく震わせて笑い続けている。
どうやらこのチビッ子王子、相当な笑い上戸らしい。
シリウスはこのままアドラ王国へ帰還するらしい。
わたしは亡国の捕虜といったところだろうか。それなのになぜか、王子様と同じ馬車に乗せられている。
「ねえ、いいかげん笑うのをやめてくれない?」
「爆弾を投げつけておいて殺そうとしていないだなんて……ぶふっ……おもしろすぎるだろ」
いつまで笑うつもりなんだろうか。
どんなことでも面白く思えるお年頃なのかもしれないけれど。
シリウスはようやく笑いを引っ込めると、今度は琥珀色の目をいたずらっぽく細めてわたしのペンダントを指さした。
「爆弾を至近距離で破裂させれば、みんな粉々になって確実に命を落とすんだろう?」
塔でのわたしのパフォーマンスをまだ根に持っているのだろう。
あんな手に引っかかるほど、アドラには火薬の知識を持つ者がいないのだと思う。
いや、アドラだけではない。
この大陸で、火薬の製法と配合、正しい扱い方を熟知していたのは、おそらくモナーク伯爵家だけだ。
「本物ならね」
わたしは肩をすくめる。
「本物とは?」
シリウスが、スッと表情を大人びたものに変えた。
「爆弾って言ってもいろいろあるの。たとえばロミオ様に投げつけたのは『破裂玉』だもの。あんな子どもだましで死んだりしないわ」
「破裂玉?」
「派手な破裂音と白い煙が上がるだけ。殺傷能力のない小さな玉なの」
耳慣れない言葉だとしても仕方ない。
昔おじいさまが作ったオリジナルのいたずらグッズのような代物だ。
『おまえみたいな爆弾令嬢のことなど、一生愛する気はないからな!』
そう言ってくるロミオに腹が立った。
顔を合わせるたびに同じことを言われるものだから、いよいよ我慢の限界がきたのだ。
「だからこちらもついに堪忍袋の緒が切れて、『まあ、ロミオ様。わたしは爆弾令嬢ではなく伯爵令嬢ですわ!』って破裂玉を投げつけてやったのよ」
ロミオ王子の暗殺未遂容疑の真相を説明した。
「勇ましいな」
シリウスは再びお腹を抱えて笑いはじめた。
そして笑いがおさまると、スッと目を細めて信じられないことを言った。
「よし、今日からマリアを俺の婚約者にする」と。
はぁっ!?
滅びゆく母国を、わたしは幽閉されている塔の小窓から見下ろしていた。
胸元のペンダントをギュッと握りしめた時、ズンッと大きな揺れが足元を襲う。
この塔は頑丈な石造りだ。それがこんなにも揺れるということは、大きな爆発があったにちがいない。
「お父様。お兄様……」
わたしは両手の指を組んで祈りを捧げた。
そのさなかに、石階段を駆け上がる複数の無粋な足音が聞こえてきた。
バン!と大きな音を立てて扉が開かれる。
敵国の鎧をまとった兵士たちが狭い部屋になだれ込んできた。
その中のひとり、恰幅のいい髭面の騎士がこちらを睨みつけて言う。
「おまえは第二王子の婚約者、マリア・モナークだな」
「ちがいます」
「嘘を言うな! 青い目に栗色の髪。その工芸品のような見事な縦カールの持ち主は、マリア・モナーク以外にはいないと聞き及んでいるぞ!」
もしかしてわたし、褒められているのかしら?
「わたしがマリアであることは間違いございません。しかし3日前に婚約破棄され、モナーク伯爵からも勘当を言い渡され、ここへ幽閉されました」
だからいまのわたしは、家名すら持たないただのマリアだ。
「よし、マリア・モナークに間違いない! 連行しろ!」
「だから、ちがうって言ってんでしょ!」
モナークじゃないと言っているのがわからないのか。
そこへ高貴な身なりをしたプラチナブロンドの髪の少年が入ってきた。
年齢は12、3歳ぐらいに見える。
しかしこちらを真っすぐ見つめる琥珀色の目には、少年特有のキラキラしさがない。
「見つかったか?」
「はい、シリウス様」
シリウス……その名を聞いてピンときた。
この少年は、敵国アドラ王国の第三王子だ。
公にはほとんど姿を見せないと聞いていたけれど、まだこんなに幼かったのか。
第一王子と年が随分離れているということは、正妃の子ではないのだろう。
それはいいとして、なぜこんな場所に?
わたしの頭の中を駆け巡る様々な疑問は、髭面のひとことでかき消された。
「この女こそが、ロミオ王子の暗殺を企てたというマリア・モナークです!」
「暗殺を企ててなんかいないわ。わたしはただ、ロミオ様に爆弾を投げつけただけよ」
「殺そうとしているではないか!」
髭面のツッコミに、ブフッ!と笑ったのはシリウスだった。
そもそも我が国を制圧したアドラ王国にとって、わたしがロミオ王子に爆弾を投げつけたかどうかなんて、どうでもいいではないか。
「わたしを殺すなら殺してくれてかまわないわ。どうせこの国は滅びるんでしょう?」
髭面がわたしの胸元を見ている。
「そのペンダント……怪しいな」
わたしは伸ばされた手を振り払った。
アクセサリーにしては武骨な形をしたペンダントヘッドだ。
しかし他人に気安く触れてほしくはない。
「やめてちょうだい。おじいさまの形見なんだから」
チェーンを首から外して手に握る。
「もしかして、爆弾だとでも思っているの?」
言い終える前に、ペンダントを石の床に叩きつけた。
髭面がシリウスを庇うように胸に抱く。
しかし何も起きなかった。
金属製のペンダントヘッドが石の床に転がっただけだ。
「馬鹿ね。本物の爆弾だったら王子を庇ったって無駄よ。みんないまごろ粉々になっていたでしょうね」
わたしは拾い上げたペンダントを再び首にかけて、にっこり笑ってみせたのだった。
◇◇◇
馬車の中で、向かい側に座るシリウスがずっと肩を小さく震わせて笑い続けている。
どうやらこのチビッ子王子、相当な笑い上戸らしい。
シリウスはこのままアドラ王国へ帰還するらしい。
わたしは亡国の捕虜といったところだろうか。それなのになぜか、王子様と同じ馬車に乗せられている。
「ねえ、いいかげん笑うのをやめてくれない?」
「爆弾を投げつけておいて殺そうとしていないだなんて……ぶふっ……おもしろすぎるだろ」
いつまで笑うつもりなんだろうか。
どんなことでも面白く思えるお年頃なのかもしれないけれど。
シリウスはようやく笑いを引っ込めると、今度は琥珀色の目をいたずらっぽく細めてわたしのペンダントを指さした。
「爆弾を至近距離で破裂させれば、みんな粉々になって確実に命を落とすんだろう?」
塔でのわたしのパフォーマンスをまだ根に持っているのだろう。
あんな手に引っかかるほど、アドラには火薬の知識を持つ者がいないのだと思う。
いや、アドラだけではない。
この大陸で、火薬の製法と配合、正しい扱い方を熟知していたのは、おそらくモナーク伯爵家だけだ。
「本物ならね」
わたしは肩をすくめる。
「本物とは?」
シリウスが、スッと表情を大人びたものに変えた。
「爆弾って言ってもいろいろあるの。たとえばロミオ様に投げつけたのは『破裂玉』だもの。あんな子どもだましで死んだりしないわ」
「破裂玉?」
「派手な破裂音と白い煙が上がるだけ。殺傷能力のない小さな玉なの」
耳慣れない言葉だとしても仕方ない。
昔おじいさまが作ったオリジナルのいたずらグッズのような代物だ。
『おまえみたいな爆弾令嬢のことなど、一生愛する気はないからな!』
そう言ってくるロミオに腹が立った。
顔を合わせるたびに同じことを言われるものだから、いよいよ我慢の限界がきたのだ。
「だからこちらもついに堪忍袋の緒が切れて、『まあ、ロミオ様。わたしは爆弾令嬢ではなく伯爵令嬢ですわ!』って破裂玉を投げつけてやったのよ」
ロミオ王子の暗殺未遂容疑の真相を説明した。
「勇ましいな」
シリウスは再びお腹を抱えて笑いはじめた。
そして笑いがおさまると、スッと目を細めて信じられないことを言った。
「よし、今日からマリアを俺の婚約者にする」と。
はぁっ!?