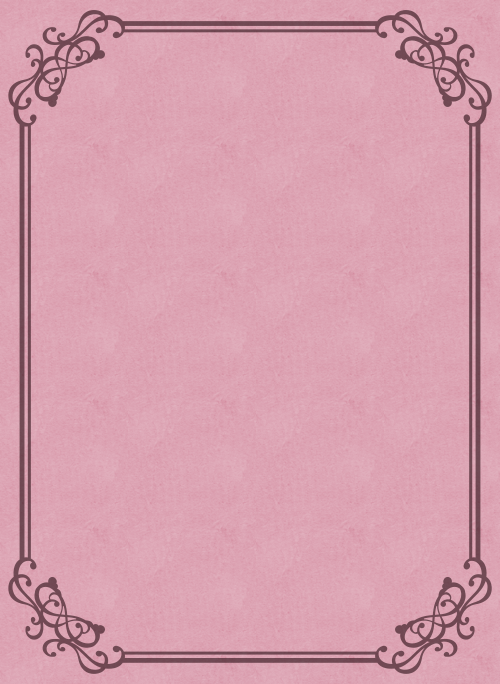「お前がFなのか?」
その一言で、私――飯島花音の平和な中学生活は終わった。
ええ、終わりました。
今朝の占いランキング1位だったのに……。
もう占いなんて信じない!
「え、あ、なんで藤真くんが屋上に…!?あ、えっと、え、Fって何のことかなぁ~?」
私立鳳凰学園、昼休みの屋上。
風は気持ちいいし、人も少ないし、なによりスマホの電波がよく入る。
だから私はここで、こっそり――ほんとっーーーーに、こっそり――新曲のアップロードをしようとしていた。
……していたのに。
どうやら夢中で気づかなかったうちに、クラスメイトの浅見藤真くんが、屋上の扉を開けて入ってきて、私のすぐ後ろにいたらしい。
背、たっか。
眉、動かなっ。
感情、相変わらず読めない……。
「屋上の施錠当番。……それより」
そう言った瞬間、藤真くんの手が伸びて、私のスマホがすっと消える。
「ちょ、返して!それ私の命!」
ぴょんぴょん飛び跳ねて取り返そうとするけど、相手の腕が長すぎるし、身長差が現実を突きつけてくる。
私は中3の平均身長、相手は……たぶん、平均を遥かに超えている。
「命をちゃんと大切にしなかったお前が悪い」
「ぐぎゃあああああ!」
「こんなところで迂闊なことやって……。お前、よく今まで正体ばれなかったな」
「ち、違う!わ、私はFじゃない!私はFじゃない!!」
藤真くんは無表情のまま、私のスマホ画面を私に向けた。
『アカウント名:F 新曲をアップロード中 残り9%』
「このアカウント、今話題の謎のボカロP・Fだよな。しかも今、新曲を上げようとしてる」
……はい。詰みました。
藤真くんはため息もつかない。
無表情で、私をどんどん追い詰めていく。
「性別も年齢も不明。去年、突然現れた謎のボカロP。澄んだ曲調と明るい歌詞で人気になった……」
「藤真くん、Wikipediaみたいに言わないで!」
自分で言っておいて泣きたくなった。
いや、泣いてる場合じゃない。
私の秘密が、いまバレた。
浅見藤真――中学3年生で同じクラス、出席番号1番。
クールな雰囲気で、長身、整った顔立ちから学園中の女子人気を集める王子様。
さらに、先月の全国模試で1位を取った天才。
「……で」
藤真くんは、私のスマホを軽く持ち上げたまま言う。
「黙っていてほしいのか?」
「ほ、ほしいです!お願いします!私、平和に生きたい!」
藤真くんは少しだけ首をかしげた。
その動きすら絵になるのが悔しい。
「黙っていてもいいけど、一つ条件がある」
条件。
その単語が出た瞬間、私の頭の中で警報が鳴り響いた。
え、私、なんかやばいことに巻き込まれそうなんだけど……!
――数時間前。
「浅見兄弟がこっちに来る!」
朝の廊下は、いつもよりざわざわしていた。
私立鳳凰学園は中高一貫校で、中学1年から高校3年まで同じ校舎で過ごす。
部活も生徒会も中高合同。
そして鳳凰学園には、全校生徒が認める伝説級の王子様たちがいる。
浅見兄弟。
タイプの違う王子様が四人。
しかも兄弟。
しかも全員、顔面が強い。
人生って不公平だな、と思うくらい強い。
「長男の浅見椿様!高3で生徒会長!優しくて人望も厚いのよね!」
「次男の浅見桃李様!高1で運動神経抜群!サッカーのユース代表ってマジやば!」
「三男の浅見藤真様!中3で全国模試1位!クールすぎて沼!」
「四男の浅見亜蘭くん!中1でアイドル顔負けの見た目!ファンサの神!」
相変わらず学園の女子たちは浅見兄弟の話題で持ちきりだ。
しかし、私はというと、教室の自分の席に座り、ノートに書きかけの譜面を広げていた。
――サビ、もう一段だけ跳ねたい。
でも跳ねすぎると歌が追いつけない。
バランス。バランス……。
「花音、今日も作曲?」
斜め前の席の友達が覗き込んでくる。
「うん。……趣味」
「相変わらず趣味が本気だよね」
本気です。
だって私の趣味は、ネットでは――
「こんなに頑張ってるならさ、ネットにアップしてみたら?もしかしたら、ボカロPの『F』みたいに人気になるかもよ?」
そういわれて思わず、ぎくりとしそうになった。
だめだめだめ、バレないようにしないと!
バレたら、恥ずかしいし、目立ちたくない……!
私はペンを走らせながら、教室の後ろで続く黄色い歓声を、右から左へ流した。
……流したはずだったのに。
「亜蘭く〜ん!」
廊下の向こうで、誰かが声を張り上げた。
次の瞬間、拍手が起きたみたいに、空気が弾ける。
亜蘭くんが、笑顔で手を振って、しかもウィンクまでしてみせたらしい。
らしい、っていうのは、私は見てないから。
……見てないけど、想像できてしまう自分が恐ろしい。
「きゃーっ!」
「今のウィンク、私に!?」
「みんなにだよ!そこが神なんだよ!」
……ファンサの範囲が広すぎる。
そこへ、四人のうちの一人が教室に入ってきた。
背筋が伸びていて、歩く音が静かで、目立つのに目立たない。
そして――
すっと、私の隣の席に座った。
浅見藤真くん。
同じクラス。
出席番号1番と2番で席も隣。
この事実だけで、クラスの女子の視線が痛い。
痛い。
皮膚が焼ける。
「……おはよ」
私は常識人として、とりあえず短く挨拶をした。
藤真くんは、教科書を机に置きながら一言。
「おはよう」
声が低くて、無駄がない。
おはようの中に、挨拶以上の情報が一切入っていない。
相変わらず、何考えているかわからないわ……。
すると、藤真くんは私の譜面に視線を落とした。
「それ」
「え?」
「オリジナル?」
「え、あ、うん、まぁ……その……」
心臓が跳ねる。
私は現実世界では普通の女子中学生として生活している。
ここで、正体不明の人気ボカロP『F』として活動していることを気づかれてはいけない。
「ふーん」
藤真くんは、それ以上突っ込まなかった。
突っ込まないんだ……。
……逆に怖い。
その『怖い』は、正解だったのかもしれない。
昼休み。
私は屋上へ向かった。
屋上は、私の避難所だ。
曲作りって、集中できる場所がないと詰む。
家は生活音が多いし、部屋の壁は薄いし、ヘッドホンの向こう側に世界があるのに、現実は私を放っておいてくれない。
スマホを開く。
『F』のアカウント。
新曲。
アップロード。
最後の確認をして――
よし。
今回の新曲もいい感じ。
そう思って浮かれていたのがいけなかったのだ。
「お前がFなのか?」
ああ、何で声掛けられるまで気づかなかったのよ、私!
――そして、現在に戻る。
「条件って……?」
私の声は、情けないくらい震えていた。
藤真くんは私のスマホを返しながら、淡々と言った。
「今度の学祭で、浅見兄弟四人でバンド演奏をする予定だ」
「……うん、知ってる。女子たちが今から成仏しそうなやつ」
「俺たちの演奏は念仏扱いなのか?まあ、いい。それでだ、そのバンドの曲を作れ」
「……は?」
「目玉としてオリジナル曲が必要なんだ」
「え、え、待って待って!私、バンド曲なんて作ったことない……!」
「同じ『曲』だ」
「いやいや!無理だよ!」
私は思わず一歩引いた。
藤真くんは一歩も動かない。
動かないのに、追い詰めてくる。
無表情の圧。
「できないなら、黙っている理由がない」
「へ?」
「『F』の正体は飯島花音ですって、ここから大声でバラしてやる」
「それ脅し!?」
「取引」
「言い換えても脅しだよ!」
藤真くんは、ほんの少しだけ目を細めた。
笑った……?
いや、笑ってない。
笑ってないけど、なんか……楽しんでる気がする。
天才って、たまに倫理観バグるのかな?
「……私の曲、ほしいの?」
「必要だ」
「必要って言い方、なんかやだ」
「じゃあ、ほしい」
「言い直すところ、律儀か!」
私のツッコミに、藤真くんは反応しない。
反応しないのに、心臓はさっきから忙しい。
イケメンの眼力、心臓に悪い。
治療費請求したい。
「いつまでに?」
私が観念して聞くと、藤真くんは容赦なく言った。
「デモは一週間後。歌詞は、その二日後」
「短っ!学祭ってもっと先だよね!?」
「準備期間は長い。でも曲がないと練習ができない」
私は頭を抱えた。
でも、抱えた頭の隙間から、現実が見える。
もし私が断ったら――藤真くんは秘密を守ってくれない。
守ってくれないというか、守る義務がない。
……詰んでる。
「……私が作ったってこと、誰にも言わないでよ」
「言わない」
「本当?」
「俺は、嘘が嫌いだ」
「その言い方、逆に嘘っぽいんだけど!」
藤真くんは、ポケットから自分のスマホを取り出した。
そして、画面を私に見せる。
『浅見兄弟バンド(仮)』
……グループチャット?
「え、なにこれ」
「作った」
「仕事が速いの怖い!」
私が叫ぶ前に、画面が動いた。
メンバー一覧に、4人の名前が並んでいる。
浅見椿
浅見桃李
浅見藤真
浅見亜蘭
そして、最後に――
招待中:飯島花音
「私の名前!」
「今、グループチャットに招待した。招待を受け入れたら取引成立ってことで」
「拒否権は?」
「あるけど、拒否したら叫ぶよ?」
「うわああああああ!わかったよ、ほら招待受け入れたから!グループチャット入ったから!取引成立させました!!」
藤真くんは相変わらず真顔のまま、核心だけ投げてくる。
わめいている私をよそに、通知が鳴り始めた。
【浅見椿:はじめまして、花音さん。急にごめんね。協力してくれるって藤真から聞いたよ】
椿様の文章優しすぎ!
へ?
てか、いつ協力するって聞いたの?
【浅見桃李:うおお!曲作れる人キター!花音ちゃんって呼んでいい!?あとテンション上がる曲で!】
テンションの圧がすごい!
そして距離が近い!
【浅見亜蘭:花音せんぱーい!よろしくですっ!キラキラしてて、みんなが手振りたくなるやつがいいなっ!✨✨✨】
絵文字多っ!
画面が眩しい!
そして追い打ちみたいに、スタンプが来た。
キラキラのハートが画面いっぱいに降ってくるやつ。
……目が乾きそう。
最後に、藤真くんが一言、打った。
【浅見藤真:放課後から活動開始】
こいつ、メッセージも冷たっ!
「……ねえ」
私は藤真くんの顔を見上げた。
「これ、私、断れない流れ?」
「合理的に考えて、断れない」
「合理的に考えなくていいから!もっと感情で考えて!ごめんね無理だよって、優しく言って!」
「善処する」
「あとさ、気になったんだけど、椿様からのメッセージに『協力してくれるって藤真から聞いたよ』て書いてあったけど、いつ話したの?話すタイミングなかったよね??」
藤真くんは、私のスマホを指で軽く叩いた。
「Fは、明るい曲が得意だろ」
「え、私の質問無視?」
「Fの曲、聴いた」
「聴いた!?え、ちょっと待って、私の曲、全部!?」
「全部は無理。時間が足りない」
「そこだけ現実的!」
私は顔が熱くなるのを感じた。
自分の作った曲を、現実の知り合いに聴かれている。
しかも隣の席の、無表情天才に。
……やばい。
恥ずかしい。
死にたい。
いや、死んだら曲が作れない!
「……わかった」
私は、敗北宣言みたいに言った。
「作る。作るけど!学園内で私がFだってこと、絶対に言わないで」
「言わない」
「あと、目立ちたくないから、浅見兄弟と一緒にいるところ、見られたくないんだけど……」
「無理だな」
「即答やめて!」
藤真くんは、珍しく少しだけ口元を緩めた。
気のせいかもしれない。
でも、気のせいじゃないと困る。
「目立つ。でも、秘密は守る」
「……それ、ずるい言い方」
「事実だ」
ずるいのは、その目。
まっすぐで、嘘がなさそうで、でも何を考えてるか分からない。
「放課後」
藤真くんが言った。
「音楽室。顔合わせをする」
「今日!?」
「今日」
「今日って言葉、そんなに軽く使わないで……!」
放課後。
私は一度教室に戻り、カバンを抱え、逃走ルートを脳内で三本引いた。
――正面玄関から帰る。
――裏門から帰る。
――窓から……いや、それは不審者だ。
どのルートにも、浅見藤真という監視カメラが置かれている気がした。
実際、音楽室とは逆方向を進んだ先の廊下の曲がり角で、本人が待っていた。
「……来た」
「ぎゃあああああ!逃げてないです!逃げてないです!」
「偶然、音楽室とは逆方向を歩いてたと?」
「うっ……!」
私は潔く藤真くんの後ろをついていくしかなかった。
歩くたびに、もう逃げられないと理解していく。
そして、藤真くんはいつも通り、静かに前を歩いていて、たまにちらっと後ろを振り向いて、私がついて来ているか無表情で確かめてくる。
……この人、恋愛ドラマの主人公みたいな顔して、やってることは取り立て屋なんだけど。
音楽室の前。
扉の向こうから、もう声が聞こえる。
「藤真、遅いよ。準備できてる?」
落ち着いた、優しい声。
扉が開き、そこにいたのは――
「花音さん、だよね?はじめまして」
浅見椿先輩。
噂通り、柔らかい笑顔で、話し方まで優しさそのもの。
ほんとに王子様だ……実在するんだ……。
「え、えっと、はじめまして……飯島花音です」
私がぎこちなく頭を下げると、椿先輩は安心させるみたいに頷いた。
「急に巻き込んでごめんね。でも、助かるよ」
その「助かる」が困るのに、椿様のために頑張りたくなっちゃう……!
「おっ、花音ちゃん!?来た来た!」
次に飛び込んできたのは、エネルギーの塊みたいな男子。
浅見桃李先輩。
サッカー部のバッグを肩にかけたまま、私のパーソナルスペースに突撃してくる。
「……ちょ、ちょっと先輩!近いです!」
「え?ごめん!でもさ、曲作れるってすごくない?俺、リズムしか分かんない!」
「それ、ドラム担当の自己紹介として完璧すぎません?」
私が半分泣きながら言うと、桃李先輩は「えへへ」と笑った。
笑顔が眩しい。眩しすぎて、目が焼ける。
「花音せんぱーい!」
今度は、音楽室の奥から小さな影が飛んできた。
浅見亜蘭くん。
中1なのに、存在が完成してる。
可愛いのに、圧がある。
「よろしくですっ!……あ、これ!あげますっ!」
亜蘭くんは、私の手に小さな飴を押し込んだ。
「え、なにこれ」
「仲良しのしるし!」
「さすが、ファンサの神!」
亜蘭くんは私に向かって、にこっと笑い、そして――ウィンク。
え、今の、私に……?
違う。
たぶん、呼吸してる相手全員にやってる……!
「亜蘭、やりすぎ」
藤真くんが淡々と言う。
亜蘭くんは「えへっ」と舌を出した。
可愛い。
可愛いが、眩しい。
この兄弟、眩しさの種類が全部違う……。
「じゃあ、早速」
椿先輩が手を叩いた。
「学祭のステージ、僕ら四人でバンドをやる。目玉企画だから、オリジナル曲が必要でね」
「うんうん!みんなで盛り上がるやつ!」
桃李先輩が頷く。
「サビでジャンプできるやつがいい!ジャンプ!」
「ジャンプの前にキメがほしい!」
亜蘭くんが手を挙げる。
「そこでウィンクすると、客席が落ちるやつ!」
「客席は落とさないで。安全第一で」
椿先輩が即ツッコミした。
生徒会長のツッコミ、理性の香りがする……。
三人の勢いに挟まれ、私は譜面用のノートを取り出す。
もう逃げられない。
覚悟を決めて、記録を残し始める。
「方向性は?」
藤真くんが訊いた。
ここだけ、空気がひゅっと冷える。
質問がシンプルすぎる。
「……明るい、感じ?」
私は恐る恐る言う。
すると亜蘭くんが「明るいの大好き!」と拍手し、桃李先輩が「テンション上げてこ!」と拳を握り、椿先輩が「歌詞は前向きだと嬉しい」と微笑む。
なんか、全部私に投げられた気がする。
「……えっと」
私は必死に頭を回した。
「観客は中高の全校生徒?」
「全校生徒。だから、かなりの人数になる」
椿先輩が答える。
「つまり、分かりやすくて、耳に残って、口ずさめて、でも――浅見兄弟らしい曲」
「トランプ関税より高い要求!」
私は悲鳴を上げた。
桃李先輩が肩をすくめる。
「ごめん!でもさ、花音ちゃんが作ったら絶対いけるって!」
「なんでそんなに自信満々なんですか……!」
亜蘭くんが両手をぱっと広げた。
「花音せんぱいなら、いけます!」
「やめて!全女子の嫉妬の炎で焼け死ぬ!」
「……飯島」
藤真くんが一言。
他の兄弟と違って、名字呼び。なんか、そこだけ現実に引き戻される。
「なに」
私がムッとして返すと、藤真くんは淡々と言った。
「仮タイトルを決めろ。方向性が定まる」
「いきなり!?」
「締切がある」
「……あなた、締切って言葉好きすぎない?」
私はノートの余白に、勢いで書いた。
『王子様たちと私の胃痛』
書いた瞬間、音楽室が静まり返った。
……やばい。
本音が出た。
「……胃痛?」
桃李先輩がきょとんとする。
椿先輩は、口元を押さえて笑いをこらえている。
亜蘭くんは「わかる!」と、なぜか全力で頷いた。
「却下」
藤真くんだけが、機械みたいに言った。
「……即却下!?」
「胃痛は今後使うな」
「胃痛がかわいそう!」
椿先輩が優しく仕切り直した。
「ごめん、笑っちゃった。じゃあ、仮でいい。花音さんの得意な明るさを、僕らのバンドに落とし込む。どうしたらいいかな」
その言い方が、ちゃんと相談で、私は少しだけ肩の力が抜けた。
脅しみたいな取引でも、結局、曲を作るのは私だ。
なら、私のやり方で――
「……じゃあ、テーマ、決めましょう」
私はペンを握り直した。
「学祭のステージって、お祭り騒ぎだけど、準備って意外と大変で。焦ったり、失敗したり、でも楽しかったり……そういう学園の今を歌にしたいです」
椿先輩が頷く。
「いいね」
桃李先輩が目を輝かせる。
「青春っぽい!」
亜蘭くんが手を叩く。
「キラキラだ!ウィンクできる!」
「できるのはお前だけだ」
藤真くんが冷静に落とす。
「じゃ、デモは」
椿先輩が言いかけた瞬間、藤真くんが遮った。
「明日の放課後。サビだけでいい」
「明日!?」
私の声が裏返った。
「花音さん、大丈夫?」
椿先輩が心配そうに覗き込む。
大丈夫じゃない。
でも椿先輩の前で「無理です」って言えるほど、私は強くない。
「……だいじょうぶ、です。たぶん」
「たぶんって言った!」
桃李先輩が笑う。
亜蘭くんがスタンプみたいに両手でピースする。
「ファイトですっ!花音せんぱい!」
藤真くんは無表情のまま、私のノートを一瞬だけ見て言った。
「逃げるなよ」
「逃げないよ!……たぶん!」
私の返事に、藤真くんの口元がほんの少しだけ動いた。
笑った、のかもしれない。
その「かもしれない」が、私の心臓に一番悪い。
今日の占い、1位だったんだよ……。
どこが!?
こうして私は、浅見兄弟バンドの作曲係(ほぼ人質)になった。
学祭まで、あと少し。
私の平和と心臓、持つかな。
その一言で、私――飯島花音の平和な中学生活は終わった。
ええ、終わりました。
今朝の占いランキング1位だったのに……。
もう占いなんて信じない!
「え、あ、なんで藤真くんが屋上に…!?あ、えっと、え、Fって何のことかなぁ~?」
私立鳳凰学園、昼休みの屋上。
風は気持ちいいし、人も少ないし、なによりスマホの電波がよく入る。
だから私はここで、こっそり――ほんとっーーーーに、こっそり――新曲のアップロードをしようとしていた。
……していたのに。
どうやら夢中で気づかなかったうちに、クラスメイトの浅見藤真くんが、屋上の扉を開けて入ってきて、私のすぐ後ろにいたらしい。
背、たっか。
眉、動かなっ。
感情、相変わらず読めない……。
「屋上の施錠当番。……それより」
そう言った瞬間、藤真くんの手が伸びて、私のスマホがすっと消える。
「ちょ、返して!それ私の命!」
ぴょんぴょん飛び跳ねて取り返そうとするけど、相手の腕が長すぎるし、身長差が現実を突きつけてくる。
私は中3の平均身長、相手は……たぶん、平均を遥かに超えている。
「命をちゃんと大切にしなかったお前が悪い」
「ぐぎゃあああああ!」
「こんなところで迂闊なことやって……。お前、よく今まで正体ばれなかったな」
「ち、違う!わ、私はFじゃない!私はFじゃない!!」
藤真くんは無表情のまま、私のスマホ画面を私に向けた。
『アカウント名:F 新曲をアップロード中 残り9%』
「このアカウント、今話題の謎のボカロP・Fだよな。しかも今、新曲を上げようとしてる」
……はい。詰みました。
藤真くんはため息もつかない。
無表情で、私をどんどん追い詰めていく。
「性別も年齢も不明。去年、突然現れた謎のボカロP。澄んだ曲調と明るい歌詞で人気になった……」
「藤真くん、Wikipediaみたいに言わないで!」
自分で言っておいて泣きたくなった。
いや、泣いてる場合じゃない。
私の秘密が、いまバレた。
浅見藤真――中学3年生で同じクラス、出席番号1番。
クールな雰囲気で、長身、整った顔立ちから学園中の女子人気を集める王子様。
さらに、先月の全国模試で1位を取った天才。
「……で」
藤真くんは、私のスマホを軽く持ち上げたまま言う。
「黙っていてほしいのか?」
「ほ、ほしいです!お願いします!私、平和に生きたい!」
藤真くんは少しだけ首をかしげた。
その動きすら絵になるのが悔しい。
「黙っていてもいいけど、一つ条件がある」
条件。
その単語が出た瞬間、私の頭の中で警報が鳴り響いた。
え、私、なんかやばいことに巻き込まれそうなんだけど……!
――数時間前。
「浅見兄弟がこっちに来る!」
朝の廊下は、いつもよりざわざわしていた。
私立鳳凰学園は中高一貫校で、中学1年から高校3年まで同じ校舎で過ごす。
部活も生徒会も中高合同。
そして鳳凰学園には、全校生徒が認める伝説級の王子様たちがいる。
浅見兄弟。
タイプの違う王子様が四人。
しかも兄弟。
しかも全員、顔面が強い。
人生って不公平だな、と思うくらい強い。
「長男の浅見椿様!高3で生徒会長!優しくて人望も厚いのよね!」
「次男の浅見桃李様!高1で運動神経抜群!サッカーのユース代表ってマジやば!」
「三男の浅見藤真様!中3で全国模試1位!クールすぎて沼!」
「四男の浅見亜蘭くん!中1でアイドル顔負けの見た目!ファンサの神!」
相変わらず学園の女子たちは浅見兄弟の話題で持ちきりだ。
しかし、私はというと、教室の自分の席に座り、ノートに書きかけの譜面を広げていた。
――サビ、もう一段だけ跳ねたい。
でも跳ねすぎると歌が追いつけない。
バランス。バランス……。
「花音、今日も作曲?」
斜め前の席の友達が覗き込んでくる。
「うん。……趣味」
「相変わらず趣味が本気だよね」
本気です。
だって私の趣味は、ネットでは――
「こんなに頑張ってるならさ、ネットにアップしてみたら?もしかしたら、ボカロPの『F』みたいに人気になるかもよ?」
そういわれて思わず、ぎくりとしそうになった。
だめだめだめ、バレないようにしないと!
バレたら、恥ずかしいし、目立ちたくない……!
私はペンを走らせながら、教室の後ろで続く黄色い歓声を、右から左へ流した。
……流したはずだったのに。
「亜蘭く〜ん!」
廊下の向こうで、誰かが声を張り上げた。
次の瞬間、拍手が起きたみたいに、空気が弾ける。
亜蘭くんが、笑顔で手を振って、しかもウィンクまでしてみせたらしい。
らしい、っていうのは、私は見てないから。
……見てないけど、想像できてしまう自分が恐ろしい。
「きゃーっ!」
「今のウィンク、私に!?」
「みんなにだよ!そこが神なんだよ!」
……ファンサの範囲が広すぎる。
そこへ、四人のうちの一人が教室に入ってきた。
背筋が伸びていて、歩く音が静かで、目立つのに目立たない。
そして――
すっと、私の隣の席に座った。
浅見藤真くん。
同じクラス。
出席番号1番と2番で席も隣。
この事実だけで、クラスの女子の視線が痛い。
痛い。
皮膚が焼ける。
「……おはよ」
私は常識人として、とりあえず短く挨拶をした。
藤真くんは、教科書を机に置きながら一言。
「おはよう」
声が低くて、無駄がない。
おはようの中に、挨拶以上の情報が一切入っていない。
相変わらず、何考えているかわからないわ……。
すると、藤真くんは私の譜面に視線を落とした。
「それ」
「え?」
「オリジナル?」
「え、あ、うん、まぁ……その……」
心臓が跳ねる。
私は現実世界では普通の女子中学生として生活している。
ここで、正体不明の人気ボカロP『F』として活動していることを気づかれてはいけない。
「ふーん」
藤真くんは、それ以上突っ込まなかった。
突っ込まないんだ……。
……逆に怖い。
その『怖い』は、正解だったのかもしれない。
昼休み。
私は屋上へ向かった。
屋上は、私の避難所だ。
曲作りって、集中できる場所がないと詰む。
家は生活音が多いし、部屋の壁は薄いし、ヘッドホンの向こう側に世界があるのに、現実は私を放っておいてくれない。
スマホを開く。
『F』のアカウント。
新曲。
アップロード。
最後の確認をして――
よし。
今回の新曲もいい感じ。
そう思って浮かれていたのがいけなかったのだ。
「お前がFなのか?」
ああ、何で声掛けられるまで気づかなかったのよ、私!
――そして、現在に戻る。
「条件って……?」
私の声は、情けないくらい震えていた。
藤真くんは私のスマホを返しながら、淡々と言った。
「今度の学祭で、浅見兄弟四人でバンド演奏をする予定だ」
「……うん、知ってる。女子たちが今から成仏しそうなやつ」
「俺たちの演奏は念仏扱いなのか?まあ、いい。それでだ、そのバンドの曲を作れ」
「……は?」
「目玉としてオリジナル曲が必要なんだ」
「え、え、待って待って!私、バンド曲なんて作ったことない……!」
「同じ『曲』だ」
「いやいや!無理だよ!」
私は思わず一歩引いた。
藤真くんは一歩も動かない。
動かないのに、追い詰めてくる。
無表情の圧。
「できないなら、黙っている理由がない」
「へ?」
「『F』の正体は飯島花音ですって、ここから大声でバラしてやる」
「それ脅し!?」
「取引」
「言い換えても脅しだよ!」
藤真くんは、ほんの少しだけ目を細めた。
笑った……?
いや、笑ってない。
笑ってないけど、なんか……楽しんでる気がする。
天才って、たまに倫理観バグるのかな?
「……私の曲、ほしいの?」
「必要だ」
「必要って言い方、なんかやだ」
「じゃあ、ほしい」
「言い直すところ、律儀か!」
私のツッコミに、藤真くんは反応しない。
反応しないのに、心臓はさっきから忙しい。
イケメンの眼力、心臓に悪い。
治療費請求したい。
「いつまでに?」
私が観念して聞くと、藤真くんは容赦なく言った。
「デモは一週間後。歌詞は、その二日後」
「短っ!学祭ってもっと先だよね!?」
「準備期間は長い。でも曲がないと練習ができない」
私は頭を抱えた。
でも、抱えた頭の隙間から、現実が見える。
もし私が断ったら――藤真くんは秘密を守ってくれない。
守ってくれないというか、守る義務がない。
……詰んでる。
「……私が作ったってこと、誰にも言わないでよ」
「言わない」
「本当?」
「俺は、嘘が嫌いだ」
「その言い方、逆に嘘っぽいんだけど!」
藤真くんは、ポケットから自分のスマホを取り出した。
そして、画面を私に見せる。
『浅見兄弟バンド(仮)』
……グループチャット?
「え、なにこれ」
「作った」
「仕事が速いの怖い!」
私が叫ぶ前に、画面が動いた。
メンバー一覧に、4人の名前が並んでいる。
浅見椿
浅見桃李
浅見藤真
浅見亜蘭
そして、最後に――
招待中:飯島花音
「私の名前!」
「今、グループチャットに招待した。招待を受け入れたら取引成立ってことで」
「拒否権は?」
「あるけど、拒否したら叫ぶよ?」
「うわああああああ!わかったよ、ほら招待受け入れたから!グループチャット入ったから!取引成立させました!!」
藤真くんは相変わらず真顔のまま、核心だけ投げてくる。
わめいている私をよそに、通知が鳴り始めた。
【浅見椿:はじめまして、花音さん。急にごめんね。協力してくれるって藤真から聞いたよ】
椿様の文章優しすぎ!
へ?
てか、いつ協力するって聞いたの?
【浅見桃李:うおお!曲作れる人キター!花音ちゃんって呼んでいい!?あとテンション上がる曲で!】
テンションの圧がすごい!
そして距離が近い!
【浅見亜蘭:花音せんぱーい!よろしくですっ!キラキラしてて、みんなが手振りたくなるやつがいいなっ!✨✨✨】
絵文字多っ!
画面が眩しい!
そして追い打ちみたいに、スタンプが来た。
キラキラのハートが画面いっぱいに降ってくるやつ。
……目が乾きそう。
最後に、藤真くんが一言、打った。
【浅見藤真:放課後から活動開始】
こいつ、メッセージも冷たっ!
「……ねえ」
私は藤真くんの顔を見上げた。
「これ、私、断れない流れ?」
「合理的に考えて、断れない」
「合理的に考えなくていいから!もっと感情で考えて!ごめんね無理だよって、優しく言って!」
「善処する」
「あとさ、気になったんだけど、椿様からのメッセージに『協力してくれるって藤真から聞いたよ』て書いてあったけど、いつ話したの?話すタイミングなかったよね??」
藤真くんは、私のスマホを指で軽く叩いた。
「Fは、明るい曲が得意だろ」
「え、私の質問無視?」
「Fの曲、聴いた」
「聴いた!?え、ちょっと待って、私の曲、全部!?」
「全部は無理。時間が足りない」
「そこだけ現実的!」
私は顔が熱くなるのを感じた。
自分の作った曲を、現実の知り合いに聴かれている。
しかも隣の席の、無表情天才に。
……やばい。
恥ずかしい。
死にたい。
いや、死んだら曲が作れない!
「……わかった」
私は、敗北宣言みたいに言った。
「作る。作るけど!学園内で私がFだってこと、絶対に言わないで」
「言わない」
「あと、目立ちたくないから、浅見兄弟と一緒にいるところ、見られたくないんだけど……」
「無理だな」
「即答やめて!」
藤真くんは、珍しく少しだけ口元を緩めた。
気のせいかもしれない。
でも、気のせいじゃないと困る。
「目立つ。でも、秘密は守る」
「……それ、ずるい言い方」
「事実だ」
ずるいのは、その目。
まっすぐで、嘘がなさそうで、でも何を考えてるか分からない。
「放課後」
藤真くんが言った。
「音楽室。顔合わせをする」
「今日!?」
「今日」
「今日って言葉、そんなに軽く使わないで……!」
放課後。
私は一度教室に戻り、カバンを抱え、逃走ルートを脳内で三本引いた。
――正面玄関から帰る。
――裏門から帰る。
――窓から……いや、それは不審者だ。
どのルートにも、浅見藤真という監視カメラが置かれている気がした。
実際、音楽室とは逆方向を進んだ先の廊下の曲がり角で、本人が待っていた。
「……来た」
「ぎゃあああああ!逃げてないです!逃げてないです!」
「偶然、音楽室とは逆方向を歩いてたと?」
「うっ……!」
私は潔く藤真くんの後ろをついていくしかなかった。
歩くたびに、もう逃げられないと理解していく。
そして、藤真くんはいつも通り、静かに前を歩いていて、たまにちらっと後ろを振り向いて、私がついて来ているか無表情で確かめてくる。
……この人、恋愛ドラマの主人公みたいな顔して、やってることは取り立て屋なんだけど。
音楽室の前。
扉の向こうから、もう声が聞こえる。
「藤真、遅いよ。準備できてる?」
落ち着いた、優しい声。
扉が開き、そこにいたのは――
「花音さん、だよね?はじめまして」
浅見椿先輩。
噂通り、柔らかい笑顔で、話し方まで優しさそのもの。
ほんとに王子様だ……実在するんだ……。
「え、えっと、はじめまして……飯島花音です」
私がぎこちなく頭を下げると、椿先輩は安心させるみたいに頷いた。
「急に巻き込んでごめんね。でも、助かるよ」
その「助かる」が困るのに、椿様のために頑張りたくなっちゃう……!
「おっ、花音ちゃん!?来た来た!」
次に飛び込んできたのは、エネルギーの塊みたいな男子。
浅見桃李先輩。
サッカー部のバッグを肩にかけたまま、私のパーソナルスペースに突撃してくる。
「……ちょ、ちょっと先輩!近いです!」
「え?ごめん!でもさ、曲作れるってすごくない?俺、リズムしか分かんない!」
「それ、ドラム担当の自己紹介として完璧すぎません?」
私が半分泣きながら言うと、桃李先輩は「えへへ」と笑った。
笑顔が眩しい。眩しすぎて、目が焼ける。
「花音せんぱーい!」
今度は、音楽室の奥から小さな影が飛んできた。
浅見亜蘭くん。
中1なのに、存在が完成してる。
可愛いのに、圧がある。
「よろしくですっ!……あ、これ!あげますっ!」
亜蘭くんは、私の手に小さな飴を押し込んだ。
「え、なにこれ」
「仲良しのしるし!」
「さすが、ファンサの神!」
亜蘭くんは私に向かって、にこっと笑い、そして――ウィンク。
え、今の、私に……?
違う。
たぶん、呼吸してる相手全員にやってる……!
「亜蘭、やりすぎ」
藤真くんが淡々と言う。
亜蘭くんは「えへっ」と舌を出した。
可愛い。
可愛いが、眩しい。
この兄弟、眩しさの種類が全部違う……。
「じゃあ、早速」
椿先輩が手を叩いた。
「学祭のステージ、僕ら四人でバンドをやる。目玉企画だから、オリジナル曲が必要でね」
「うんうん!みんなで盛り上がるやつ!」
桃李先輩が頷く。
「サビでジャンプできるやつがいい!ジャンプ!」
「ジャンプの前にキメがほしい!」
亜蘭くんが手を挙げる。
「そこでウィンクすると、客席が落ちるやつ!」
「客席は落とさないで。安全第一で」
椿先輩が即ツッコミした。
生徒会長のツッコミ、理性の香りがする……。
三人の勢いに挟まれ、私は譜面用のノートを取り出す。
もう逃げられない。
覚悟を決めて、記録を残し始める。
「方向性は?」
藤真くんが訊いた。
ここだけ、空気がひゅっと冷える。
質問がシンプルすぎる。
「……明るい、感じ?」
私は恐る恐る言う。
すると亜蘭くんが「明るいの大好き!」と拍手し、桃李先輩が「テンション上げてこ!」と拳を握り、椿先輩が「歌詞は前向きだと嬉しい」と微笑む。
なんか、全部私に投げられた気がする。
「……えっと」
私は必死に頭を回した。
「観客は中高の全校生徒?」
「全校生徒。だから、かなりの人数になる」
椿先輩が答える。
「つまり、分かりやすくて、耳に残って、口ずさめて、でも――浅見兄弟らしい曲」
「トランプ関税より高い要求!」
私は悲鳴を上げた。
桃李先輩が肩をすくめる。
「ごめん!でもさ、花音ちゃんが作ったら絶対いけるって!」
「なんでそんなに自信満々なんですか……!」
亜蘭くんが両手をぱっと広げた。
「花音せんぱいなら、いけます!」
「やめて!全女子の嫉妬の炎で焼け死ぬ!」
「……飯島」
藤真くんが一言。
他の兄弟と違って、名字呼び。なんか、そこだけ現実に引き戻される。
「なに」
私がムッとして返すと、藤真くんは淡々と言った。
「仮タイトルを決めろ。方向性が定まる」
「いきなり!?」
「締切がある」
「……あなた、締切って言葉好きすぎない?」
私はノートの余白に、勢いで書いた。
『王子様たちと私の胃痛』
書いた瞬間、音楽室が静まり返った。
……やばい。
本音が出た。
「……胃痛?」
桃李先輩がきょとんとする。
椿先輩は、口元を押さえて笑いをこらえている。
亜蘭くんは「わかる!」と、なぜか全力で頷いた。
「却下」
藤真くんだけが、機械みたいに言った。
「……即却下!?」
「胃痛は今後使うな」
「胃痛がかわいそう!」
椿先輩が優しく仕切り直した。
「ごめん、笑っちゃった。じゃあ、仮でいい。花音さんの得意な明るさを、僕らのバンドに落とし込む。どうしたらいいかな」
その言い方が、ちゃんと相談で、私は少しだけ肩の力が抜けた。
脅しみたいな取引でも、結局、曲を作るのは私だ。
なら、私のやり方で――
「……じゃあ、テーマ、決めましょう」
私はペンを握り直した。
「学祭のステージって、お祭り騒ぎだけど、準備って意外と大変で。焦ったり、失敗したり、でも楽しかったり……そういう学園の今を歌にしたいです」
椿先輩が頷く。
「いいね」
桃李先輩が目を輝かせる。
「青春っぽい!」
亜蘭くんが手を叩く。
「キラキラだ!ウィンクできる!」
「できるのはお前だけだ」
藤真くんが冷静に落とす。
「じゃ、デモは」
椿先輩が言いかけた瞬間、藤真くんが遮った。
「明日の放課後。サビだけでいい」
「明日!?」
私の声が裏返った。
「花音さん、大丈夫?」
椿先輩が心配そうに覗き込む。
大丈夫じゃない。
でも椿先輩の前で「無理です」って言えるほど、私は強くない。
「……だいじょうぶ、です。たぶん」
「たぶんって言った!」
桃李先輩が笑う。
亜蘭くんがスタンプみたいに両手でピースする。
「ファイトですっ!花音せんぱい!」
藤真くんは無表情のまま、私のノートを一瞬だけ見て言った。
「逃げるなよ」
「逃げないよ!……たぶん!」
私の返事に、藤真くんの口元がほんの少しだけ動いた。
笑った、のかもしれない。
その「かもしれない」が、私の心臓に一番悪い。
今日の占い、1位だったんだよ……。
どこが!?
こうして私は、浅見兄弟バンドの作曲係(ほぼ人質)になった。
学祭まで、あと少し。
私の平和と心臓、持つかな。