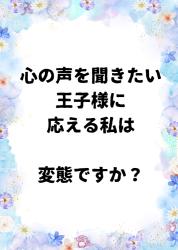その現象は、「若盲」と呼ばれる。通称は「首隠し」。発症した者は「首なし」になったと言われる。
老眼が年を重ねることで近くを見えなくなるのに対し、若盲は若さによって個の一部を失う病だと例えられることが多い。ある日突然、若者たちの首から上が、世界から隠されてしまう。
もっとも、それは呪いでも怪異でもない。あくまで一種の病であり、老眼のように、すべての人に等しく訪れるものでもなかった。
「運が悪かったね、御子柴くん」
「まぁな。でも、笑えるよな。発症した途端、誰からも告白されなくなったんだぜ?」
夕暮れの通学路。隣を歩く彼の制服の襟元から上には、何もなかった。そこにあるはずの端正な顔立ちも、何度か染め直した茶髪も、今はただ赤く染まった夕空が向こう側に見えるだけだ。
「……もててたもんね、御子柴くん。お陰で私は、またこうして普通に話せるようになって、嬉しいかな……って、ごめん。不謹慎だったよね」
「いいや。態度を変えないでいてくれた奴が本当のマブダチだ。綾瀬はまったく変わらないしな。分かりやすくて助かるよ」
「……私は、マブダチなんだ?」
嬉しいけれど、胸の奥が少しだけ痛む。
だって、私はずっと好きだったから。小学生の時も。中学生の時も。そして、彼の顔が世界から消えてしまった高校生の今だって。
「そんな顔するなよ。誤解されるぞ」
今までの私なら、彼を取り巻くその他大勢の女の子と同じだと思われるのが怖くて、こんな顔は見せられなかった。
──こんな、思わせぶりな顔。
でも、今なら御子柴くんの顔は私には見えない。蔑まれても、引かれても、顔がある時ほどには分からない。だから、私は少しだけ勇気を出せる。
「……誤解じゃないかもしれないけどねっ」
冗談かもしれないし、冗談じゃないかもしれない。そんな口調で彼の何もない首から上を見上げる。
「……首が戻ってくるのは、若さを失った頃なんだよな」
御子柴くんが話題を変えた。
やっぱり、私なんて対象外なのかな。
胸がピリリと痛む。
「うん、そうらしいね。三十歳を過ぎる頃には、みんな見えるようになるって」
「今の俺、酷いんだぜ。どうせ見えないだろって髪もセットしてねーし、伸びてきたらハサミで適当に切ってる。たぶん、めちゃくちゃ斜めのオカッパだ」
「あはは! それはちょっと見てみたいかも。可愛い気がする」
「みっともないだけだよ」
「えー、絶対に可愛い。謙遜しないでいいのに」
「してねーよ」
コンっと額を小突かれる。それがすごく嬉しい。こんなふうに気安くしてもらえて、チョロい私はすぐに彼を好きになってしまった。
駅へ続く坂道。御子柴くんが鞄からマーブルチョコを取り出すと、慣れた手つきで口元へと放り込んだ。
彼の手から離れた色鮮やかな粒が、虚空へと消える。直後、カリッと乾いた咀嚼音が響いた。
「お前にもやるよ」
彼の手が私の唇へと伸びる。指先がわずかに触れ、甘い感触が舌の上に転がった。
「わ、たしも……御子柴くんにあげたい」
「……今、食べてるけど」
「私の手で、あげたいの」
自分でもどうかしていると思う。
私は御子柴くん自身が好きなのか、それとも首なしの在り方に魅せられているのか。境界線が分からなくなっていく。
コロン、と私の手のひらに一粒のチョコが転がされた。許されたのだと思う。私は震える指でそれを摘まむと、彼の首の断面のさらに上へと掲げた。
指先が、何もない空間に吸い込まれる。
そこには柔らかい弾力と、湿った感触があって。
──このまま、指を。
もっと奥まで入れたら、私の指も彼の一部として世界から隠されるのだろうか。
「……えっちな顔してる」
「え……っ?」
掠れた声が、すぐ近くで聞こえた。
「俺が何か食べてる時、いつもえっちな顔するなと思ってたけど……今日はいつもの比じゃねーな」
「え、う、うそ!」
かぁっと顔が火照る。
「お前、首なしフェチだろ」
「そっ、そんなこと……っ!」
否定しきれなかった。
「首なしなら、誰でもいいのか?」
その問いに、心臓が跳ねた。
見えない誰か。顔も分からない誰かの、暗闇のような口の中に指を入れる。想像しただけで吐き気がする。
「いや! 絶対にそれはいや! 気持ち悪い! 御子柴くんのじゃないといや!」
「……なんだそれ」
「あ」
叫んでから気づく。
これでは、ただの告白だ。
「俺と付き合いたいのか?」
真っ直ぐな問いに、足が止まる。
頷けば、彼を独占できるのだろうか。
でも……。
「……もし付き合えるなら、卑怯かなって思うの」
「卑怯?」
「だって、御子柴くんが首なしにならなければ、もっと可愛い子と付き合えたでしょ。この病気を利用して、私みたいな取り柄のない子が彼女になれるなんて、卑怯だよ」
「取り柄、なくはないだろ」
「えっ?」
期待を込めて、そこにあるはずの瞳を見上げる。
「……えっちな顔が、すごくえっちなところとか」
「もー!!!」
冗談で返されたのが悔しくて、涙が出そうになった。今のはすごく期待したのに。
ふわりと髪に彼の手が触れた。
残っている首のラインが近づき、世界との境界線が迫る。
唇に、熱い、柔らかな何かが触れた。
「ま、待って。今の、って。待って待って!」
「何があったんだろうな」
「えええええーっ!」
「見えないのって不便だよな」
「わ、私、は、初めてだったのに……っ!」
「あ」
「それに、口、半開きだったし!」
「そこかよ!?」
「やり直し! やり直しをお願いします!」
彼の顔は見えない。
けれど、私と同じくらいに赤くなっていたらいいなと思う。
「……見えないと、不便だよな」
彼はもう一度、噛みしめるように言った。
「何が起きたのか分からない」
「さ、さすがに分かるけどっ」
「俺が何をしたのか、お前が何をしてほしいのか……言葉で教えてくれたら、もう一回してやるよ、桃香」
彼が初めて私を名字ではなく名前で呼んだ。
どうしようどうしよう。私も彼のことを、司くんって名前で呼んだ方がいいのかな。えっとえっと、キスして欲しいの司くんって言えばいいのかなっ! わっわっ、恥ずかしいよ。
「もーもか。待ってるんだけど」
「心の準備するまで待って!」
私たちはこの日、恋人になった。
彼が再び「顔」を取り戻すまで、彼はどんな表情で私を見るのだろう。
《完》
老眼が年を重ねることで近くを見えなくなるのに対し、若盲は若さによって個の一部を失う病だと例えられることが多い。ある日突然、若者たちの首から上が、世界から隠されてしまう。
もっとも、それは呪いでも怪異でもない。あくまで一種の病であり、老眼のように、すべての人に等しく訪れるものでもなかった。
「運が悪かったね、御子柴くん」
「まぁな。でも、笑えるよな。発症した途端、誰からも告白されなくなったんだぜ?」
夕暮れの通学路。隣を歩く彼の制服の襟元から上には、何もなかった。そこにあるはずの端正な顔立ちも、何度か染め直した茶髪も、今はただ赤く染まった夕空が向こう側に見えるだけだ。
「……もててたもんね、御子柴くん。お陰で私は、またこうして普通に話せるようになって、嬉しいかな……って、ごめん。不謹慎だったよね」
「いいや。態度を変えないでいてくれた奴が本当のマブダチだ。綾瀬はまったく変わらないしな。分かりやすくて助かるよ」
「……私は、マブダチなんだ?」
嬉しいけれど、胸の奥が少しだけ痛む。
だって、私はずっと好きだったから。小学生の時も。中学生の時も。そして、彼の顔が世界から消えてしまった高校生の今だって。
「そんな顔するなよ。誤解されるぞ」
今までの私なら、彼を取り巻くその他大勢の女の子と同じだと思われるのが怖くて、こんな顔は見せられなかった。
──こんな、思わせぶりな顔。
でも、今なら御子柴くんの顔は私には見えない。蔑まれても、引かれても、顔がある時ほどには分からない。だから、私は少しだけ勇気を出せる。
「……誤解じゃないかもしれないけどねっ」
冗談かもしれないし、冗談じゃないかもしれない。そんな口調で彼の何もない首から上を見上げる。
「……首が戻ってくるのは、若さを失った頃なんだよな」
御子柴くんが話題を変えた。
やっぱり、私なんて対象外なのかな。
胸がピリリと痛む。
「うん、そうらしいね。三十歳を過ぎる頃には、みんな見えるようになるって」
「今の俺、酷いんだぜ。どうせ見えないだろって髪もセットしてねーし、伸びてきたらハサミで適当に切ってる。たぶん、めちゃくちゃ斜めのオカッパだ」
「あはは! それはちょっと見てみたいかも。可愛い気がする」
「みっともないだけだよ」
「えー、絶対に可愛い。謙遜しないでいいのに」
「してねーよ」
コンっと額を小突かれる。それがすごく嬉しい。こんなふうに気安くしてもらえて、チョロい私はすぐに彼を好きになってしまった。
駅へ続く坂道。御子柴くんが鞄からマーブルチョコを取り出すと、慣れた手つきで口元へと放り込んだ。
彼の手から離れた色鮮やかな粒が、虚空へと消える。直後、カリッと乾いた咀嚼音が響いた。
「お前にもやるよ」
彼の手が私の唇へと伸びる。指先がわずかに触れ、甘い感触が舌の上に転がった。
「わ、たしも……御子柴くんにあげたい」
「……今、食べてるけど」
「私の手で、あげたいの」
自分でもどうかしていると思う。
私は御子柴くん自身が好きなのか、それとも首なしの在り方に魅せられているのか。境界線が分からなくなっていく。
コロン、と私の手のひらに一粒のチョコが転がされた。許されたのだと思う。私は震える指でそれを摘まむと、彼の首の断面のさらに上へと掲げた。
指先が、何もない空間に吸い込まれる。
そこには柔らかい弾力と、湿った感触があって。
──このまま、指を。
もっと奥まで入れたら、私の指も彼の一部として世界から隠されるのだろうか。
「……えっちな顔してる」
「え……っ?」
掠れた声が、すぐ近くで聞こえた。
「俺が何か食べてる時、いつもえっちな顔するなと思ってたけど……今日はいつもの比じゃねーな」
「え、う、うそ!」
かぁっと顔が火照る。
「お前、首なしフェチだろ」
「そっ、そんなこと……っ!」
否定しきれなかった。
「首なしなら、誰でもいいのか?」
その問いに、心臓が跳ねた。
見えない誰か。顔も分からない誰かの、暗闇のような口の中に指を入れる。想像しただけで吐き気がする。
「いや! 絶対にそれはいや! 気持ち悪い! 御子柴くんのじゃないといや!」
「……なんだそれ」
「あ」
叫んでから気づく。
これでは、ただの告白だ。
「俺と付き合いたいのか?」
真っ直ぐな問いに、足が止まる。
頷けば、彼を独占できるのだろうか。
でも……。
「……もし付き合えるなら、卑怯かなって思うの」
「卑怯?」
「だって、御子柴くんが首なしにならなければ、もっと可愛い子と付き合えたでしょ。この病気を利用して、私みたいな取り柄のない子が彼女になれるなんて、卑怯だよ」
「取り柄、なくはないだろ」
「えっ?」
期待を込めて、そこにあるはずの瞳を見上げる。
「……えっちな顔が、すごくえっちなところとか」
「もー!!!」
冗談で返されたのが悔しくて、涙が出そうになった。今のはすごく期待したのに。
ふわりと髪に彼の手が触れた。
残っている首のラインが近づき、世界との境界線が迫る。
唇に、熱い、柔らかな何かが触れた。
「ま、待って。今の、って。待って待って!」
「何があったんだろうな」
「えええええーっ!」
「見えないのって不便だよな」
「わ、私、は、初めてだったのに……っ!」
「あ」
「それに、口、半開きだったし!」
「そこかよ!?」
「やり直し! やり直しをお願いします!」
彼の顔は見えない。
けれど、私と同じくらいに赤くなっていたらいいなと思う。
「……見えないと、不便だよな」
彼はもう一度、噛みしめるように言った。
「何が起きたのか分からない」
「さ、さすがに分かるけどっ」
「俺が何をしたのか、お前が何をしてほしいのか……言葉で教えてくれたら、もう一回してやるよ、桃香」
彼が初めて私を名字ではなく名前で呼んだ。
どうしようどうしよう。私も彼のことを、司くんって名前で呼んだ方がいいのかな。えっとえっと、キスして欲しいの司くんって言えばいいのかなっ! わっわっ、恥ずかしいよ。
「もーもか。待ってるんだけど」
「心の準備するまで待って!」
私たちはこの日、恋人になった。
彼が再び「顔」を取り戻すまで、彼はどんな表情で私を見るのだろう。
《完》