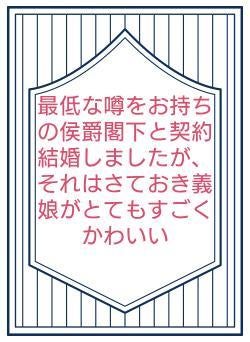「やあ、ルイーゼ嬢」
「ごきげんよう、オリヴァー様」
天気の良い午後、庭でフリンクと遊んでいるところにオリヴァーが訪ねてきた。オリヴァーが来ると真っ先にフリンクが気づいて、オリヴァー目掛けて走っていく。駆けていくフリンクを追い掛けると、その先でオリヴァーが笑っているのだ。すごいものだと感心しながら、ルイーゼはフリンクにじゃれつかれるオリヴァーに挨拶を返した。
「今日はフリンクに良いものを持ってきたよ」
「まあ、何かしら。よかったわねフリンク」
「これをどうぞ。ルイーゼ嬢、後でフリンクに与えてやっておくれ」
オリヴァーはフリンクにではなく、ルイーゼにラッピングされた贈り物を差し出す。ルイーゼが首を傾げながら受け取ると、オリヴァーは目を細めくちびるに人さし指をあてた。
「ここで与えて、もし変な場所に隠しては大変だから。この子が安心できる場所で開いて」
「はい、分かりました」
中身は何だろうかと思いながら、ルイーゼは贈り物を背中に隠す。オリヴァーはしばらくフリンクと遊んで、「じゃあ、またね」と帰っていった。ルイーゼはいつものように彼を見送って、足元のフリンクを見つめる。
「部屋に戻りましょうか、フリンク。何を頂いたのかしらね?」
しっぽを振って「きゃん!」と返事をするフリンクを連れて、ルイーゼは私室に戻った。玩具だろうか、それともおやつだろうか。少しわくわくしながらラッピングを開くと、中には手ごろな大きさの骨が入っていた。
「……骨?」
本当にこれを喜ぶのかしら? と首を傾げながらルイーゼはお行儀よく座るフリンクに骨を与えた。フリンクはくんくんと骨の匂いを嗅ぎ、どこかシレッとした顔で骨を咥えて歩いていく。そっと見守っていると、フリンクはベッドの下に骨を隠して、犬は何も隠していませんよ? という顔でルイーゼの元に戻ってきた。
「……見ていたから知っているのだけれど」
何のことですかね……ととぼけるような顔でフリンクは寝そべり、前足を舐めた。ルイーゼは思わず吹き出して、知らないふりに付き合ってあげることにする。よく分からないけれど、どうやら骨はフリンクの宝物になったらしい。使用人が捨ててしまわないよう伝えておかなければ、と考えながら、ルイーゼはくすくす笑ってフリンクの背中を撫でた。