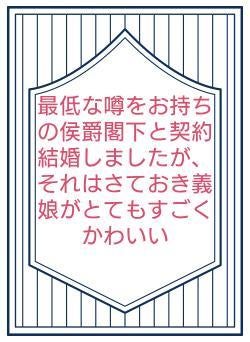『もうそろそろ殿下が様子見にいらっしゃるだろう』と父に聞かされてから数日後、いつものように庭で遊んでいたときに、フリンクが突然顔を上げて走り出した。
「待ってフリンク、どこへ行くの」
ルイーゼが止めても聞かず、フリンクは垣根を越えて走っていく。慌ててルイーゼが追いかけると、垣根の向こうから嬉しそうなフリンクの鳴き声と誰かが笑う声が聞こえてきた。
「ハハッ元気そうだね。私を覚えていてくれたの?」
聞き覚えのない声に、ルイーゼはおずおずと垣根から顔を覗かせる。視線の先で、少年と青年の間にいるような、まるで若木のようにしなやかな人がフリンクにじゃれつかれ笑っていた。さらさらと流れる艷やかな黒髪、芸術品のように整った相貌。その人はルイーゼに気づき、柔らかな笑顔を浮かべルイーゼに声をかけた。
「こんにちはレディ。私はオリヴァー、この子の様子を伺いにきたんだ」
「ごきげんよう」
ルイーゼはどぎまぎしながら垣根から姿を現す。
「ルイーゼ・フォン・ファルケンシュタインと申します。ようこそおいでくださいました、殿下」
——第二王子だ。ルイーゼはスカートをつまみ、深く礼をとった。
「オリヴァーで構わないよ。偶々時間が取れたからと、急に来てしまって悪かったね」
「いいえオリヴァー様。お越しいただき光栄です」
母親の元で茶会などには顔を出し始めたけれど、ルイーゼは社交界デビュー前。王子殿下と初めて直接言葉を交わすことに緊張しながらも、ルイーゼは落ち着いて見えるよう振る舞った。初々しい様に目元を和らげ、オリヴァーは優しくルイーゼに問いかける。
「この子に名を付けてくれた?」
「はい、フリンクと」
「そう。良い名を付けてもらったね、フリンク」
フリンクはまるで正式な主に再会できたことを喜ぶかのように、オリヴァーの足に前足をかけてしっぽを振っている。少し嫉妬しながら、それと『やっぱり連れ帰ろう』と言われるのではないかと不安を感じながら、ルイーゼは思わずスカートを握りしめて視線を揺らした。
「元気そうでよかった。大事にしてもらっているんだね。フリンクにいい家族が出来たことを嬉しく思うよ」
オリヴァーは片膝をついてフリンクを撫で回し、笑みを深める。フリンクは飛び跳ねながら「きゃん! きゃん!」と嬉しそうに返事をした。
「……それは」
「この子の顔をひと目見れば分かるよ。これからもずっと、仲良くしてやっておくれ」
オリヴァーが笑顔でルイーゼを見つめる。目を見開き、『家族になることを認められたのだ』と理解して——ルイーゼは頬を赤らめて震えるくちびるを押さえた。
「はい、はい……! もちろんです!」
「また会いに来てもいいかな? 時間が取れたとき、急に来ることになるけれど」
「ええ、歓迎いたします!」