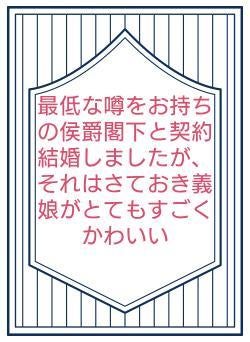「きゃああ!!」
翌朝、部屋に響いた侍女の悲鳴にルイーゼは驚いて飛び起きた。何事かと辺りを見回せば、扉の前には口に手をあてわななく侍女の姿が見える。視界の端をぴゅうと何かが横切って、目で追えば子犬が壁の隅に顔を押しあててうなだれていた。
ラグがぐちゃぐちゃにまくれ上がり、引き出しは開けられ中身が床に散乱している。そして——ソファーの上に飾っていたはずの、ルイーゼが大切にしているぬいぐるみは腕や足がもげかけて、綿が飛び出していた。部屋の惨状にルイーゼはぽかんと口を開ける。侍女がキッと眉をつり上げ、険しい声を出した。
「この、なんてことを!!」
「待ってちょうだい」
ルイーゼはつとめて落ち着いた声を出し侍女を制止した。
「何の準備もなしに部屋にいれたわたくしが悪いのだわ」
ルイーゼは寝台を降り、ゆっくりと子犬に歩み寄る。
「ですがお嬢様、叱らねばいたずらを繰り返します」
「いけないことをしている最中を見つけたら、きちんと叱るわ。……それにほら、見てちょうだいこの子の顔」
ルイーゼは思わず吹き出した。柔らかく撫でられた背におそるおそる振り向いた子犬は、耳をぺったりと伏せて眉間にしわを寄せ、なんとも情けない顔つきでルイーゼを見上げている。
「悪いことをしたと分かっているのよ。なんて情けない顔をしているの、お前」
ふぅーんとこぼされた鳴き声に、侍女も思わず苦笑を浮かべる。ボロボロになったぬいぐるみを拾い上げ、そっとルイーゼに歩み寄った。
「わたくしもお前が危なくないように気をつけるけれど、お前もあんまりないたずらをしてはだめよ」
変なものを口にしていないかとルイーゼが子犬を覗き込み顔に手を伸ばすと、ぴゅうぴゅうと鼻を鳴らし子犬はルイーゼの手にすり寄った。ルイーゼは子犬の頭を撫でて、「……それにしても」と思わず笑い声を上げる。
「あの逃げ足! すばしっこいったらなかったわ。そうだ、決めた!」
子犬の顔を両手で包み、ルイーゼは満面の笑みを浮かべる。
「フリンクにしましょう! お前の名前よ!」
「良い名をもらったわね、フリンク」
侍女も膝をついて、フリンクに声をかける。「大声を出してごめんなさいね」とフリンクに謝る侍女を笑顔で見上げ、それから彼女の手にある無残な姿のぬいぐるみを見つめ、ルイーゼは不安そうに眉を下げた。
「……直せるかしら?」
「ええ、お任せください。部屋も元通りにしてごらんにいれます」
「さすがね」
ルイーゼは安心して微笑む。もう大切なぬいぐるみを噛まれないように玩具を用意してあげなければ、と考えながら、ルイーゼはフリンクのほっぺたをむゆっともんだ。