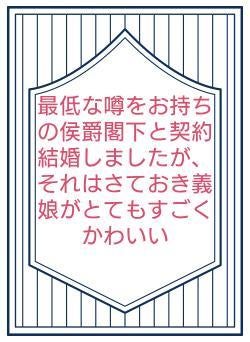オリヴァーが帰るまでの間、自分がいつも通りに振る舞えたかルイーゼは自信が持てなかった。どうしようもなく頬が赤らんで、声が上擦ったように思う。私室に戻り、ルイーゼはソファーに腰掛けて膝を抱えた。
好きになって、どうするというのだ。オリヴァーは王位を継ぐであろう王子殿下。そしてルイーゼは——家門を守るため婿をとらなければならない、公爵家の一人娘だった。
(こんな気持ち、知りたくなかった)
目が熱い。視界が滲む。ファルケンシュタイン公爵家は、ルイーゼが知る限り第一王子にも第二王子にも、特別肩入れをしていなかった。急に子犬をもらい受け、オリヴァーとの距離を詰め始めたのは、きっと、父がオリヴァーに付いたということだろう——そうルイーゼは考えていた。ならばルイーゼは、彼が有利になるよう動かされる立場なのだ。
「……ふ、ぅッ」
こらえきれない嗚咽が漏れる。こぼれ落ちた涙を追いかけるようにルイーゼは膝に顔を埋め、くちびるを噛み締めた。
「フゥン、フゥーン」
近くでフリンクの甘える声が聞こえる。そっと顔を上げると、フリンクがボールを咥えしっぽを振ってルイーゼを見つめていた。手を差し出せば、フリンクはルイーゼの手の上にボールを落とす。さあ投げてごらんなさいよ、犬が最高に楽しいことを教えてあげますから、みたいな顔をして、フリンクが「ワンッ」と鳴く。潤む瞳で弱々しく笑い、ルイーゼはボールをぽんと投げた。
フリンクが飛び跳ねてボールを追う。それからボールを咥えて、どうです! すごいでしょう!! とフリンクが瞳を輝かせてルイーゼの元にボールを運んでくる。ルイーゼはまたボールを投げてやって、フリンクは大はしゃぎでボールを追いかけて。
「…………ふふ、ふふふっ」
ルイーゼは涙をこぼしながら笑った。慰めてくれるフリンクが愛しくて。ボールひとつで大はしゃぎする様子がたまらなく可愛くて。
「ねえ、お前がいるならわたくしはきっと大丈夫だわ」
——例え、彼を王にするために婿が定められても。ルイーゼは涙を流し笑いながら、ボールを投げ続けた。