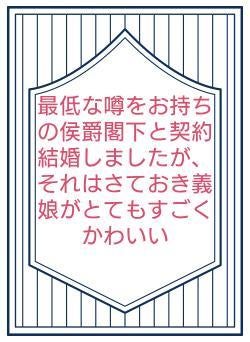ファルケンシュタイン公爵家当主である父が抱きかかえた可愛らしい子犬を前に、ルイーゼは目を瞬いた。
「ほらルイーゼ、犬だぞ。欲しがっていただろう?」
「もう、もうお父様ったら! 私はもう立派なレディなのよ!」
父が差し出す子犬を前に、ルイーゼは腰に手をあて頬を膨らませる。『犬が飼いたい』と、確かに幼い頃ねだった記憶があった。欲しがったのは三つか四つのころ。ぬいぐるみをねだるような、幼い欲求だった。叶えられぬまま年月が過ぎ、ルイーゼはもう『生きものを玩具のように欲しがってはいけない』と理解している。欲しいと思うものだって、ぬいぐるみから装飾品や書物に変化しているのだ。十二歳になったのに! と憤りながら、それでも隠しきれない喜びに目を輝かせてルイーゼは子犬を見つめた。
「レディになったからさ。今ならこの子を迎えても、きちんと世話をしてやれるだろう?」
「……もちろんよ!」
そういうことなら、とルイーゼは満面の笑みで頷く。レディと認められているのなら不満はない。だってもう、命の大切さも、飼い犬だからと勝手気ままに扱っていいわけがないことも、きちんと理解しているのだから。
ファルケンシュタイン公爵はゆっくりとしゃがんで、そっと子犬を床に降ろす。ルイーゼも床に膝をついて、伺うように子犬の顔を覗き込んだ。おそるおそる手を差し出すと、子犬はしっぽを振りながら甘えるようにすり寄ってくる。
「と言ってもまだお試しでね。この子がうちを気に入ってくれて、お前たちが仲良くなったら正式に飼おうと思っているよ」
「まだうちの子ではないの?」
「ああ、そうさ。オリヴァー殿下の飼い犬が子を産んでね、『娘が犬を飼いたがっている』と話したところ、それならばと預けてくださったんだ」
オリヴァー・カール・フォン・シュティグロート殿下。この国の第二王子だ。第一王子が病弱なため、王位を継ぐのは第二王子の彼ではないかと有力視されている。フンフンと鼻を鳴らし懸命にルイーゼの手の匂いを嗅ぐ子犬をしげしげと見つめ、ルイーゼはぽつりと呟く。
「お前、王家の犬なの?」
子犬は顔を上げ、犬はよくわかりませんね、と言いたげな顔でルイーゼを見つめ返した。「ちっとも高貴そうには見えないわ」と笑って、ルイーゼは子犬の頭を撫でてみる。くうんと鼻を鳴らし、手に頭をすりつける様子が愛らしい。「後日殿下が様子見にいらっしゃるから、それまで仲良くするんだよ」という父の言葉に頷いて、ルイーゼは子犬を撫でながら「ねえ、うちを気に入った? 気に入ったとおっしゃい」と何度も子犬に言い聞かせていた。
「ほらルイーゼ、犬だぞ。欲しがっていただろう?」
「もう、もうお父様ったら! 私はもう立派なレディなのよ!」
父が差し出す子犬を前に、ルイーゼは腰に手をあて頬を膨らませる。『犬が飼いたい』と、確かに幼い頃ねだった記憶があった。欲しがったのは三つか四つのころ。ぬいぐるみをねだるような、幼い欲求だった。叶えられぬまま年月が過ぎ、ルイーゼはもう『生きものを玩具のように欲しがってはいけない』と理解している。欲しいと思うものだって、ぬいぐるみから装飾品や書物に変化しているのだ。十二歳になったのに! と憤りながら、それでも隠しきれない喜びに目を輝かせてルイーゼは子犬を見つめた。
「レディになったからさ。今ならこの子を迎えても、きちんと世話をしてやれるだろう?」
「……もちろんよ!」
そういうことなら、とルイーゼは満面の笑みで頷く。レディと認められているのなら不満はない。だってもう、命の大切さも、飼い犬だからと勝手気ままに扱っていいわけがないことも、きちんと理解しているのだから。
ファルケンシュタイン公爵はゆっくりとしゃがんで、そっと子犬を床に降ろす。ルイーゼも床に膝をついて、伺うように子犬の顔を覗き込んだ。おそるおそる手を差し出すと、子犬はしっぽを振りながら甘えるようにすり寄ってくる。
「と言ってもまだお試しでね。この子がうちを気に入ってくれて、お前たちが仲良くなったら正式に飼おうと思っているよ」
「まだうちの子ではないの?」
「ああ、そうさ。オリヴァー殿下の飼い犬が子を産んでね、『娘が犬を飼いたがっている』と話したところ、それならばと預けてくださったんだ」
オリヴァー・カール・フォン・シュティグロート殿下。この国の第二王子だ。第一王子が病弱なため、王位を継ぐのは第二王子の彼ではないかと有力視されている。フンフンと鼻を鳴らし懸命にルイーゼの手の匂いを嗅ぐ子犬をしげしげと見つめ、ルイーゼはぽつりと呟く。
「お前、王家の犬なの?」
子犬は顔を上げ、犬はよくわかりませんね、と言いたげな顔でルイーゼを見つめ返した。「ちっとも高貴そうには見えないわ」と笑って、ルイーゼは子犬の頭を撫でてみる。くうんと鼻を鳴らし、手に頭をすりつける様子が愛らしい。「後日殿下が様子見にいらっしゃるから、それまで仲良くするんだよ」という父の言葉に頷いて、ルイーゼは子犬を撫でながら「ねえ、うちを気に入った? 気に入ったとおっしゃい」と何度も子犬に言い聞かせていた。