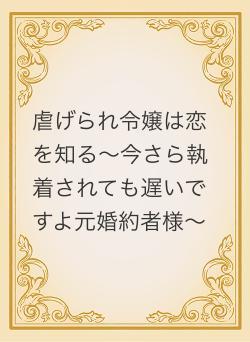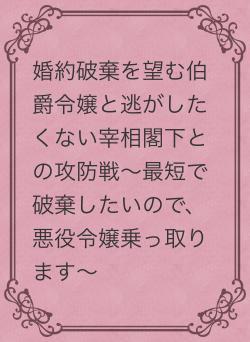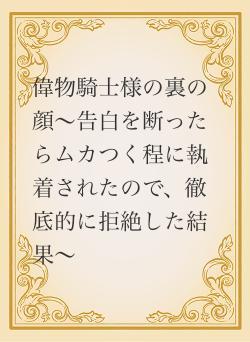「──見ぃつけた」
ほくそ笑みながら呟くのは、この国の宰相であるジェド・ブラケット。学園在学中に新たな領地を開拓。事業にも手広く手を出し、その能力を買われて宰相へと上り詰めた実力者。そして、誰もが認めるほどの超美形な人物ゆえに、女性の人気も凄まじい……かと思えばそうでもない。何故なら彼は、黙ってさえいればイケメンの視覚的満足男子。
──と言うのも、彼が口を出せば一瞬でその場は静まり返り、異様な空気に包まれた挙句にどんな異論も認められない。人を殺すことだって躊躇わない。顔色一つ変えずに采配を決め、国を動かす人物。冷静にして冷酷。
そんなジェドの視線の先にいるのが、友人らと談笑している令嬢、ルシル・カレッジだった。
***
今日は一年に一度の王家主催の園遊会。何十種類とある満開の花に囲まれた王城の庭園で美味しい料理に舌鼓を打ち談笑する。和やかで穏やかな時間。
──ただ一人を除いて。
(また…)
父であるカレッジ伯爵と共にこの園遊会へやって来たルシルだったが、会場に着いてから感じる射るような視線に悩まされていた。
(なんなの?)
辺りを見渡すが該当するような人物はおらず、気の所為だと自分に言い聞かせて談笑を続けていた。
ゾクッ!
鋭利な刃物で突かれたような鋭い視線を感じ、額に汗が滲み出てくる。鼓動が早まり、足が震える。
(これ…気の所為じゃない)
誰かが私を見てる。理由は分からないが殺気とは違う……これは、虎視眈々と獲物の動向を伺う獣の様な視線。逃がさないという意思が嫌でも伝わってくる。
人から恨まれるような人生は歩んでいないはずだけど、気付かない内に恨みを買っていたか?
それならそれで言ってくれれば謝罪くらい、いくらでもしてやる。陰からコソコソとされるより何倍もいい。
いつの間にか震えが止まり、不安が怒りに変わっていた。
(もう、一体、誰ッ!?)
勢いよく体を捻り視線を向けた。その視線はジェドの視線とぶつかった。
「え」
思わず間の抜けた声が出た。
まさか凝視していた人物が、鬼畜だと噂される宰相殿だとは露ほどにも思っていなかったからだ。
ジェドは「ふっ」と意味深な笑みを浮かべると、そのまま姿を消してしまった。
「ちょっと待ち──!」
「ルシルさん?」
「あ」
慌てて引き留めようとしたが、側にいた令嬢に呼び止められた。
「どうかなさって?」
「申し訳ありません。用事を思い出して……失礼します!」
引き止める令嬢の声を無視して、ジェドの後を追った。
(宰相様がどうして?)
学園で姿を見たことがあるが、声をかけた事もなければ掛けられたこともない。早い話が面識が一切ない。
「どこに行った?」
流石にドレスでは走りずらく、踵の高いヒールで城の中を走り回っては体力も限界。その場で立ち止まり息を整えていると、静まり返った廊下にカツン……と床を蹴る足音が聞こえた。
「まさか貴方から訪ねて来てくれるとは思いませんでしたね」
ゆっくり姿を現したのは、探していた人物ジェドだ。
初めて手の届きそうな距離で顔を拝見したが、確かに息を飲むほど美しい。だが、笑顔を浮かべているのに目が全く笑っていない。ミステリアスだと言えば聞こえはいいが、単に何を考えているのか分からない得体の知れない人と言った感じ。
「お初にお目にかかります。カレッジ伯爵の娘ルシルと申します」
貴族としての最低限の礼儀は忘れない。
ジェドは「ええ、存じておりますよ」などと平然と口にしてくる。
「宰相様が私になにかご用ですか?」
睨みつけながら問いかけた。この人相手に睨みをきかせる令嬢も珍しいだろうが、ここで怯んではいけない気がした。
そんな私を見て、ジェドは怒るどころか嬉しそうに口角を吊り上げた。
「場所を変えましょうか」
嫌な予感が頭をよぎるが、今更逃げることも出来ない。大人しくジェドの後を付いて行く。
「どうぞ」
行き着いた先は、ジェドの執務室。
その人の性格が表れているのか、随分と簡素な室内だった。あるのは執務用の机と椅子。それに整頓された本棚と二人掛けのソファーがあるだけ。高官である者らは高価で豪華な調度品などを買い集めては自分のステータスを上げて優位意識を保っている。この人もその中の一人だと思っていたけど……
「立ち話も何なんで、お座りください」
「いいえ、すぐにお暇しますので結構です」
「そうですか」
部屋の主が座るように促しているのに断るのは失礼だと思うが、いざとなった時にすぐに対処できて逃げれるように座るのを拒否した。私の考えを知ってか知らずか、ジェドは終始楽しそうな表情を浮かべている。
「では、単刀直入に伝えますね」
ゴクッと喉が鳴る。
「ルシル嬢、私と婚約しましょう」
ほくそ笑みながら呟くのは、この国の宰相であるジェド・ブラケット。学園在学中に新たな領地を開拓。事業にも手広く手を出し、その能力を買われて宰相へと上り詰めた実力者。そして、誰もが認めるほどの超美形な人物ゆえに、女性の人気も凄まじい……かと思えばそうでもない。何故なら彼は、黙ってさえいればイケメンの視覚的満足男子。
──と言うのも、彼が口を出せば一瞬でその場は静まり返り、異様な空気に包まれた挙句にどんな異論も認められない。人を殺すことだって躊躇わない。顔色一つ変えずに采配を決め、国を動かす人物。冷静にして冷酷。
そんなジェドの視線の先にいるのが、友人らと談笑している令嬢、ルシル・カレッジだった。
***
今日は一年に一度の王家主催の園遊会。何十種類とある満開の花に囲まれた王城の庭園で美味しい料理に舌鼓を打ち談笑する。和やかで穏やかな時間。
──ただ一人を除いて。
(また…)
父であるカレッジ伯爵と共にこの園遊会へやって来たルシルだったが、会場に着いてから感じる射るような視線に悩まされていた。
(なんなの?)
辺りを見渡すが該当するような人物はおらず、気の所為だと自分に言い聞かせて談笑を続けていた。
ゾクッ!
鋭利な刃物で突かれたような鋭い視線を感じ、額に汗が滲み出てくる。鼓動が早まり、足が震える。
(これ…気の所為じゃない)
誰かが私を見てる。理由は分からないが殺気とは違う……これは、虎視眈々と獲物の動向を伺う獣の様な視線。逃がさないという意思が嫌でも伝わってくる。
人から恨まれるような人生は歩んでいないはずだけど、気付かない内に恨みを買っていたか?
それならそれで言ってくれれば謝罪くらい、いくらでもしてやる。陰からコソコソとされるより何倍もいい。
いつの間にか震えが止まり、不安が怒りに変わっていた。
(もう、一体、誰ッ!?)
勢いよく体を捻り視線を向けた。その視線はジェドの視線とぶつかった。
「え」
思わず間の抜けた声が出た。
まさか凝視していた人物が、鬼畜だと噂される宰相殿だとは露ほどにも思っていなかったからだ。
ジェドは「ふっ」と意味深な笑みを浮かべると、そのまま姿を消してしまった。
「ちょっと待ち──!」
「ルシルさん?」
「あ」
慌てて引き留めようとしたが、側にいた令嬢に呼び止められた。
「どうかなさって?」
「申し訳ありません。用事を思い出して……失礼します!」
引き止める令嬢の声を無視して、ジェドの後を追った。
(宰相様がどうして?)
学園で姿を見たことがあるが、声をかけた事もなければ掛けられたこともない。早い話が面識が一切ない。
「どこに行った?」
流石にドレスでは走りずらく、踵の高いヒールで城の中を走り回っては体力も限界。その場で立ち止まり息を整えていると、静まり返った廊下にカツン……と床を蹴る足音が聞こえた。
「まさか貴方から訪ねて来てくれるとは思いませんでしたね」
ゆっくり姿を現したのは、探していた人物ジェドだ。
初めて手の届きそうな距離で顔を拝見したが、確かに息を飲むほど美しい。だが、笑顔を浮かべているのに目が全く笑っていない。ミステリアスだと言えば聞こえはいいが、単に何を考えているのか分からない得体の知れない人と言った感じ。
「お初にお目にかかります。カレッジ伯爵の娘ルシルと申します」
貴族としての最低限の礼儀は忘れない。
ジェドは「ええ、存じておりますよ」などと平然と口にしてくる。
「宰相様が私になにかご用ですか?」
睨みつけながら問いかけた。この人相手に睨みをきかせる令嬢も珍しいだろうが、ここで怯んではいけない気がした。
そんな私を見て、ジェドは怒るどころか嬉しそうに口角を吊り上げた。
「場所を変えましょうか」
嫌な予感が頭をよぎるが、今更逃げることも出来ない。大人しくジェドの後を付いて行く。
「どうぞ」
行き着いた先は、ジェドの執務室。
その人の性格が表れているのか、随分と簡素な室内だった。あるのは執務用の机と椅子。それに整頓された本棚と二人掛けのソファーがあるだけ。高官である者らは高価で豪華な調度品などを買い集めては自分のステータスを上げて優位意識を保っている。この人もその中の一人だと思っていたけど……
「立ち話も何なんで、お座りください」
「いいえ、すぐにお暇しますので結構です」
「そうですか」
部屋の主が座るように促しているのに断るのは失礼だと思うが、いざとなった時にすぐに対処できて逃げれるように座るのを拒否した。私の考えを知ってか知らずか、ジェドは終始楽しそうな表情を浮かべている。
「では、単刀直入に伝えますね」
ゴクッと喉が鳴る。
「ルシル嬢、私と婚約しましょう」