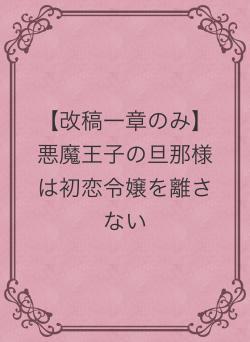※
僕が花音に『哀』の感情の欠如を告白してから、二か月が過ぎた。同じ悩みをもつ僕らの交際は順調で、ありのままの姿を受け入れてくれる花音の存在は日増しに大きく愛おしくなっていた。
(急がないと……)
バイトを終えた僕は店長に挨拶を済ませると、彼女に会いたくて足早に自宅アパートへ向かっていく。
(今日はハンバーグだって言ってたな)
花音から昨日、送られてきたメールを見ながら僕は口元を緩めた。
自宅アパートに到着するとすぐにエレベーターに乗り、玄関の扉を開く。
「おかえりなさい〜」
花音が駆け寄ってきて、部屋はハンバーグのいい匂いが漂っている。
「遅くなってごめん。美味しそうだね」
「お口に合うかわからないけど」
「もう何度も食べたから美味しいに決まってるよ」
「あ、そうだね」
「…………」
目の前にいるのは間違いなく彼女本人なのに、何故だろう。何処か違和感を感じる。声もいつもより少し高めで鼻にかかっているように思う。
「英太どうしたの? 早く食べよ?」
「……うん」
彼女が僕の腕に手を絡めると、料理の並んだダイニングテーブルへと連れて行く。
「あれ、ソース?」
「あ、ごめん。これしか売ってなくて〜」
テーブルには真新しい市販のソースのボトルが置いてある。僕は先ほど抱いた彼女への違和感が間違いないことを確信する。
「……花音はハンバーグにソースかけるんだ?」
「あったり前じゃん〜」
僕はその瞬間に、花音が腕に絡めている手を強く振り解いた。
「きゃ……っ、何すんのよ」
「……花音も僕もハンバーグにはケチャップなんだ」
「あ、えっと今日は……あたしソースな気分で」
「花音はあたしなんて言わないよ。君は誰?」
目の前の花音の顔が醜く歪む。彼女は髪をかきあげると、ため息を吐き出した。
「──もうバレたんだ」
僕が花音に『哀』の感情の欠如を告白してから、二か月が過ぎた。同じ悩みをもつ僕らの交際は順調で、ありのままの姿を受け入れてくれる花音の存在は日増しに大きく愛おしくなっていた。
(急がないと……)
バイトを終えた僕は店長に挨拶を済ませると、彼女に会いたくて足早に自宅アパートへ向かっていく。
(今日はハンバーグだって言ってたな)
花音から昨日、送られてきたメールを見ながら僕は口元を緩めた。
自宅アパートに到着するとすぐにエレベーターに乗り、玄関の扉を開く。
「おかえりなさい〜」
花音が駆け寄ってきて、部屋はハンバーグのいい匂いが漂っている。
「遅くなってごめん。美味しそうだね」
「お口に合うかわからないけど」
「もう何度も食べたから美味しいに決まってるよ」
「あ、そうだね」
「…………」
目の前にいるのは間違いなく彼女本人なのに、何故だろう。何処か違和感を感じる。声もいつもより少し高めで鼻にかかっているように思う。
「英太どうしたの? 早く食べよ?」
「……うん」
彼女が僕の腕に手を絡めると、料理の並んだダイニングテーブルへと連れて行く。
「あれ、ソース?」
「あ、ごめん。これしか売ってなくて〜」
テーブルには真新しい市販のソースのボトルが置いてある。僕は先ほど抱いた彼女への違和感が間違いないことを確信する。
「……花音はハンバーグにソースかけるんだ?」
「あったり前じゃん〜」
僕はその瞬間に、花音が腕に絡めている手を強く振り解いた。
「きゃ……っ、何すんのよ」
「……花音も僕もハンバーグにはケチャップなんだ」
「あ、えっと今日は……あたしソースな気分で」
「花音はあたしなんて言わないよ。君は誰?」
目の前の花音の顔が醜く歪む。彼女は髪をかきあげると、ため息を吐き出した。
「──もうバレたんだ」