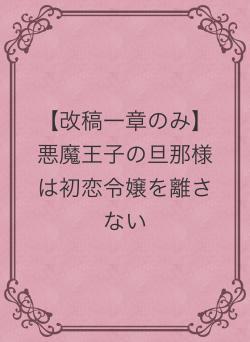「ふんっ、これでもまだ笑う?」
「……ふふ……」
「え?」
「……あはははははっ」
戸惑うような顔を見せる彼女たちが滑稽で、私は大きな声で笑い続けた。
それ以来、嫌がらせはなくなった。怒りの感情がなく、本来怒る場面で可笑しくなってしまう私を気味悪がって勝手に遠ざかっていった。
そうして一人きりの穏やかな日常を繰り返す中で、私はやがて感じた退屈と興味本位から恋人をつくることにした。いろんな人と告白されるままに付き合ってみたが、どの恋も長続きはしなかった。
『人形と付き合ってるみたい』
それがお決まりの別れ台詞だった。
「お人形、みたい……か」
さきほど美咲に言われたばかりだからか、その言葉が心をえぐるように痛む。
「──お人形みたい? それ誰に言われたの?」
「……え?」
見上げれば、いつのまにか注文の際に接客をしてくれた男性店員が立っている。
「あ、あの……」
「此処いい?」
反射的に頷いた私に微笑むと彼は真向かいに座り、手に持っていた新作のピーチスムージーをテーブルにコトンと置いた。
「……ふふ……」
「え?」
「……あはははははっ」
戸惑うような顔を見せる彼女たちが滑稽で、私は大きな声で笑い続けた。
それ以来、嫌がらせはなくなった。怒りの感情がなく、本来怒る場面で可笑しくなってしまう私を気味悪がって勝手に遠ざかっていった。
そうして一人きりの穏やかな日常を繰り返す中で、私はやがて感じた退屈と興味本位から恋人をつくることにした。いろんな人と告白されるままに付き合ってみたが、どの恋も長続きはしなかった。
『人形と付き合ってるみたい』
それがお決まりの別れ台詞だった。
「お人形、みたい……か」
さきほど美咲に言われたばかりだからか、その言葉が心をえぐるように痛む。
「──お人形みたい? それ誰に言われたの?」
「……え?」
見上げれば、いつのまにか注文の際に接客をしてくれた男性店員が立っている。
「あ、あの……」
「此処いい?」
反射的に頷いた私に微笑むと彼は真向かいに座り、手に持っていた新作のピーチスムージーをテーブルにコトンと置いた。