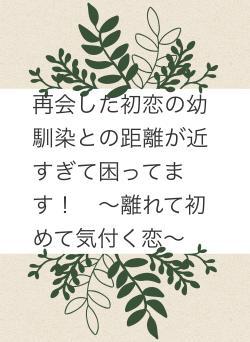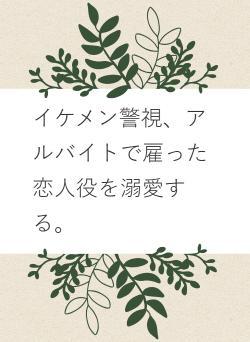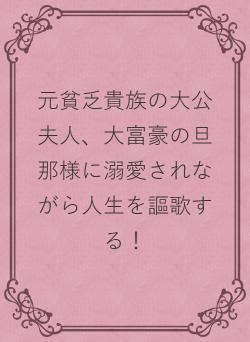そして、頼んだケーキが運ばれてきて、余計緊張が走った。この前は、テーブルマナーを指摘されてしまったから、今日は上手く出来るか心配で心臓がバクバク。けれど……目の前の泉谷さんは、私の事をじっと見てくる。
「……やっぱり瑠香さん、ちゃんとした先生にテーブルマナーを教わるべきだわ。だって、かの大企業月城グループCEOの息子で、会社経営をしている和真の妻なんですもの。和真が恥をかく前にした方がいいわ」
「……」
やっぱり、言われた……
「あなた、大学はどこなの? 当然、有名な大学よね?」
「……Y大学、です」
「あら? 私、聞いた事ないわね。どこの大学?」
一応住所を言ってみたけれど……知らないような口調で「あらそうなの……」と言ってくる。
どうして、こんな事を聞いてくるのだろうか。仲良くしたいと言ってここに連れてこられたから、よく知りたいのだと思うのだけれど……私はあまり、答えたくない。
私が一番に答えたくない質問をされる前に、帰りたい……
「じゃあ、ご両親は?」
「っ……」
「会社経営でもされてるのかしら? もしそうなら、もちろん私の知っている会社でしょうけれど」
それは一番、聞かれたくなかった質問。
両親はどちらも会社員で、もういません。だなんて、答えたくない。
「答えられないわよね。だって、いないんですもの」
その言葉で、この刺々しいような言葉の訳が分かった。
そして、緊張感が走り、両手が私のスカートを握りしめた。目の前の泉谷さんは立ちあがり、私の方にゆっくりとヒールを鳴らして近づいてくる。
「実の親がいない独りぼっちですものね。親戚に引き取られているらしいけれど、血の繋がっている家族なんて一人もいない事に変わりはないわ。平凡なあなたには、どう着飾ったところで平凡に変わりはない。むしろ醜いわ。どう頑張ったって平凡は平凡なのに無駄な事をするんですもの」
「っ……」
その時だった。膝が急に熱くなった。そして、すぐに気が付いた。私の目の前に置いてあった紅茶のカップが消えていて、それは泉谷さんの手にあり……中身がなくなっていた。私の膝に、かけられていたのだ。
「あら大変! 大丈夫?」
私に向けるその顔は……心配する気は一つもないと言っているように見えた。
私は、よく知ってる。この人とそっくりな人達を、何度も見た事があるから。
「でも、その姿、お似合いよ。親なしの凡人には」
いつもだ。いつも、私はそれを受け入れる事しか出来なかった。だって、私は言われたとおりに平凡で、何も出来ないんだから。