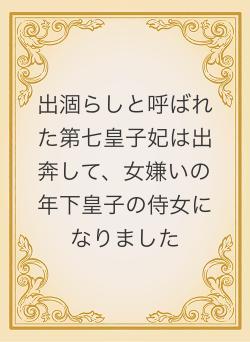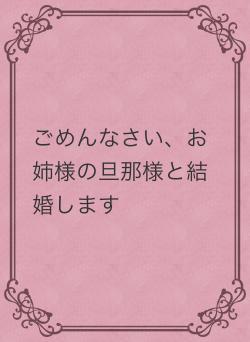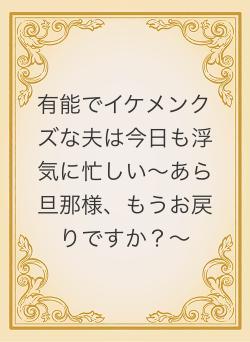「傘を持ってないかと思って寄ったんだ」
1つの傘に2人で入り、田んぼ沿いの一本道を歩いて行く。
「もう直ぐ私も女学生だよ!」
「大して勉強好きじゃないのに、そんなに嬉しいの?」
「もう勇さんの意地悪! でも勿論嬉しいに決まってるでしょう? だってあの憧れの徽章を身に付けられるんだもの!」
高等女学校に入学すれば、制服の腰のくびれにバンド型の徽章をつける事が出来る。女の子なら一度は憧れるものだ。
文子は浮き立ち、勇の持つ傘の中から抜けると濡れる事も気にせずに、ステップを踏むように駆けて行く。
「文ちゃん、折角迎えに来たのに濡れちゃうよ!」
少し焦った様子の勇が追いかけて来る。
だが彼が再び傘を差してくれる前に、頭上の雨は止んだ。
「誠ちゃん」
弟の誠一が背伸びをして文子に傘を差してくれていた。
「今帰り?」
随分と遅いねと続けようとして口を閉じた。何故なら誠一の手にはもう1本傘が握られていたからだ。恐らく一度家に帰った後に、わざわざ傘を持って迎えに来てくれたのだろう。
「迎えに来てくれてありがとう」
嬉しくなり笑顔で礼を述べると、誠一は持っていた傘を文子に押し付けて無言のまま元来た道を戻って行く。
様子を見守っていた勇と目が合うと彼は肩をすくめて笑う。
「勇さんもありがとう。ここまでで大丈夫だよ」
「頼りになるお迎えが来たからね」
傘からはみ出ないように、いつもより小さく勇へ手を振ると誠一の後を追いかけたーー
令和7年7月ーー
琴音は目を開けるとベッドから飛び起きる。そして窓を勢いよく開け放つ。朝から曇り空だが気分は晴々しい。今日から7月が始まる。
また夢を見た。
きっと昨日勇希と話をしていたから、傘のお迎えの日の夢だったのかも知れない。
「勇さんが、勇希くん……」
未だに信じられないが事実だ。
昨日あの後、思い切って勇希に文子の夢の話と共に勇の話をした。絶対に変人扱いされると覚悟していたが……。驚いた事に勇希も同じような話を始めた。それは昔から勇と文子の夢を見るというものだった。
夢の中の彼は勇という人物であるという。その話を聞いて躊躇いながらも琴音が見た夢を話すとーー
『それ僕も見たよ。その後、誠一くんが家に着く前に転んじゃって、拗ねて暫く部屋から出てこなくて大変だったよね』
実は今日見た夢には続きがある。それは自宅に帰り着く前に、誠一が道で転んでしまったのだ。怪我はなかったが泥塗れとなり拗ねてしまった。更に自宅に帰り綺麗な服に着替えるとそのまま暫く部屋から出てこなかった。父が言うには恥ずかしかったらしい。
この話を後日、文子が勇に話すと苦笑していた。その場面を勇希は夢で見たそうだ。
その後も確認の為、これまで見た夢の内容を伝えるとことごとく一致した。
『まさか琴ちゃんが文ちゃんだったなんて、信じられないよ! 嬉しいな』
『あ、でも、あくまで夢の中の話だから……』
『本当にそうかな』
『え……』
『確かに夢ではあるけど、僕は自分を勇だって思ってるよーー』
「琴音ー! 起きてるの? 遅刻するわよ!」
「あ、そうだっ、遅刻する!」
暫し物思いに耽っていると、1階から母が呼ぶ声がして我に返る。慌てて身支度を整えると1階へと下りて行った。
「おはよう」
「あ、おはよう」
教室に入ると勇希に声を掛けられた。
「今日も中里くんはお休み?」
「う、うん。でももう熱は下がったみたいだから、明日か明後日には登校出来ると思うって言ってた」
朝、学校に行く前に蓮にライルンをしてみた。すると熱は下がったがまだ怠くて動けないと返ってきた。
それにしても昨日の今日で気不味い。
朝起きた瞬間は浮き足立っていたが、いざ本人を目の前にすると妙に気恥ずかしく感じた。
それから今日は一日中、隣の席の勇希が気になって授業に全く集中出来なかった。来週は期末テストだというのにしょうもない。
「琴ちゃん、途中まで一緒に帰ろう」
「え、あ、うん……」
放課後、勇希と一緒に帰る事になったが、緊張して横を歩く彼の顔をまともに見れない。それに普段饒舌な勇希も口数が少ないように思えて、なんとも言えない空気が流れる。
「寄り道しようか」
そんな中、勇希からの提案で昨日に続いてニ頭山神社に立ち寄った。
「ねぇ、《《覚えてる》》? よく一緒にこの石段上ってお参りに来たよね」
「っーー」
勇希は石段を先に上り切ると振り返り笑った。その笑顔が勇そのもので目眩すら感じる。
「勇、さん……」
「うん」
自分はただ文子という少女の夢を見ているだけだ。例え夢の中では文子として存在していようとも、私は文子じゃない。そう思うのに、自分と文子の境目が曖昧になっていく。最近では感情も文子のものか自分のものかも分からない。
「ずっと僕の帰りを待っていてくれたんだよね。約束、果たせなくてごめん」
「ーー」
92段で足を止めていた琴音に勇希は真っ直ぐに手差し出す。
1歩2歩上り、最後の1歩を踏み締めるとその手を勢いのまま掴んだ。
「ただいま」
「お帰りなさい……勇さん」
彼の名前を呼んだ声は掠れていた。