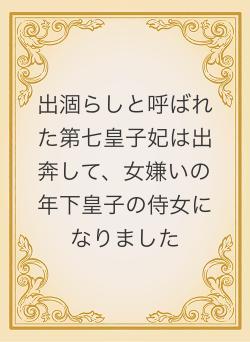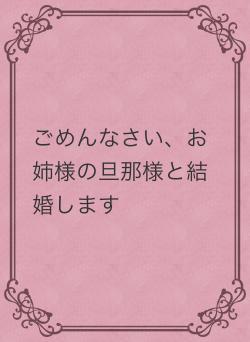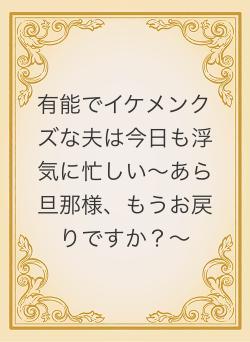稲見勇希が転校してきてから毎日が憂鬱だ。
これまで琴音に1番近い異性は自分だった。だが今はその立場が脅かされつつある。
出会ってまだ1ヶ月くらいの癖に、まるで昔から親しかったような顔をして図々しく彼女の隣にいる。
琴音も琴音で以前警告したにもかかわらず何の警戒もせずに受け入れている。
そして少し側を離れただけでやはりこうなった。
蓮が家庭科室の前扉を開けると、真っ先にその光景が目に飛び込んできた。
「琴ちゃん、何してるの」
無意識に声のトーンは普段よりも低くなる。
「蓮くん、お帰りなさい。今ね、”勇希くん”に勉強教わってて」
広い家庭科室の一角にあるテーブルに隣り合わせで座っている。その距離は肩が触れそうな程近い。
少しトイレに席を立っただけなのに、2人は急激に親密になったらしい。蓮が家庭科室を出る前はまだ”稲見くん”と呼んでいた。それが今は”勇希くん”に変わっている。
もし自分が猫だったならば、全身の毛を逆撫で唸り声を上げていただろう。そんなくだらない事を思う程、苛ついた。
「そこはボクの席だ」
「そんなの誰が決めたんだよ」
クラスでは運が悪くいつも席が隣にはなれずにいたので、せめて同好会の時は隣が良かった。なので2人しかいなかったが、向かい合わせではなく敢えて隣同士で座っていた。その場所を稲見に取られるなど許せる筈がない。
「退け」
「嫌だ。見て分からないのかよ。今、琴ちゃんに勉強ーーって、何するんだよ⁉︎」
”琴ちゃん”そう稲見が発した瞬間、心臓が大きく脈打ち完全に頭に血が上った。
頭で考えるよりも先に身体が勝手に動く。
稲見の首根っこを掴み引き摺るように持ち上げて、乱暴に床に座らせた。本当は放り投げてやりたいが、琴音が見ているので堪える。
普段は稲見の方が瞬発力は高いと思われるが、突然の出来事になされるがままになっていた。
「蓮くん」
そんな中、柔らかな声で名前を呼ばれ我に返った。声の方へと顔を向けると黒曜石のような黒く丸い瞳と目が合う。
「私が逆側に座るから、勇希くんと座って」
的外れな事を言われた蓮も勇希も呆然とするが、琴音は立ち上がると先ず勇希に「大丈夫?」と声を掛けて手を貸す。そして問題ない事を確認すると本当に逆側に移動してしまった。
「それじゃあ、蓮くん。悪い事をしたらごめんなさいしないとダメだよ」
「……ごめん」
「あーいや、まあ、僕も言い過ぎたし」
彼女は普段はおっとりしていて抜けているのに、こういった事柄には厳しい。
蓮は少し意地を張る癖があるので、昔からよくこの言葉を言われてきた。そして琴音から言われると不思議と素直になれる。
「じゃあ、続きやろう」
今日は通常通り和菓子を作る予定だったが、期末テスト前なので急遽勉強会に変更をした。本当は琴音と2人きりが良かったが、何故か勇希と隣り合わせに座り勉強するはめになってしまった。
蓮は憂鬱になりながらも、大人しく教科書とノートを開いた。
少し不穏さを残したまま下校時刻となり、帰路につく。琴音の手前、蓮も勇希も一時休戦といった所だ。
「ーーそれでね、勇さんが文子とぼたもちを食べてて」
僕と彼女だけの秘密の話。
琴音は物心ついた頃からとある少女の夢を見るという。
彼女は文子という昭和初期を生きた少女で、その文子には勇という幼馴染がいる。その夢の中では琴音は文子として存在している。
昔から夢を見る度に話をされてきた。初めはただの夢だと考えていたが、蓮自身が成長するに伴い考え方が変わった。もしかしたら琴音は文子という少女の生まれ変わりなんじゃないかと、そんな非現実的な事を考えるようになった。
突拍子もない発想で現実味はない。だが幼い琴音が昭和初期の生活や風景を知る筈がない。
以前テレビでどこかの国の子供がとある死んだ男の記憶を持っているという話を観た。前世の名前と言ったこともない街の名前と家の住所を言い当てた。やらせかも知れないが、それを思い出した。
『お父さんもお母さんも、みんな信じてくれないの』
大人達に話しても、当然誰も琴音の話に耳を傾けない。子供の戯言、テレビで観た動画で観たのだろうと片付けた。
『じゃあ、この事はボクと琴ちゃんだけの秘密にしようよ』
『どうして?』
『信じてくれないのに話しても悲しくなるだけだから。でもボクはもっと琴ちゃんの話聞きたいから、ボクにだけに教えてよ』
『うん!』
彼女を笑顔にしたい一心だった。なので深い意味はない。だが今はあの約束は自分と琴音を繋ぐ大切な絆だと思っている。
「勇さんって本当に優しくて誠実でーー」
最近、夢の話が増えた。
昔はたまに話す程度だったが、最近では毎日のように彼女の口から勇の名前が出る。
文子や勇が実在した人物なのかは分からないが、勇が少し羨ましく思えてしまう。
琴音は勇の話をする時、まるで恋をする乙女の顔をしている。夢相手に嫉妬するなど心底下らないと分かっているが、こればかりはどうにもならない。
「蓮くん」
「どうかした?」
「えっと、家に着いたよ」
「……」
考え事に集中し過ぎて、気付けば自宅前に立っていた。琴音は少し戸惑った様子でこちらを見る。
「……また、明日」
「うん、また明日ね」
だが声を掛けると直ぐに笑顔になり、大きく手を振りながら家の中へと入って行った。
隣に住んでいて毎日顔を合わせていて通信アプリであるライルンをすれば直ぐに既読がついて返してくれる。なのに琴音が自分へと背を向ける度に寂しい気持ちが込み上げてくるのは何故だろう。