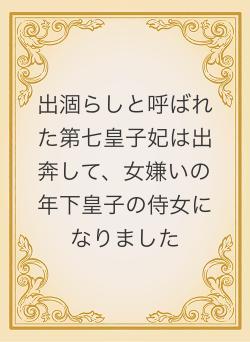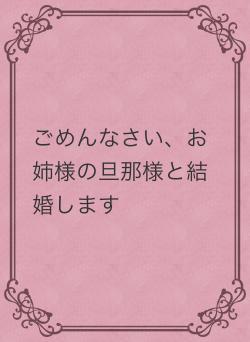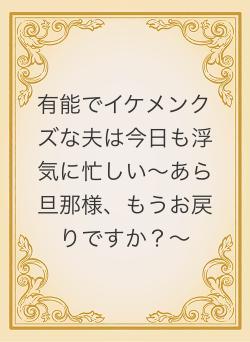「手と手を合わせて頂きます」
鴉のように真っ黒な艶やかな髪と焦茶の瞳の少年が見えるーー客間のテーブルには大皿にぼたもちが並べられ、文子と勇は隣り合い座り食べていた。
「文ちゃん、口にあんこがついてる」
「え、嘘⁉︎」
慌ててハンカチを取り出そうとすると、その前に勇が自分のハンカチを取り出し文子の口元を拭ってくれた。
「あ、ありがとう……」
「文ちゃんももう11歳なんだから、ぼたもちを綺麗に食べれるようにならないとね。慌てて食べるからだよ」
文子の家の客間で、勇と2人で母が作ったぼたもちを頬張っていた。
年に2回、春と秋のお彼岸だけぼたもちを食べる事が出来るが、正直もっと食べたいと思っている。毎日だって食べたい。文子は三度の飯よりぼたもちが大好きだ。
「だってほっぺが落ちちゃいそうなくらい美味しいんだもん〜」
「確かにおばさんが作ったぼたもちは美味しいけど、ぼたもちは逃げたりしないからさ。もっと落ち着いて食べな」
「勇ちゃん、厳しい」
「それと、呼び方」
「呼び方?」
「ボクももう中学生になるんだから、ちゃん付けはやめて欲しいんだ」
「じゃあ、なんて呼ぶの?」
「さんかくんかな」
「それなら……勇さん?」
慣れない呼び方に違和感を覚えつつ口にしてみると、勇は何故か顔を手で隠すとあからさまに背けた。
「どうしたの? 勇さん」
「な、何でもない」
彼は湯呑みを掴み、少し温くなったお茶を飲み干した。
「でも寂しい。勇さんが中学生になっちゃったら、もう一緒に学校に行けなくなるね
「仕方ないよ。ボクは文ちゃんより1つ上だからね」
「あ〜あ、勇さんと同い年に生まれたかった」
「家は近所だし、別に全く会えなくなる訳じゃないだろう」
「そうだけど……」
「これまで通り勉強なら教えてあげるから、いつでもうちにおいで。母さんも喜ぶしさ」
「うん」
勇の言葉が嬉しくて文子ははにかんだ。
「またいる……」
ボソリと呟くような声に振り返れば、少し開いた襖から弟がこちらを覗いていた。その顔は分かり易く不快そうに顔を歪ませている。
「誠ちゃん、お帰りなさい。お父さんとお出掛け楽しかった?」
3歳年下の弟の誠一とは血の繋がりはない。文子の実父は病で亡くなっており、母は文子が7歳の時に誠一の父と再婚をした。
「別に、普通……」
相変わらず素っ気ない態度を取られるが、意に介す事なく話を続ける。
弟が文子の事をどのように思っているかは分からないが、血の繋がりがなくても文子は誠一を大切で可愛い弟だと思っている。いつかお姉ちゃんと呼んで貰うのが夢だ。
「お母さんがぼたもち作ってくれたから誠ちゃんも一緒に食べよう」
笑って手招くと、渋々部屋の中へ入って来て円卓のテーブルの前にちょこんと正座する。お行儀が良くて思わず頭を撫でようとするが、軽く手を払われてしまう。
「誠一くん、お姉さんに対してその態度は良くないよ」
すかさず勇が注意をするが誠一は無視をして目の前のぼたもちに手を伸ばす。
ムッとした顔の勇が更に口を開こうとしたので、文子は軽く首を横に振ってみせた。
「文ちゃん、前から思ってたけど甘やかし過ぎだよ」
「誠ちゃんはまだ9歳だもの」
「もう9歳だよ」
「勇さん厳し過ぎ」
呆れ顔の勇に文子は唇を尖らせた。その隣では誠一が黙々とぼたもちを頬張っており、無表情だが弟も本当はぼたもちが大好きな事を知っている。
ふと開いていた窓から午後の眩しい日差しと穏やかな風が差し込んできて文子は目を細めた。