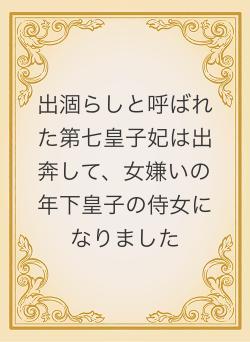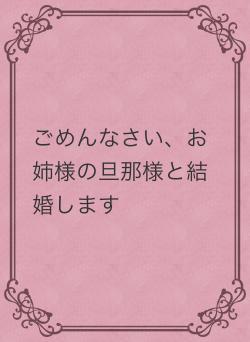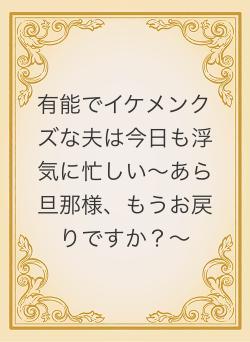沢山人が死に、遺体が集められ焼かれた。
独特な匂いに包まれ、悲しむ事も許されない中、骨と灰になった母や弟は埋葬された。
父や勇の身体は帰って来なかったので、埋葬出来ただけでも感謝すべきだろうか……。きっと2人は遠い異国の地で、埋葬される事もなくただ朽ち果てたに違いない。前に負傷して帰還した近所の男性がそんな話をしていた事をぼんやりと思い出した。
「眠れんの?」
住む家がなくなり、文子は暫く幸子の家でお世話になる事となった。
埋葬が終わった夜。中々寝付けず何度目かの厠に向かう。するとその帰りに廊下で幸子の母と出会した。居間に招かれ、ちゃぶ台の前に正座をすると湯呑みに水を淹れて出してくれた。
「文ちゃんが良ければ、ずっとウチにいたらええよ」
「そういう訳には……」
「いいんよ。私はね、文ちゃんの事も娘だって思ってるからね。幸子はね、文ちゃんと友達になる前は変わり者だって周りから言われていつも仲間外れにされててね。いつも独りぼっちだったんよ。だから文ちゃんが友達になってくれて、本当に感謝してる。ありがとうね」
幸子とは女学校で一緒のクラスになり友達となった。その前の事はあまり話したがらないので聞いた事はないが、意外な事実に少し驚く。
「文ちゃんのお母さんも本当に人柄のいいお人だった。随分と文ちゃんのお母さんには励まされたんだよ。とっても感謝してるんよ。だから私がお母さんの代わりに文ちゃんをお嫁に出してあげるからね。なんも心配はいらんよ。もし結婚したくないならずっとウチにいたらええ。文ちゃんの好きにしたらええんよ」
「おばさん……ありがとう、ございます……」
幸子の母の優しさに胸が押し潰されそうになる。嬉しくて苦しい。
小さな拳を握り締めた。
悲しむなんて間違っている。
父も母も弟も、勇も皆お国の為に命を捧げた。立派な事だ。名誉な事だ。娘として姉として幼馴染として誇らしく思う。
ぽっかり空いた心の穴を感じながらも、必死に脳裏に思い浮かべた。
私もお国の為に身を粉にして働き、立派に生きて立派に死のう。それが正義で正しい……。
昭和20年、7月後期ーー
夏も本番に差し掛かり、毎日が暑さとの戦いだ。朝から晩まで軍需工場で働き、クタクタになり帰宅する。
幸子やその家族、工場で共に働いている人達、瓦礫の街ですれ違う人々。誰も口には出さないが、その姿から極度の疲労感が窺えた。
ラジオからは相変わらず日本が敵の艦を沈めた、敵軍を撃破ったと報じられている。その度に皆、歓喜の声を上げるが文子の心の中には疑念が蓄積していった。
生活環境は悪化する一方で、物もなくなりいつもお腹を空かせている。こんな状況下で、本当に日本は優勢なのだろうか? 出征した男性達は次々と戦死している。残された女性や子供、年配者は栄養が足りずに死ぬ者もいれば病に倒れる者もいた。そして先の空襲で多くの死者を出した。私達は一体どこへ向かっているのだろう……?
毎日同じ日を繰り返す。
日の出と共に目覚め、簡単に身支度を整え工場に向かう。
だが最近は、先の空襲の後片付けの為に文子や幸子は駅にいた。学生達の姿もあり、皆で協力して瓦礫の撤去に当たっていた。
そんな時だった。辺りに空襲警報が鳴り響く。作業を中断して皆、一目散に走り出す。
瓦礫となった街の中を悲鳴を上げた人々が逃げ惑う。空から聞こえる機械音が焦燥と恐怖感を煽った。
「文ちゃん、早く‼︎」
幸子の背を追いかけるように必死に走っていたが、文子はふと足を止めた。
逃げてどうする?
頭の中にそんな疑問が浮かぶ。
鼓動が全身に広がっていく感覚がした。目を見開き身体が硬直する。瞬間、呼吸すら忘れた。
私は今、息をしている意味はあるのだろうか?ーー
もう帰る家もない。もう、誰もいない。
毎日毎日毎日、死ぬ物狂いで朝から晩まで働いて、辛くて苦しくても絶対にこの戦争に勝つのだと信じてきた。
でも今この瞬間、その全てが無意味に思えてしまった。戦争に勝っても負けてもーー誰も帰って来やしない。生きている意味理由が分からない。それならもう解放されて楽になりたい。
「文ちゃん⁉︎ 早く逃げないとっ」
ふと振り返り、足を止めた文子に気付いた幸子が叫ぶ。
「文ちゃん‼︎」と何度も叫ぶ声が雑音に混じり聞こえる。まるで他人事のようにそう思った。
ああ疲れた。お腹空いた。心も身体も限界で悲鳴を上げている。
家族も彼も、大切人達は皆死んでしまった。
私は何処へ帰ればいいのだろう。
ふと空を仰ぎ見る。生温い風が髪を揺らすのを感じる。日差しが照り付けていた。
耳に付く機械音が一層大きく鳴り響く。そしてまた空から光の雨が降る。
「もう一度、皆でぼたもち食べたかったな」
そう呟いた瞬間、私はその光に焼かれた。