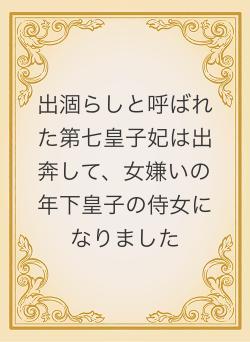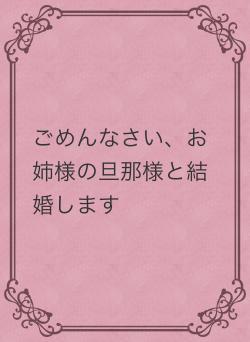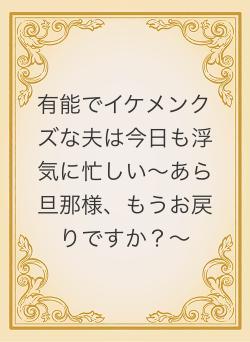昭和19年、春ーー
父が出征してから文子は暇を見つけては、二頭山神社にお参りをしに来ている。
春の真昼の柔らかな日差しに照らされながら、95段の石段1段1段を確りと踏み締めて上り切り、今日もまた神様に父が無事に帰って来るようにと祈った。本来はこんな願いはしてはいけない。父の無事ではなく日本国の勝利をただひたすら願うべきだ。なので母や弟にも言えない秘密だ。
「文ちゃん」
帰ろうと石段を下りようとした時、見慣れた人影が視界に映る。彼は踊り場に立ちこちらを見上げていた。
「勇さん、どうしたの?」
彼と会ったのはいつぶりだっただろうか。
最近忙しいのか、偶然会う事も家を訪ねても留守で会えていなかった。
文子は石段を軽快な足取りで下り勇の元へ行くと向かい合う。
「文ちゃんの家に行ったけど出掛けたって言われて。多分ここかなって」
「そうだったんだ、ごめんなさい。それにしてもなんだか久々だね」
「そうだね、1ヶ月……いや1ヶ月半振りか」
「忙しかったの?」
「まあ、このご時世だから色々とね」
「そっか、そうだよね」
暫し沈黙が流れた。
文子のこれからの事を勇にも知らせておいた方がいいだろう。そう思うが、自分自身にまだ躊躇いがあるせいか中々言い出せない。
「あのね、私……高等師範学校への進学取りやめたの」
「うん、人伝に聞いた」
「そうなんだ……。あ、でも全然平気! だってお父さん達兵隊さんがお国の為に頑張ってるんだから、私もお国の為に働かないと。勇さんはもう直ぐ高等学校に入学だね」
「……」
1度口にすれば他愛無く、次々に言葉が出てくる。文子は暗い気持ちを隠すように明るく笑って話すが、勇は黙り込みその表情は固い。
「勇さん?」
「……実はボクも進学はしないだ」
「え……」
「出征する事になった」
「ーー」
時間が止まったのではないかと錯覚をした。見開いた瞳を閉じる事が出来ず、唇を薄く開いたまま彼をただ見る。
風が吹きゆらゆらと桜の花弁が日差しと共に2人に降り注ぐのを他人事のように感じた。
「おめでとう、ございます」
夢か現か分からない。どこかぼんやりした思考の中でようやく声を絞り出す。
喜ばなくてはいけないと口角を上げて笑みを浮かべた。
おめでとうございますーー
この言葉を言う度に心が擦り減っていく。
誰にも言えない、いやこんな感情は間違っている、心の中でも思ってはいけない。私達は誇り高き大日本帝国の臣民だ。お国の為に……。
「ありがとう。父さんの意向で、進学を取りやめてお国の為に志願したんだ。兄さんの代わりに……。これで母さんも浮かばれる」
勇の父は軍需工場で所長を務めている。勇の兄はその補佐を担っているが、身体が弱く徴兵検査を通らなかった。その事に勇の父は酷く落胆し、また周りから侮蔑的に見られていた。その為、まだ徴兵年齢に達していない勇を進学させず志願兵として送り出すと決めたそうだ。
「文ちゃん」
「……」
「この戦争に勝ったら、僕と一緒になって欲しい」
「っーー」
まさか勇から結婚を申し込まれるとは思っておらず、文子は息を呑んだ。真っ直ぐな焦茶色の瞳に射抜かれ微動だに出来ない。緊張からか急に喉が渇き手に汗も滲む。
「勇さん、私ーー」
「文ちゃん」
驚きはしたが素直に嬉しかった。文子もまた自分の気持ちを伝えようとするが、言葉を遮られる。
「返事はその時まで保留にしておいて欲しい」
勇があまりに不安気な顔をするのでそれ以上は何も言えなかった。そしてそれから時間はあっという間に流れ、桜が散る頃勇は出兵の日を迎えた。
ある日の早朝、駅には沢山の人々の姿があった。のぼりに小さな国旗、幾度となく「万歳」と叫ぶ人々。見飽きた光景に、大分慣れてきた作り笑顔。また1人、大切な人を見送る。
「おめでとうございます」
「日向野勇、お国の為に1人でも多くの敵兵を討ち取って参ります!」
勇に最後の言葉を掛けると彼は凛々しく敬礼をし汽車に乗り込んだ。
窓に見えている彼の姿は汽笛と共に遠ざかって行く。駆け出したい衝動を抑え足を踏ん張った。すると左手にあたたかな温もりを感じた。反射的に顔を向けると、誠一が文子の手を確りと握り締めていた。だがこちらに視線を向ける事なくひたすら遠ざかって行く汽車を睨んでいた。
私達は現実を捻じ曲げたまま理不尽の中でいつまで生きなければならないのだろう。