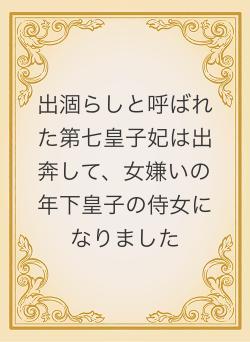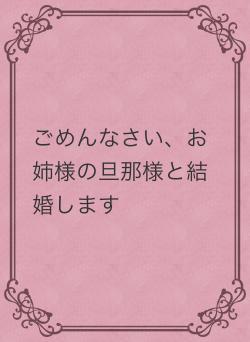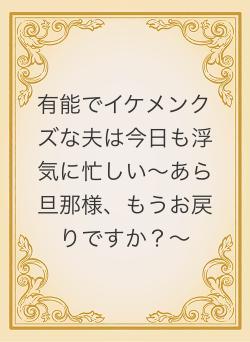夏休み7日目ーー
蓮は琴音と勇希と一緒に池辺里駅からバスで15分のショッピングモールであるスズモールに来ていた。
到着した時間はPM11時だったが、混む前に早めに昼食を食べる事にした。
「夏なのにたい焼き? っていうか昼ごはんそれだけ?」
「うん、あまり食欲ないからたい焼きなら食べれるかなって。それにここのたい焼きのあんこ本当に美味しいんだよ! 夏バテしてても食べれちゃうくらい」
フードコートのイスに座るとそれぞれの店舗で購入してきた物を食べ始める。
「そんなに美味しいんだ。じゃあ、一口頂戴」
琴音の言葉に勇希はニヤリと笑うとそんな図々しい要求をしてきた。何が「じゃあ」だ。蓮は苛立つ。
「食べたいなら自分で買えよ」
「一口食べたいだけだから1個は無理」
「なら諦めろ。卑しいな」
「だからちょっと味見したいだけなんだって」
「大人しくハンバーガーでも食べてろ」
「っていうか中里くんに言ってる訳じゃないし。ねぇ、琴ちゃん」
蓮は冷やしうどんを食べる手を止めると、勇希のハンバーガーが載ったトレーを押し付けるように押した。
「なにするんだよ⁉︎ 落ちるじゃんか」
「煩い」
「2人共、行儀悪いよ。それに喧嘩はダメ。そんなにたい焼き食べたいならもう1個買ってくるよ」
呆れたような怒ったような顔をしている琴音に、蓮も勇希も押し黙る。
別に蓮も勇希もたい焼きを食べたい訳でも食べさせたくない訳でもない。焦点は琴音の食べ掛けのたい焼きだ。本当にしょうもない話で、気まずいやら恥ずかしくなる。
その後勇希はたい焼きを諦めたらしく、黙々とハンバーガーを食べていた。蓮もうどんを無言で食べ終えると食器を下げに席を立つ。
「次、どこ見る?」
「ヴァンヴァンに行こう」
「稲見には聞いてない」
「えー、琴ちゃんヴァンヴァン嫌い?」
「ううん、私も行きたい」
「……じゃあ、それで」
無性に腹が立つが、琴音も行きたいのなら何も言えない。寧ろ行く以外の選択肢はない。ただ2人の行きたい場所が被った事実だけが腹が立った。
「これ可愛い〜」
スズモールの1階にあるヴァンヴァン。生活雑貨や本などが売っている。ただ変わった物が多く、たまに用途不明のものも見かける。
「本当だ、いいね」
同調する勇希に絶対に思っていないだろう! と突っ込みを入れたいが琴音の手前黙っている。
棚に置かれた茶色の物体を手にしている琴音を見て可愛いと思いながらも、相変わらず趣味が分からないと眉根を寄せた。
「はにわの縫いぐるみとか珍しいね」
「そうだよねー! 可愛いな〜。でも結構高いね」
50センチはあるだろうはにわの縫いぐるみは凡そ5千円だ。確かに学生の自分達からしたら結構な値段だ。いや、普通に大人でも高く感じるだろう。何しろはにわの縫いぐるみなど欲しい人間などそうはいない。正直蓮には5千円の価値があるようには思えなかった。だが琴音が欲しいなら話は別だ。
「欲しいなら買ってあげるよ」
「え、いいよ!」
「遠慮しなくてもいいよ。結構お小遣い貰ってるからさ」
「ダメだよ! お小遣いは自分の為に使わないと」
蓮が誕生日に買ってあげると言おうとすると、先に勇希がそんな事を言い出す。
「大丈夫だよ、月に3万貰ってるし」
「すごい、勇希くんの家お金持ちだね」
「う〜ん、まあ普通だと思うけど、じいちゃんがくれるんだよね」
勇希の言葉に琴音だけでなく蓮も目を見張る。蓮の月のお小遣いは6千円だ。使わなかった分は貯金しているが、そんなに余裕がある訳ではない。
これまで琴音といる時間が減ると思いアルバイトはしてこなかったが直ぐにでも探そうと考える。
「おじいさん?」
「今年で98歳なんだ」
「すごい、後2年で100歳だね!」
「まあね……。それよりさ、はにわ買ってくるよ」
「気持ちは嬉しいけど本当に大丈夫」
「僕が《《文ちゃんに》》プレゼントしたいんだ」
「っ……」
勇希の口から”文ちゃん”の名前が出た瞬間、怒りよりも寂しさが勝った。疎外感を覚えて胸がずきりと痛む。
琴音は戸惑った様子だがどこか嬉しそうに見えた。それがものすごく嫌だ。
「ーー」
目の前で2人の押し問答というなのイチャイチャを見せつけられても何も言えずに見ているしか出来なかった。