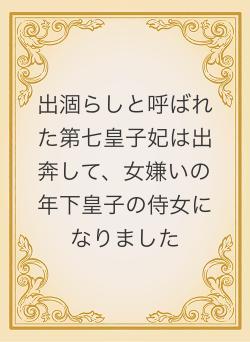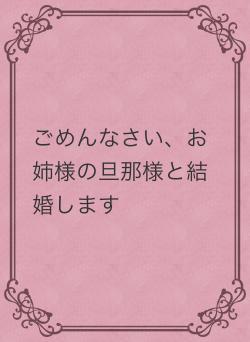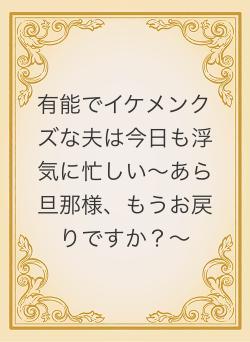線路を越えた池辺里駅の向こう側にあるかき氷屋は、閑静な住宅街を進むと突然姿を現す。小さくレトロな店構えの店先にはテーブルやイスが並べられ6人まで座る事が出来る。
「レモン牛乳って美味しいの?」
かき氷を食べる勇希を見て琴音は小首を傾げる。
昔からこの時期限定で通っているが、毎回疑問に思いながらもそのままになっていた。琴音は毎回あずきを頼むと決めているし、蓮はイチゴと決まっている。なので勇希が迷わずレモン牛乳を頼み少し驚いてしまった。
珍しく客の姿は琴音達しかおらず椅子に座る事が出来た。
「美味しいよ。っていうか食べた事ないんだ?」
「うん、だってあずきが1番だもん」
「文ちゃんらしいね。気になるなら、僕の少し食べてみる?」
あれから気まぐれのようにたまに文ちゃんと呼ばれているが違和感はない。寧ろこれが在るべき姿なのかも知れないとすら思えた。
勇希の半分程減った氷から、琴音は自分のスプーンを使い一口掬い上げ口に入れた。ふわふわの柔らかな氷とレモン風味とミルク、どこか懐かしい味のかき氷だった。
「どう美味しい?」
「うん、美味しいね!」
暑さも手伝い食べるスピードも上がり、あっという間に食べ終えた。
「よし、自転車に乗ってみて」
「え、無理無理!」
帰り道で自転車に乗るように促され慌てて拒否をするが、勇希からの圧に負けて取り敢えず跨ってみる。すると……。
「きゃっ、勇希くん⁉︎」
「行くよ!」
片足をペダルに乗せた瞬間、自転車は勝手に動き出した。勇希が荷台を押したからだ。確りと掴んだまま走り出し、閑静な住宅街をそのまま前進して行く。
「放さないでね⁉︎」
「ははっ、大丈夫!」
太陽が真上にきている中、生温い風と日差しを全身に浴びながら走って行く。何処からともなく蝉の声が聞こえてきて、ああ夏だなとしみじみ思った。
池辺里駅の側を流れる川沿いに自転車を止め、石段を下りて更に川へと近付く。勇希は鉄柵に手をつき川を眺めた。その隣に同じく琴音も手をつくと、一瞬ふわりと冷たい風が頬を掠めた。やはり水の近くは少し涼しく感じる。
「あー怖かった! 勇希くん、疲れたでしょう?」
「まあね。でも楽しかった」
互いに顔を見てなんとなく噴き出した。
「来週辺りに電車乗ってどっか出掛けてよう」
「どこかってどこ?」
「どっか遠くだよ」
「遠く……」
屈託のない笑みを向けられ目を細めた。
ああこれも覚えている。勇と文子が交わした些末な約束。結局その約束が果たされる事なはなかった。何故なら勇の母が亡くなったからだ。
昭和17年春ーー
『文ちゃんは怖がりだな。心配しなくても大丈夫だよ。直ぐに日本が敵軍を殲滅して勝利を収めるに決まってる。それより今度、休みになったら遠出しよう』
太平洋戦争が始まったばかりの頃だった。少し不安気にしていた文子に勇はそう言って軽く笑った。
『どこまで行くの?』
『遠くだよ。行ける所まで、遠く』
『遠く……』
2人で空を仰ぎ見て約束をしたが、その約束は果たされなかった。
戦争が始まり4ヶ月程、日本は初めて空爆を受けた。勇の母は、実母の体調が芳しくないと東京へ里帰りしており空爆に巻き込まれ帰らぬ人となってしまった。
その時の勇の気落ちした姿が暫く脳裏に焼きついて離れなかった。これまで穏やかだった勇の父は人が変わってしまい、それから少しずつ文子の周りは戦渦に巻き込まれていった。
誰が悪いのか?
直ぐに人は目に見える悪を探す。烏合の衆となりその悪を憎み、戦い、排除する。
同じ仲間にさえ疑いの目を向けて互いを見張り合い、国の隷属となった。反する意見の者達は赤とされ処罰される。
今ならおかしいと気付けるが、誰もが同じ思想を持つ中でそれが間違っているなど考えもしなかった。死の間際まではーー