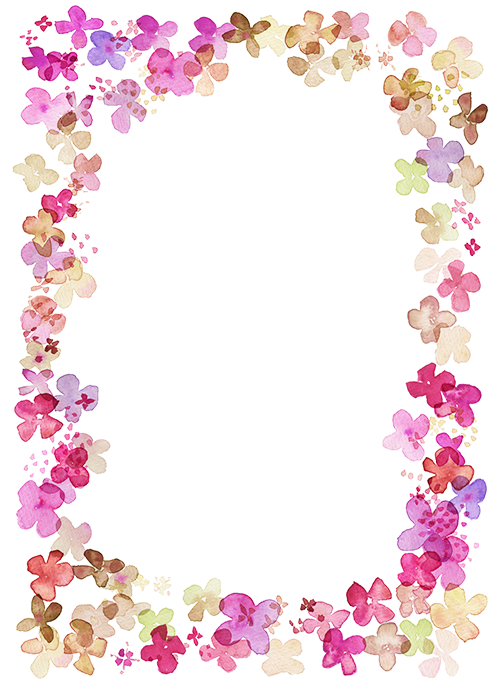そんな自分を浅ましく思う。
守るためとはいえ急に触れられて、彼女はどれほど動揺しただろうと反省する。
そんな気まずい雰囲気を緩和したのは、美味しそうな湯気をたてる雑炊だった。
「お待たせしました。いただきましょう」
笑顔の千沙さんと向き合って手を合わせて、口をつける。
「うん、うまいな」
だしの利いた優しい汁に鮭フレークの塩味が絶妙だった。
少し厚さが気になるネギも一緒に頬張れば、辛みがうまさを引き立てる。
「美味しい。遅い時間に食べるにはちょうどいいですね」
ふうふうと可愛く唇をすぼめて食べる千沙さんにも笑顔が見えて、ほっとする。
一緒に作ったとは言えないが、こうしてふたりで料理をして一緒に食べる日が来るなんて。
改めて喜びをかみしめていると、ふと脳裏に古い思い出がよみがえった。
「……そういえば、大学受験を控えていたころ、一度だけきみの実家で雑炊をいただいたことがあったな」
誠に教えてもらいたい教科があって、泊まり込みになったので、夜食として出してもらったのだ。
「でもタイミング悪く誠が眠ってしまって、俺が二人分いただくことになって」
「はい、おぼえています。ダイニングテーブルに座る湊さんの前にどんぶりふたつ並んでいて」
「そうそう。それをきみがびっくりした顔で見ていたんだよな」
守るためとはいえ急に触れられて、彼女はどれほど動揺しただろうと反省する。
そんな気まずい雰囲気を緩和したのは、美味しそうな湯気をたてる雑炊だった。
「お待たせしました。いただきましょう」
笑顔の千沙さんと向き合って手を合わせて、口をつける。
「うん、うまいな」
だしの利いた優しい汁に鮭フレークの塩味が絶妙だった。
少し厚さが気になるネギも一緒に頬張れば、辛みがうまさを引き立てる。
「美味しい。遅い時間に食べるにはちょうどいいですね」
ふうふうと可愛く唇をすぼめて食べる千沙さんにも笑顔が見えて、ほっとする。
一緒に作ったとは言えないが、こうしてふたりで料理をして一緒に食べる日が来るなんて。
改めて喜びをかみしめていると、ふと脳裏に古い思い出がよみがえった。
「……そういえば、大学受験を控えていたころ、一度だけきみの実家で雑炊をいただいたことがあったな」
誠に教えてもらいたい教科があって、泊まり込みになったので、夜食として出してもらったのだ。
「でもタイミング悪く誠が眠ってしまって、俺が二人分いただくことになって」
「はい、おぼえています。ダイニングテーブルに座る湊さんの前にどんぶりふたつ並んでいて」
「そうそう。それをきみがびっくりした顔で見ていたんだよな」