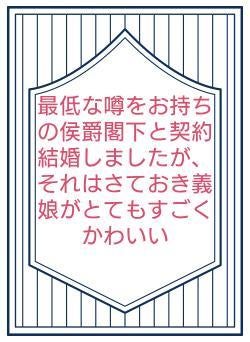夕食後私室に戻り、ふたりきりになったとたんヘレンがぽつりと呟く。
「ご覧になりましたか、あのなんとも気まずげなご様子……もしやその肩掛けは、浮気相手に関係するものでは……」
同じものを贈ったか、それともまさかお下がりなんてことは……! とヘレンが嘆く。
「まあまあ、良いではないの。もしそうだとしても、肩掛けに罪はないわ。本当に気に入ったの」
「お嬢様は!! 気にしなさすぎです!!」
「ヘレン、呼び名が戻っているわ」
「……申し訳ございません、エレオノール様」
「全く、奥様とは呼ばないのだから」
「愛人問題が解決するまで、私は断固としてエレオノール様を『奥様』とお呼びいたしませんよ!」
閣下もです! エレオノール様の前では『旦那様』とお呼びいたしません!! と憤慨するヘレンに苦笑を浮かべる。
「確証があるわけでもなし……それに構わないじゃないの、愛人のひとりやふたり」
「エレオノール様は!! 気にしなさすぎなんですよ!!」
妻の地位は揺るぎない。日々それを実感している。本当に気にすることなどないと思うのだけれど。
「……幸いと言うべきか、エレオノール様が閣下に恋をなさっておられないから」
首を傾げる私に、ヘレンがさめざめと嘆き始めた。
「そりゃあ、確かに政略結婚でございます。でも私はエレオノール様に幸せになっていただきたくて……それなのに最初からこのような疑惑だなんて……」
「ああっごめんね、ごめんなさいヘレン。ちゃんと考えるから」
両手で顔を覆い下を向くヘレンに、慌てて声をかける。ヘレンは「お考えになることがよいことなのかさえ、もう私には分かりません……」と嘆き、気を取り直して私に謝罪し、退室していった。
ヘレンが下がった後、窓の外を眺めひとり考える。確かにヘレンの言う通りだ。手紙は一往復するだけでも日を要し、三年の婚約期間に交わした手紙は数えるほど。手紙のやり取りを好ましく思っても——恋に落ちるきっかけはなかった。恋とは、婚約とはと考え書物を読み漁ったけれど、なるほどと感心するばかりで共感が持てない。
恋とは、なんだろうか。こうして穏やかに過ごし、家門繁栄すればよいのではないのかしら。跡目争いは避けたいけれど、私は『奥様』として尊重されているのだし……
それともいつか、許しがたく思う日がくるのだろうか。——思い悩む視線の先で、アラン様が宵闇の中別邸に向かっていった。
「ご覧になりましたか、あのなんとも気まずげなご様子……もしやその肩掛けは、浮気相手に関係するものでは……」
同じものを贈ったか、それともまさかお下がりなんてことは……! とヘレンが嘆く。
「まあまあ、良いではないの。もしそうだとしても、肩掛けに罪はないわ。本当に気に入ったの」
「お嬢様は!! 気にしなさすぎです!!」
「ヘレン、呼び名が戻っているわ」
「……申し訳ございません、エレオノール様」
「全く、奥様とは呼ばないのだから」
「愛人問題が解決するまで、私は断固としてエレオノール様を『奥様』とお呼びいたしませんよ!」
閣下もです! エレオノール様の前では『旦那様』とお呼びいたしません!! と憤慨するヘレンに苦笑を浮かべる。
「確証があるわけでもなし……それに構わないじゃないの、愛人のひとりやふたり」
「エレオノール様は!! 気にしなさすぎなんですよ!!」
妻の地位は揺るぎない。日々それを実感している。本当に気にすることなどないと思うのだけれど。
「……幸いと言うべきか、エレオノール様が閣下に恋をなさっておられないから」
首を傾げる私に、ヘレンがさめざめと嘆き始めた。
「そりゃあ、確かに政略結婚でございます。でも私はエレオノール様に幸せになっていただきたくて……それなのに最初からこのような疑惑だなんて……」
「ああっごめんね、ごめんなさいヘレン。ちゃんと考えるから」
両手で顔を覆い下を向くヘレンに、慌てて声をかける。ヘレンは「お考えになることがよいことなのかさえ、もう私には分かりません……」と嘆き、気を取り直して私に謝罪し、退室していった。
ヘレンが下がった後、窓の外を眺めひとり考える。確かにヘレンの言う通りだ。手紙は一往復するだけでも日を要し、三年の婚約期間に交わした手紙は数えるほど。手紙のやり取りを好ましく思っても——恋に落ちるきっかけはなかった。恋とは、婚約とはと考え書物を読み漁ったけれど、なるほどと感心するばかりで共感が持てない。
恋とは、なんだろうか。こうして穏やかに過ごし、家門繁栄すればよいのではないのかしら。跡目争いは避けたいけれど、私は『奥様』として尊重されているのだし……
それともいつか、許しがたく思う日がくるのだろうか。——思い悩む視線の先で、アラン様が宵闇の中別邸に向かっていった。