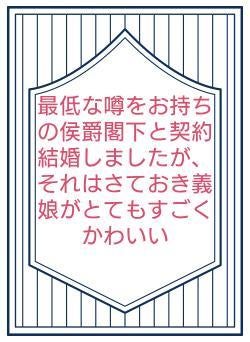§
アラン様が別邸に籠もられるとき、同伴することが日課になった。
アラン様お手製のソファーカバーがかかったソファーに腰掛ける。左右には大小いくつもの熊や兎のぬいぐるみ。皆可愛らしいレース編みの付け襟をつけている。ヘレンが淹れたお茶を飲みながら、滑らかに動き続ける手元を、流れてゆく糸をのんびりと眺める。
「——貴方も何かお作りになりますか?」
手元から顔を上げ、アラン様がふいに口を開く。彼からそっと目をそらし、私はあいまいな笑みを浮かべた。
「いえ、あまり得意ではないのです」
「ですが、手紙に添えてくださったハンカチの刺繍は見事でした」
「あれは手ほどきを受けて——」
つい誤魔化そうとして、思い直す。アラン様に秘密を打ち明けさせておきながら、自分は秘めておこうなど、公平ではない。私は観念して口を割った。
「見栄を張りました。あれはそこのヘレンが作ってくれたものに、目立たぬよう針をひと刺し」
私の告白に、アラン様が目を瞬いて楽しげに笑う。そしてヘレンに顔を向け、彼女に声をかけた。
「どうだ、君が座って刺繍をするかい?」
「いいえ旦那様、滅相もございません」
恐縮しきって肩を縮めるヘレンに「無理を言ったな」ともう一度笑い、アラン様は気にされる様子もなく手を動かし始めた。
ほっと息を吐く私の隣で、ヘレンもそっと息を吐く。……アラン様に誤解していたと直接告げることができず、つまりは謝罪することもできず、ヘレンは地に埋まりそうな気持ちを抱え、今までの分を取り戻さん勢いで『旦那様』と口に出している。私のことも『奥様』と。『責任は私にあるし、アラン様もきっとお許しくださる』と慰めているけれど、なかなかいたたまれなさを拭えない。
アラン様が別邸に籠もられるとき、同伴することが日課になった。
アラン様お手製のソファーカバーがかかったソファーに腰掛ける。左右には大小いくつもの熊や兎のぬいぐるみ。皆可愛らしいレース編みの付け襟をつけている。ヘレンが淹れたお茶を飲みながら、滑らかに動き続ける手元を、流れてゆく糸をのんびりと眺める。
「——貴方も何かお作りになりますか?」
手元から顔を上げ、アラン様がふいに口を開く。彼からそっと目をそらし、私はあいまいな笑みを浮かべた。
「いえ、あまり得意ではないのです」
「ですが、手紙に添えてくださったハンカチの刺繍は見事でした」
「あれは手ほどきを受けて——」
つい誤魔化そうとして、思い直す。アラン様に秘密を打ち明けさせておきながら、自分は秘めておこうなど、公平ではない。私は観念して口を割った。
「見栄を張りました。あれはそこのヘレンが作ってくれたものに、目立たぬよう針をひと刺し」
私の告白に、アラン様が目を瞬いて楽しげに笑う。そしてヘレンに顔を向け、彼女に声をかけた。
「どうだ、君が座って刺繍をするかい?」
「いいえ旦那様、滅相もございません」
恐縮しきって肩を縮めるヘレンに「無理を言ったな」ともう一度笑い、アラン様は気にされる様子もなく手を動かし始めた。
ほっと息を吐く私の隣で、ヘレンもそっと息を吐く。……アラン様に誤解していたと直接告げることができず、つまりは謝罪することもできず、ヘレンは地に埋まりそうな気持ちを抱え、今までの分を取り戻さん勢いで『旦那様』と口に出している。私のことも『奥様』と。『責任は私にあるし、アラン様もきっとお許しくださる』と慰めているけれど、なかなかいたたまれなさを拭えない。