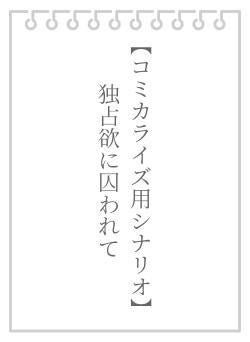男の人の目を見ると、心臓が痛む。
痛いと言ってしまうと大袈裟に聞こえるかもしれない。
けれど私の中では、ほんの小さな刺激でもすぐに火がつくように、胸の奥がひりつく。
呼吸の仕方を、一瞬だけ忘れる。
声が出るまでに、ほんの少し間が空く。
その“ほんの少し”が、いつも私を黙らせる。
二十六歳になっても、私はまだそれを“慣れ”に変えられない。
朝のオフィスは、音の層でできている。
キーボードの乾いたリズム、コピー機の低い唸り、誰かが椅子を引く音、カップが机に置かれる軽い衝撃。
人の気配の温度が、部屋の中に溶けていく。
その中に混ざる男の人の声だけが、私の背中をわずかに硬くする。
私は企画部の次長という肩書きを持っている。
入社して四年でこの役職に就いたことを、周囲は「出世が異常」と笑った。
後輩はまっすぐな目で「すごい」と言った。
私はそのどれにも、笑顔で応える。
“すごい人の顔”を作るのは得意だ。
得意になったのは、いろんなものを失ってからだ。
だから、仕事をしている間だけは、私は平気な人でいられる。
そう思い込むための手順を、私は自分の中にいくつも作った。
スケジュールを細かく組むこと。
会話の距離を決めておくこと。
笑うタイミングを予習しておくこと。
そして“必要以上に見ない”こと。
私の平気は、自然なものじゃない。
でも自然じゃないことを悟られるのは、もっと嫌だった。
「相根さん、来週の資料、最終版できました」
後輩の古賀くんがプリントを抱えてやってくる。
私は顔を上げる前に、視線の角度だけで彼の位置を測った。
安全圏。
彼の声は穏やかで、距離もちゃんとしてくれる。私は彼に救われている。
「ありがとう。机に置いておいて」
「はい。あと、この表現、ちょっと分かりにくいかなって思って直しました。見てもらえます?」
古賀くんの指が紙の端を叩く。
私はそこをじっと見て頷いた。
「うん、いいね。読みやすくなってる」
「よかった」
彼はほっとした笑みを残して去っていく。
私はその背中に小さく息を吐いてから、資料を重ね直した。
——会社では“平気な人”でいなければならない。
次長として、判断できる人間でいなければならない。
部下の前で揺らいではいけない。
上の人間に“見抜かれるような隙”を作ってはいけない。
それを守るためなら、自分の心の癖だって、折りたたんでしまえると思っていた。
午前中の会議を二本こなし、企画書のラフを二つ直し、部のメンバーの相談に応え、昼休みが終わるころ、私はようやくコーヒーのカップを手に取った。
今日の午後は社長との打ち合わせが入っている。
企画部が進めている新規プロジェクトの方向性確認。
社長がわざわざ時間を作って口を出してくる案件は、会社としても重要度が高いということだ。
かつて私は、社長から直接のフィードバックをもらえることに少し誇らしさを感じていた。
今は、違う。
予定が入った瞬間から、体の深いところが固くなる。
——社長。
同じ会社の人間なのに、東雲颯の前では、私はいつも心の奥の温度が奪われる。
東雲颯。二十八歳。
若くして社長になった、うちの会社の“顔”。
業界でも有名なやり手で、仕事の嗅覚が鋭く、言葉も鋭い。
愛想がない。
不機嫌なのか平常なのか、顔だけじゃ判別できない。
しかもタメ口で、口が悪い。
それを「合理的」「気取らない」で済ませていいのかどうか、私にはよく分からない。
ただ、彼の眼差しはあまりに冷たくて、むき出しの刃みたいに見える。
社員の評判は二つに割れる。
「怖い」
「でも、仕事ができる」
そしてみんな最後に付け足す。
「顔が、良すぎる」
……どれにも、私は頷けてしまう側だった。
会議室へ向かう廊下を歩きながら、私は手のひらを開いたり閉じたりした。
汗は、ほんの少し。
それでも指先が冷たいのが分かる。
会議室の扉の前に立ち、資料の表紙をもう一度確認する。
万が一、数字を読み間違えたら。
万が一、彼に詰められて声が揺れたら。
万が一、あの低い声がすぐ傍から落ちてきたら。
——私は次長だ。
次長は、逃げない。
自分に言い聞かせて、ノックした。
「失礼します」
「入れ」
短い声。
低く、乾いていて、余計な温度がない。
会議室に入ると、東雲社長はすでに席に着いていた。
黒いスーツの襟元は完璧に整っていて、それだけで“手抜きのない人間”だと分かる。
机の上に開かれた資料の端が、ぴたりと整列しているのが目に入った。
几帳面というより、隙がない。
私は社長と目を合わせないまま席に着き、資料の角を揃えた。
「で?」
社長が顎だけで私の資料を指す。
視線はまだ紙の上。
まっすぐにこちらを見ないところが、逆に圧になる。
「説明、始めます」
私は声を出す前に呼吸を整えた。
男の人の前で声が揺れるのは、いちばん嫌だった。
私は1ページ目から説明を始めた。
狙い、ターゲット、競合、収益見込み、ロードマップ。
喋っている最中、私はずっと資料の文字を追っていた。
よくない癖だと分かっている。
でも私は目を上げられない。
視線がぶつかった瞬間に胸の奥が縮むことを、私は知っている。
社長は一度も頷かない。
資料をめくる音だけが、私の言葉の隙間に入る。
「——以上です。現時点ではこの方向で進める案を考えています」
私は最後のページを閉じ、結論を告げた。
沈黙が落ちる。
社長は紙から目を離さず言った。
「弱い」
心臓が跳ねる。
その一言だけで、胸の奥をきゅっと掴まれたみたいに呼吸が浅くなる。
「どこが、でしょうか」
なるべく淡々と返したつもりだった。
声の高さが上がらないように、言葉の端をきっちり締める。
「全部」
迷いのない、雑な切り方。
でも社長は悪意のない顔で続けた。
「数字の根拠が足りねぇし、競合との差も甘い。“やりたい感”だけで走ってない? この企画」
タメ口。しかも刺さる言い方。
口が悪いのに、言ってることは正しい。
喉がきゅっと狭まるのを、私は奥歯で堪えた。
「……根拠の追加は次回までに補強できます」
「補強? 違うだろ」
社長がようやく顔を上げた。
私は反射的に視線を落とす。
それでも、鋭い目だけがこっちに向いたことは分かった。
「作り直せって言ってんの。
補強じゃ足りない。骨組みからズレてる」
私は胸の奥で、自分のプライドが小さく鳴るのを聞いた。
悔しい。
でも、それを顔に出したら負けだと思った。
「……わかりました」
資料の端を無意識に強く掴んでいた指に気づき、そっと力を抜く。
社長はそこで止めない。
「相根、お前さ」
呼び捨て。
がつんとくるのに、それが彼の普通なのが分かっているから、余計に反応できない。
「いい企画出すのは分かる。でも、俺に刺さらないもんは通らない。分かる?」
私は即答した。
「はい」
声が小さくならないように、短く、はっきり。
——怖い。
でもここで折れたら、次長じゃなくなる。
社長は私の返事に興味がないみたいに視線を資料に戻した。
そしてすぐ次のナイフを置く。
「あと、ここ。顧客の解像度、浅い。“こういう人が喜ぶはず”って願望入ってるだろ」
「……顧客インタビューの数が足りない、ということですか」
「数の問題じゃない。聞き方が甘いんだよ。“欲しい答え”探して質問してる」
胸の奥がひやっとする。
図星に近かったからだ。
私は言い返す言葉の代わりに、メモを取った。
ペン先が紙に触れる音が小さく響く。
「……改善します」
「“改善します”じゃなくて、やり直せ。俺、来週また見るから」
「承知しました」
社長は、ふうと小さく息を吐いた。
ため息とも、興味のなさとも取れる音。
「別に怒ってねぇよ。怒ってたらもう終わってる」
私は少しだけ目を瞬いた。
その言葉があまりに淡々としていて、逆に本音に聞こえたから。
社長は机に指を軽く置いて言う。
「“今のまま進めたら失敗する”って見えたから止めただけ。お前、止められた方がいいタイプだろ」
タメ口のくせに、妙に核心を突く。
私は返事を探しあぐねて、「……はい」とだけ答えた。
社長は何か言い続けるでもなく、ふと視線を落として書類を閉じた。
「で、スケジュールどうする?」
話題が変わる。
切り替えが早い。
私はその速度に置いていかれないよう、急いで頭を整えた。
「来週の月曜までに再構成し、火曜に中間レビューをいただければ、その後、開発側に展開できます」
「火曜ね。時間は?」
「午前十時からでお願いできますでしょうか」
「俺の予定、確認して」
ぶっきらぼうに言うけれど、それは“仕事としての会話”の範囲で、余計な棘はない。
私はタブレットで社長の予定を確認し、淡々と答えた。
「午前十時、空いています」
「じゃ、それで」
一言で決まる。
しばらく沈黙。
社長は腕を組み、何か考えている顔をしている。
私はその間、呼吸を整えていた。こういう沈黙の時間が、私には一番きつい。
何を言われるか分からない恐怖が、じわじわ染みてくる。
だけど社長は、私のほうを真正面から見ようとせず、横に視線を流したまま言った。
「相根、お前、最近疲れてる?」
いきなりすぎて、私は返答に詰まった。
「……いえ」
「嘘くさいな」
たったそれだけ。
社長の声は相変わらず冷たい。
でも、そこに怒りも嘲りもない“ただの観察”があった。
私は視線を落としたまま答える。
「……忙しいだけです」
「そ」
それで終わり。
掘り下げない。
慰めない。
拒否もしない。
それが、なぜか少しだけ楽だった。
社長は椅子の背にもたれて言う。
「企画、期待してるからな」
言い方は雑でぶっきらぼう。
まるで“ついで”みたいに軽い。
でも、その言葉のあとに、胸の奥がごく小さくふわっとした。
期待してる、の意味が、私にはまだ分からなかったけれど。
打ち合わせはそれで終わりだった。
社長は立ち上がる気配もなく、視線を資料に落としたまま言う。
「以上。出ていいよ」
「……失礼します」
私は資料を抱えて立ち上がった。
扉へ向かう。
このまま呼吸を整えて、仕事の私に戻らなければいけない。
扉に手をかけた瞬間、背中に声が落ちる。
「相根」
私は反射的に足を止めた。
「次、同じ進行でいい。お前がやれ」
決定事項を告げるだけの声。
優しくも温かくもない。
ただの事実として、短く置かれる。
私は頷いた。
「承知しました」
社長は「うん」すら言わない。
でも、その無関心みたいな終わり方が、私には不思議と刺さらなかった。
私は会議室を出て、廊下の角まで歩いたところで、ようやく息を吐いた。
肩の力が抜ける。
手のひらが、さっきより震えていない。
——冷たい人だ。
本当に、冷たい。
口も悪いし、言葉も刺さる。
それなのに、“次も君がやれ”という決定は、私の中でなぜか“拒絶”じゃなく“何か別の音”として残っている。
あの人は、私の企画にダメを出した。
容赦のない言い方で切った。
でも、切り終わったあと、私を放り投げなかった。
次、同じ進行で。
お前がやれ。
その言葉を思い出すたび、胸の奥で何かが微かに揺れる。
怖さだけの色じゃない。
悔しさとも違う。
名前のないその揺れが、私の中でほんの少しだけ、ぬくもりの形をしていた。
それに気づくのが、少しだけ怖かった。
私はもう一度、深く息を吸って、フロアへ戻った。
仕事は続く。
次の会議も、次の資料も、次のレビューも。
来週、また社長に見せる企画を作り直さなければならない。
冷たい声。
口の悪い言葉。
鋭い目。
——それでも。
私は来週の予定を思い浮かべた瞬間、体のどこかが“拒むより先に、確かめたい”と思っているのを感じた。
その感情に、まだ名前はつけられない。
でも、私はその名前のない感情を、今は少しだけ、手放したくなかった。
痛いと言ってしまうと大袈裟に聞こえるかもしれない。
けれど私の中では、ほんの小さな刺激でもすぐに火がつくように、胸の奥がひりつく。
呼吸の仕方を、一瞬だけ忘れる。
声が出るまでに、ほんの少し間が空く。
その“ほんの少し”が、いつも私を黙らせる。
二十六歳になっても、私はまだそれを“慣れ”に変えられない。
朝のオフィスは、音の層でできている。
キーボードの乾いたリズム、コピー機の低い唸り、誰かが椅子を引く音、カップが机に置かれる軽い衝撃。
人の気配の温度が、部屋の中に溶けていく。
その中に混ざる男の人の声だけが、私の背中をわずかに硬くする。
私は企画部の次長という肩書きを持っている。
入社して四年でこの役職に就いたことを、周囲は「出世が異常」と笑った。
後輩はまっすぐな目で「すごい」と言った。
私はそのどれにも、笑顔で応える。
“すごい人の顔”を作るのは得意だ。
得意になったのは、いろんなものを失ってからだ。
だから、仕事をしている間だけは、私は平気な人でいられる。
そう思い込むための手順を、私は自分の中にいくつも作った。
スケジュールを細かく組むこと。
会話の距離を決めておくこと。
笑うタイミングを予習しておくこと。
そして“必要以上に見ない”こと。
私の平気は、自然なものじゃない。
でも自然じゃないことを悟られるのは、もっと嫌だった。
「相根さん、来週の資料、最終版できました」
後輩の古賀くんがプリントを抱えてやってくる。
私は顔を上げる前に、視線の角度だけで彼の位置を測った。
安全圏。
彼の声は穏やかで、距離もちゃんとしてくれる。私は彼に救われている。
「ありがとう。机に置いておいて」
「はい。あと、この表現、ちょっと分かりにくいかなって思って直しました。見てもらえます?」
古賀くんの指が紙の端を叩く。
私はそこをじっと見て頷いた。
「うん、いいね。読みやすくなってる」
「よかった」
彼はほっとした笑みを残して去っていく。
私はその背中に小さく息を吐いてから、資料を重ね直した。
——会社では“平気な人”でいなければならない。
次長として、判断できる人間でいなければならない。
部下の前で揺らいではいけない。
上の人間に“見抜かれるような隙”を作ってはいけない。
それを守るためなら、自分の心の癖だって、折りたたんでしまえると思っていた。
午前中の会議を二本こなし、企画書のラフを二つ直し、部のメンバーの相談に応え、昼休みが終わるころ、私はようやくコーヒーのカップを手に取った。
今日の午後は社長との打ち合わせが入っている。
企画部が進めている新規プロジェクトの方向性確認。
社長がわざわざ時間を作って口を出してくる案件は、会社としても重要度が高いということだ。
かつて私は、社長から直接のフィードバックをもらえることに少し誇らしさを感じていた。
今は、違う。
予定が入った瞬間から、体の深いところが固くなる。
——社長。
同じ会社の人間なのに、東雲颯の前では、私はいつも心の奥の温度が奪われる。
東雲颯。二十八歳。
若くして社長になった、うちの会社の“顔”。
業界でも有名なやり手で、仕事の嗅覚が鋭く、言葉も鋭い。
愛想がない。
不機嫌なのか平常なのか、顔だけじゃ判別できない。
しかもタメ口で、口が悪い。
それを「合理的」「気取らない」で済ませていいのかどうか、私にはよく分からない。
ただ、彼の眼差しはあまりに冷たくて、むき出しの刃みたいに見える。
社員の評判は二つに割れる。
「怖い」
「でも、仕事ができる」
そしてみんな最後に付け足す。
「顔が、良すぎる」
……どれにも、私は頷けてしまう側だった。
会議室へ向かう廊下を歩きながら、私は手のひらを開いたり閉じたりした。
汗は、ほんの少し。
それでも指先が冷たいのが分かる。
会議室の扉の前に立ち、資料の表紙をもう一度確認する。
万が一、数字を読み間違えたら。
万が一、彼に詰められて声が揺れたら。
万が一、あの低い声がすぐ傍から落ちてきたら。
——私は次長だ。
次長は、逃げない。
自分に言い聞かせて、ノックした。
「失礼します」
「入れ」
短い声。
低く、乾いていて、余計な温度がない。
会議室に入ると、東雲社長はすでに席に着いていた。
黒いスーツの襟元は完璧に整っていて、それだけで“手抜きのない人間”だと分かる。
机の上に開かれた資料の端が、ぴたりと整列しているのが目に入った。
几帳面というより、隙がない。
私は社長と目を合わせないまま席に着き、資料の角を揃えた。
「で?」
社長が顎だけで私の資料を指す。
視線はまだ紙の上。
まっすぐにこちらを見ないところが、逆に圧になる。
「説明、始めます」
私は声を出す前に呼吸を整えた。
男の人の前で声が揺れるのは、いちばん嫌だった。
私は1ページ目から説明を始めた。
狙い、ターゲット、競合、収益見込み、ロードマップ。
喋っている最中、私はずっと資料の文字を追っていた。
よくない癖だと分かっている。
でも私は目を上げられない。
視線がぶつかった瞬間に胸の奥が縮むことを、私は知っている。
社長は一度も頷かない。
資料をめくる音だけが、私の言葉の隙間に入る。
「——以上です。現時点ではこの方向で進める案を考えています」
私は最後のページを閉じ、結論を告げた。
沈黙が落ちる。
社長は紙から目を離さず言った。
「弱い」
心臓が跳ねる。
その一言だけで、胸の奥をきゅっと掴まれたみたいに呼吸が浅くなる。
「どこが、でしょうか」
なるべく淡々と返したつもりだった。
声の高さが上がらないように、言葉の端をきっちり締める。
「全部」
迷いのない、雑な切り方。
でも社長は悪意のない顔で続けた。
「数字の根拠が足りねぇし、競合との差も甘い。“やりたい感”だけで走ってない? この企画」
タメ口。しかも刺さる言い方。
口が悪いのに、言ってることは正しい。
喉がきゅっと狭まるのを、私は奥歯で堪えた。
「……根拠の追加は次回までに補強できます」
「補強? 違うだろ」
社長がようやく顔を上げた。
私は反射的に視線を落とす。
それでも、鋭い目だけがこっちに向いたことは分かった。
「作り直せって言ってんの。
補強じゃ足りない。骨組みからズレてる」
私は胸の奥で、自分のプライドが小さく鳴るのを聞いた。
悔しい。
でも、それを顔に出したら負けだと思った。
「……わかりました」
資料の端を無意識に強く掴んでいた指に気づき、そっと力を抜く。
社長はそこで止めない。
「相根、お前さ」
呼び捨て。
がつんとくるのに、それが彼の普通なのが分かっているから、余計に反応できない。
「いい企画出すのは分かる。でも、俺に刺さらないもんは通らない。分かる?」
私は即答した。
「はい」
声が小さくならないように、短く、はっきり。
——怖い。
でもここで折れたら、次長じゃなくなる。
社長は私の返事に興味がないみたいに視線を資料に戻した。
そしてすぐ次のナイフを置く。
「あと、ここ。顧客の解像度、浅い。“こういう人が喜ぶはず”って願望入ってるだろ」
「……顧客インタビューの数が足りない、ということですか」
「数の問題じゃない。聞き方が甘いんだよ。“欲しい答え”探して質問してる」
胸の奥がひやっとする。
図星に近かったからだ。
私は言い返す言葉の代わりに、メモを取った。
ペン先が紙に触れる音が小さく響く。
「……改善します」
「“改善します”じゃなくて、やり直せ。俺、来週また見るから」
「承知しました」
社長は、ふうと小さく息を吐いた。
ため息とも、興味のなさとも取れる音。
「別に怒ってねぇよ。怒ってたらもう終わってる」
私は少しだけ目を瞬いた。
その言葉があまりに淡々としていて、逆に本音に聞こえたから。
社長は机に指を軽く置いて言う。
「“今のまま進めたら失敗する”って見えたから止めただけ。お前、止められた方がいいタイプだろ」
タメ口のくせに、妙に核心を突く。
私は返事を探しあぐねて、「……はい」とだけ答えた。
社長は何か言い続けるでもなく、ふと視線を落として書類を閉じた。
「で、スケジュールどうする?」
話題が変わる。
切り替えが早い。
私はその速度に置いていかれないよう、急いで頭を整えた。
「来週の月曜までに再構成し、火曜に中間レビューをいただければ、その後、開発側に展開できます」
「火曜ね。時間は?」
「午前十時からでお願いできますでしょうか」
「俺の予定、確認して」
ぶっきらぼうに言うけれど、それは“仕事としての会話”の範囲で、余計な棘はない。
私はタブレットで社長の予定を確認し、淡々と答えた。
「午前十時、空いています」
「じゃ、それで」
一言で決まる。
しばらく沈黙。
社長は腕を組み、何か考えている顔をしている。
私はその間、呼吸を整えていた。こういう沈黙の時間が、私には一番きつい。
何を言われるか分からない恐怖が、じわじわ染みてくる。
だけど社長は、私のほうを真正面から見ようとせず、横に視線を流したまま言った。
「相根、お前、最近疲れてる?」
いきなりすぎて、私は返答に詰まった。
「……いえ」
「嘘くさいな」
たったそれだけ。
社長の声は相変わらず冷たい。
でも、そこに怒りも嘲りもない“ただの観察”があった。
私は視線を落としたまま答える。
「……忙しいだけです」
「そ」
それで終わり。
掘り下げない。
慰めない。
拒否もしない。
それが、なぜか少しだけ楽だった。
社長は椅子の背にもたれて言う。
「企画、期待してるからな」
言い方は雑でぶっきらぼう。
まるで“ついで”みたいに軽い。
でも、その言葉のあとに、胸の奥がごく小さくふわっとした。
期待してる、の意味が、私にはまだ分からなかったけれど。
打ち合わせはそれで終わりだった。
社長は立ち上がる気配もなく、視線を資料に落としたまま言う。
「以上。出ていいよ」
「……失礼します」
私は資料を抱えて立ち上がった。
扉へ向かう。
このまま呼吸を整えて、仕事の私に戻らなければいけない。
扉に手をかけた瞬間、背中に声が落ちる。
「相根」
私は反射的に足を止めた。
「次、同じ進行でいい。お前がやれ」
決定事項を告げるだけの声。
優しくも温かくもない。
ただの事実として、短く置かれる。
私は頷いた。
「承知しました」
社長は「うん」すら言わない。
でも、その無関心みたいな終わり方が、私には不思議と刺さらなかった。
私は会議室を出て、廊下の角まで歩いたところで、ようやく息を吐いた。
肩の力が抜ける。
手のひらが、さっきより震えていない。
——冷たい人だ。
本当に、冷たい。
口も悪いし、言葉も刺さる。
それなのに、“次も君がやれ”という決定は、私の中でなぜか“拒絶”じゃなく“何か別の音”として残っている。
あの人は、私の企画にダメを出した。
容赦のない言い方で切った。
でも、切り終わったあと、私を放り投げなかった。
次、同じ進行で。
お前がやれ。
その言葉を思い出すたび、胸の奥で何かが微かに揺れる。
怖さだけの色じゃない。
悔しさとも違う。
名前のないその揺れが、私の中でほんの少しだけ、ぬくもりの形をしていた。
それに気づくのが、少しだけ怖かった。
私はもう一度、深く息を吸って、フロアへ戻った。
仕事は続く。
次の会議も、次の資料も、次のレビューも。
来週、また社長に見せる企画を作り直さなければならない。
冷たい声。
口の悪い言葉。
鋭い目。
——それでも。
私は来週の予定を思い浮かべた瞬間、体のどこかが“拒むより先に、確かめたい”と思っているのを感じた。
その感情に、まだ名前はつけられない。
でも、私はその名前のない感情を、今は少しだけ、手放したくなかった。