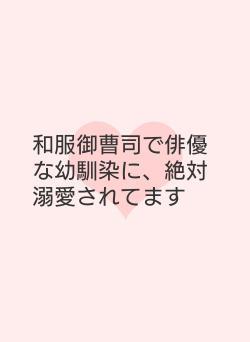4回裏 sideヴァレンス
ヴァレンスが白猫ユリアを自室に連れてきて数日が経った。
王妃ユリアの失踪は表立っては隠されていて、諜報部の人間たちで捜索活動がおこなわれている状態――ということになっている。
(あの白猫はユリアだと思っていたが……)
問題が起きた。
そう――。
――人間ユリアの身体が見つかったのだ。
失踪したと思われた翌朝、唐突にベッドの上に現れたのだった。
現れたという表現はおかしいのかもしれない。
彼女の身体は、ずっと同じ場所にあったようなのだ。
おそらく何らかの幻術の類で隠れていたという表現の方が近いようだ。
彼女は全く目覚めることはなく、懇々と眠りに就いた状態である。
だが――それが見えているのはヴァレンスだけだったのだ。
(まぎれもなく、あの白猫はユリア本人だろう……ささいな仕草やこちらへの気配りのようなものが、あまりにもユリアそのものだ……)
そう考えると、白猫にユリアの魂が宿ったような状態なのだろうか――?
(魔力のない俺には判断がつかない……遠方にいる魔術師の師を呼んでいるが、まだまだこちらに来るのに時間が掛かるようだ)
今のところ、人間のユリアはちゃんと生きている状態だが、それがいつまで大丈夫なのかは未知の領域だ。
だからこそ、ヴァレンスの気持ちは落ち着かない。
とはいえ――。
(最初は少しだけ警戒していたユリアが、俺にものすごく懐いて……すり寄ってくるのが堪らなく愛おしい…………!)
しかも、今まで一緒に過ごしたことがなかったのに、毎晩同じベッドの上で眠っている……!
(こんなに幸せだとは思っていなかった……!)
どんな姿をしていたとしても妻は妻だ。
あれだけ近づくことが出来なかった距離が一気に近づいたような気がして嬉しくてしょうがない。
(ネコと言えば、目を合わせてくれないのが定番だが……俺に対してものすごく熱い眼差しを向けてくる……!)
黄金の瞳でじっと見つめられるとドギマギしてしょうがない。
撫でたりブラッシングをしてやると、少しだけざらついた舌でぺろぺろと自分を舐めてくるところだったり、ピンクの肉球でふみふみしてきたり、ゴロゴロと喉を鳴らしてくる姿も愛おしくてたまらない。
時には、木登りをして執務室にいる自分の姿を眺めに来ていることもあって、ここに至福極まれりである。
あまりに感極まって――ヴァレンスは毎日眠る前に詩を十編ほど紡いでしまう始末だ。
(匿名でセルツェ王家の詩集第四巻に寄稿しようと思う……)
そう、そして、ヴァレンスの気分が一番高揚するのが――。
白猫ユリアがツンと素っ気ない態度をとったかと思いきや、尻尾をピンと立てながら、こちらをじっと見つめてくるのだ。
(ネコの愛情表現……! ネコのユリアは間違いなく俺に懐いている……!)
人間同士では失敗したが、人間とネコの姿になって、初めて白猫ユリアの信頼を勝ち取ることができたのだ。
「昔……白猫を飼っていたんだったな……」
だからこそ、ヴァレンスはネコの飼育について詳しかった。
けれども、彼がまだ子ども時代のある日、忽然と姿を消したのだ。
死を悟ったネコは飼い主の前から姿を消すというから――おそらくは亡くなってしまったのだろう。
(……雪の深い夜、真っ白な山の中へと続く足跡が残っていたな……)
今までの過去を振り返る。
(国王の甥という立場で、王位継承位もそんなに高いものではなかったが……陰湿な叔父王のおかげ、王族としての良い待遇は受けてこなかった……)
とはいえ、それなりに武術や魔術の教育は受けさせてもらえていたのだから、圧政を強いられていた民たちよりもマシな立場だったはずだ。
(ユリアはとても奥深くて聡い人間だ。しっかりと学べば周囲からも文句なしの最高の王妃になることができるだろう)
不幸な生い立ちだった彼女にあまり無理はさせたくなくて、この二年間、王妃教育を無理やり推し進めるようなことはしなかった。
けれども、見てはいけないと思いつつも、たどたどしい字で一生懸命書いてるのを見てしまった。
『ちゃんと、おうひ、しごと、みんなの、やくに、たちたい』
ネコから人間の姿に戻ることが出来るのか、現時点では分からないが……。
(しっかりとユリアと向き合って……彼女の意思を確認して)
そうして――。
――ちゃんと対等な立ち位置で、自分の治世を支えていってほしい。
城の中でただ守られているだけの年若い少女ではなく、しっかりした意思を持つ強い女性なのだと改めてヴァレンスの心は惹かれていた。
そんなことを思いながら、ヴァレンスは自室へと戻る。
夜の部屋、白猫がにゃあんと嬉しそうにこちらに駆け寄ってきた。
「ユリア、どうだ、不都合はないか?」
「にゃあん(大丈夫です)」
「そうか、それなら良かった」
ふっとヴァレンスがこちらを見て微笑んできた。
数日過ごしてきて、不思議なことがある。
このネコがユリアだと確信している理由でもある。
実は――。
(ユリアの声が重なって聴こえてきている……気がする)
もしかしたら思い込みかもしれないが……白猫が鳴くたびに、愛らしいユリアの声が聞こえるのだ。
(俺の願望かもしれないが……)
ヴァレンスは寝間着に着替えると、少し歩いた先にあるベッドの上に腰かけた。
白猫がてててと近づいてきたかと思うと、すりすりとピンクの鼻先で少しだけざらついた頬に触れてくる。
それだけでも心臓が爆発しそうだったのだが――。
それだけでは済まなかった。
なんと――。
「にゃにゃにゃ、なあん(ヴァレンス様……好き)」
あげく――白猫ユリアがヴァレンスの唇の端をぺろりと舐めてきたのだった。
状況についていけず、ヴァレンスは石のように固まってしまう。
「にゃ……?」
不思議そうにユリアが首をかしげている。
(今のは聞き間違いか……!? まったく事態が急すぎて、理解が追い付かない……!!)
――自分のことを好きだと言わなかっただろうか――?
(ユリアが俺のことを……好き……!? 飼い主としてということか?)
ヴァレンスは顔を真っ赤にして固まっていると、白猫はなぜか妙にわたわたしていた。
その時――。
「にゃ?」
一瞬、白猫ユリアの姿がぐらりと蜃気楼のように揺らめいた。
(気のせいか? ユリアに何か異変が起こっているのだろうか?)
ヴァレンスは目を真ん丸に見開いた。
だが、すぐに先ほどのユリアのセリフが頭に木霊しはじめる。
咳ばらいをしたかと思うと――。
「ユリア……俺も……その……」
――好きだ。
そう言おうかと思ったけれど……。
(ちゃんと想いを伝えるのは彼女が人間に戻ってからだ……それが武人としての礼儀というものだろう)
己を律した彼は、ごろんと横になった。
そうして――。
いつもは出来ない、ちょっとだけ大胆な行動にヴァレンスは出ることにする。
「ユリア……ほら、こちらにおいで」
彼が片腕を差し出して、白猫ユリアを手招く。
彼女が彼の筋肉質な腕の上に寝転ぶと、ジーンと感動で胸がいっぱいになっていく。
「ユリア、良い夢を……」
(ああ、なんて幸せなのだろうか……!)
ふと、白猫ユリアに腕を差し出しながら、ヴァレンスは部屋の奥にある開かずの間を見た。
――部屋の中に開かずの間があるのには理由があるが……
そんなことは意識の外に追いやって――ヴァレンスは幸福に包まれながら眠りに就くことができたのだった。
***
翌朝。
秋晴れの中、緑に覆われた白庭を歩いていると――。
――妙な気配を感じた。
「これは……」
そうして視線を移す。
バサバサと大鷲が飛んできたかと思うと――ヴァレンスの頭上を羽ばたく。
「――師匠……」
ヴァレンスがそう呟くと、鷲は急降下してくると同時に、ぐにゃりと変形する。
そうして――。
「久しいな、ヴァレンス坊や」
黒いローブに身を包んだ、黒髪長髪の妖艶な美形が現れたのだった。
瞳の色は紅く、人として異質だということを象徴しているかのようだ。
「今回も魔術師らしからぬ派手な登場ですね……」
ヴァレンスが嘆息しながら告げた。
「人を呼びつけておいて、なんだ、その言いぐさは……相変わらず、小生意気なガキだ」
「もう俺は三十近い、もう充分大人ですよ」
「オレから見れば、ひよひよのヒヨコでしかない」
「はあ、そうですか……」
目の前の人物は、ヴァレンスの魔術の師である。
昔から、年齢も性別も一貫しない。
やや堅苦しい話し方をするこの人から、幼い頃のヴァレンスは影響を受けた気がする。
「ヴァレンスよ、オレは、まだるっこしいのは好きではない。お前の妻の様子を見てきた。単刀直入に言おう」
そう言われ、ヴァレンスはごくりと息を呑んだ。
「ああ、その前に――」
師匠は話を転換した。
「お前たちはまだ夫婦の間柄ではないな?」
「は?」
「昨年会った時に、今年の抱負でしっかり夫婦の関係になると言っていなかったか?」
頭の回転が速すぎて、話が飛躍することがたまにある。
「キスはどうだ? まだ事を成していないのか? 早くしないと色々と時間がないぞ……お前がその調子では私も心配でしょうがない……」
――白猫ユリアと人間ユリアの関係について聞けるものだと思っていたのに――。
ヴァレンスは心の中でがっくりと肩を落とした。
ちょっとイラついた口調で返す。
「ああ、あなたが心配するようなことは何もない。安心してほしい。ちゃんとユリアの件に関してはカタをつけるつもりだ――だが、俺からユリアに口づけることはないだろう――なぜなら……」
やや虚勢を張りながら返したヴァレンスが苦悩に満ちた表情を浮かべた。
(――尊すぎて、髪に口づけるので精いっぱいだからな――!!)
――口づけられるんだったら、とっくの昔にやっている――!!
そんなことを思っていると――。
師匠がふっと怪しげな笑みを浮かべた。
「そうか……それは残念だ」
「何が残念なのだというのですか……」
ちょっと苛立ちながら返していると、今度は師匠が嘆息しながら返してくる。
「全く、人に教えを乞う態度ではないな。まあ、定番だろう? 王子の口移しで目覚める姫の話というやつは?」
「え――?」
「あの白猫はお前の伴侶で間違いない……まあ、半分魂が体から抜け出ているような状態だがな」
「半分?」
「そうだ――そうして――」
師匠の指先がこちらにゆっくりと向けられた。
「――お前もだよ、ヴァレンス・セルツェ」
「――え?」
そうして、師匠はふっと視線を茂みに移す。
「ああ、お前の半身がどうやら何か悪さをしそうだな」
「俺の半身? あなたは何を言って……?」
その時――。
「にゃあんっ……!」
白猫ユリアの声が聞こえた。
「にゃにゃにゃにゃん」
はっとしてヴァレンスは茂みへと踵を返す。
「――ユリア!?」
そうして――ヴァレンスは驚くべき光景を目にするのだった――。