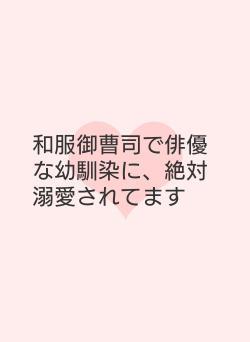3回裏 sideヴァレンス
白猫の黄金の瞳とばっちり目が合ったヴァレンスは戸惑いを隠せない。
机の上に置いてあったユリアの手記に一瞬目を落とした後、もう一度ネコに視線を戻す。
(今朝の夢で見たネコ……? まさか、ユリアが本当にネコになったというのか……?)
「冷血王」と呼ばれる彼は生粋の軍人だ。
――残念ながら魔力持ちではないからこそ、魔力持ちの聖女ユリアを娶ることになったのである。
数代前の国王の治世の頃には、王城の中を魔術師たちがたくさん闊歩していたと伝えられているが、近年では絶滅危惧種に近い。
魔術商法のような怪しい詐欺が横行したり、自称魔術師のような類はたくさん存在しており、魔術を架空の概念だとかインチキだと思っている国民たちもいるぐらいだ。
もちろん、神聖な力を信じて心酔しているものも存在している。
全く魔術の才能に恵まれなかったヴァレンスだが、一応王族のたしなみとして魔術や魔法の理論に関しては学んでいる。
現存する魔術師の一人である師匠だっているのだ。
(ユリアは類稀なる魔力の持ち主だ……だからこそ、魔力を行使して朝の空中散歩をしていたのだとしても、置手紙を残して忽然と姿を消したのだとしても……)
――ネコの姿になったのだとしても、それを全く否定することはできないのだ……。
「――ユリア……!?」
白猫がユリアだとは断定できない状態だったが――。
ヴァレンスの手元にある、彼女の残したと思われる置手紙(?)
そこに書かれていた内容に再度ヴァレンスは目を遣る。
真っ白な手紙には習いたての字が躍っている。
『りえん、ヴァレンス様、ネコ、なりたい』
貧しい修道女時代を過ごしたユリアにとって、紙とインクはとても貴重なものだった。
その中でも、奇妙な人間扱いをされてきた彼女に筆記具が与えられる機会は少なかったのだという。
(ここに書いてある通りのことをユリアが考えていたのだとして……彼女を追い詰めてしまった原因の一つが俺であることは間違いない……)
そうして――。
(もしかしたら、あのネコはユリアではないかもしれない……)
ヴァレンスは――一縷の望みをかけてユリアの元へと駆ける――。
(俺には魔力がないから判別は出来ない……)
白猫に近づいたヴァレンスがしゃがみ込む。
逸る気持ちを抑えきれないけれども、白猫の繊細な身体を傷つけまいと、武骨な大きな手をぬっと伸ばす。
(だけれど、この生まれてしばらく経ったぐらいの、まだ動きがたどたどしい子ネコが、部屋にいないユリアを探すための手がかりであることは間違いない)
彼の両手に触れられかけた白猫がぎゅっと目を瞑る。
(ああ、怯えているんだな……これ以上、怖がらせないようにしなければ……)
そうして――――。
――ふわり。
被毛に覆われたネコの身体に、少しだけゴツゴツした指先が柔らかく触れる。
足元が床から離れ、宙に浮いた感覚がある。
その時――まだ若いヴァレンスが怯えて震える少女と出会った時の記憶がふっと蘇ってきた。
『魔力持ちなんて珍しいな……』
魔術師である師も近くにいたから、魔力のないヴァレンスでも少女が魔力持ちだと気づいたのだ。
少女はぼろぼろの端切れのような衣服をまとっていて、服を着ているのか着ていないのかも定かではないような状態だった。
皆が貧困に喘いでいるせいで、子ども相手にも寛容になれなくなっていたのだろう。
ひどく雑な扱いを受けた魔力持ちの少女の姿を見て、青年になりたてのヴァレンスの胸が軋んだ。
(こんなか弱い少女が苦しむ世の中なのだな……)
本来セルツェ王国はヴァレンスの叔父が統治していた国だった。
けれども、暴虐の限りを尽くす叔父によって、国民たちは疲弊してしまっていた。
少女が苦しむような現状を憂いたヴァレンスが、軍を率いて反旗を翻して――王位簒奪が繰り広げられたという経緯がある。
そこで彼は現在に意識を戻した。
(今はそんなことを考えている場合じゃない)
そうして――そろうりそろりと瞼を持ち上げる子ネコをじっと見る。
「……ユリア……?」
月のような黄金の瞳がきょろりとヴァレンスのことを見つめてくる。
(くっ……ネコに見つめられただけなのに、心臓が早鐘のようで落ち着かない……やはり、このネコの正体はユリアで……)
それがなぜか――ある意味答えが出ている気もしなくもない……。
再びまた、ふわり――。
白猫姿の私を、ヴァレンスが抱きしめる。
「にゃあ……」
(ネコの姿だし断定はできない状態とは言え)妻を抱きしめるのは初めてなので、どんどん鼓動が高まっていく。
(石鹸の淡くて優しい香り……これは、ユリアの髪と同じ香り……)
――決して彼女が使った使用済みのシーツに顔を埋めていたとかそんなわけではないとは全く言い切れないが――毎晩髪に口づけていたので知っている。
白猫の頭を優しくなでなでしてみる。
何も言わずに、しばらく彼の腕の中で過ごす彼女は、とろんとした瞳で幸せそうにしていた。
ふと――白猫がとった動作を注視する。
(ああ、間違いない……これは……)
白猫の肉球同士がふにふにと重なり合う。
その仕草は――まさしく人間であるユリアの毎日の日課である祈りを捧げる時の癖、そのものだった。
(もう何百回と観察してきたから知っている……ユリアには祈りの際に眉を顰める癖がある。全く同じことを、このネコがしていた……やはり……間違いない)
――このネコの正体は――ユリアだ。
ネコの中、意識はそのままなのだろうか――?
それとも、ユリア本人は自分がネコになったとは気づいていないのだろうか――?
そこは心配でしょうがなかったが――。
――もしかしたら、神が夫婦のやり直しをする機会を与えてくれたのかもしれない。
(ネコ姿のユリアを抱きしめたことで気分が高揚しきっている)ヴァレンスの口の端がにやりと上がった。
「にゃ……?」
そこまで前向きに考えていたが、白猫の鳴き声でヴァレンスははっとなった。
(いいや、やっぱりユリアは俺を嫌って失踪していて……それを認めたくはないがために、おかしな妄想をしているのだろうか……?)
ヴァレンスは一気にしおれてしまう。
「……すまないな……白猫がユリアだなんて……そんなはず、あるわけないな……」
少しだけヴァレンスは冷静になる。
そもそもが自分と離縁したくて、ネコになりたいとユリアは願ったのかもしれないのだ……。
ふと――ヴァレンスの表情が一瞬青ざめたものの、瞬時にキリリとしたものに変わる。
そうして――もう一度ネコに目をやる。
手を重ね合わせたうえに首をかしげているではないか。
(いや、間違いない……やはりユリアだ……)
(……ひとまず、白猫の様子をつぶさに観察してみよう……絶対に真実が明らかになるはずだ……それに…… 白猫の中にいるユリアの意識が連続しているんだとしたら、嫌いな俺に対して警戒しているかもしれない……)
とにかく慎重に――白猫ユリアを怯えさせないようにしないといけない。
「妻がいなくなってしまった……前々から俺に愛想をつかしているようでもあったから、こうなってしまったのは仕方ないだろうし……ひとまず捜索を願い出すとしよう……」
(あまり大事にしてはユリアも驚いてしまうかもしれないし……捜索は小規模でおこなわなければなるまいな……)
――ヴァレンスが優しい手つきで喉ぼとけに触れる――ゴロゴロと鳴き声が出てくるし――。
「にゃあん(気持ちが良い……)」
(――なぜかネコが気持ちいいと言った気がするが気のせいだろうか?)
魔力持ちじゃないけれども、ユリアの魔力が高すぎて干渉してきているパターンかもしれない。
とにかく、まずは出会ったばかりの白猫の体のユリアの信頼を勝ち取るのが先決だろう。
「お前が妻の捜索の手がかりになるかもしれない……。だから、俺についてきてはくれないか? 白猫のユリアよ」
わざとユリアと呼んだが、白猫は否定はしなかった。
あげく、ヴァレンスの腕にゆっくりとしなだれかかってくるではないか。
そんな動作をユリアにされたことなどなかったので――真っ赤になったヴァレンスは思わず明後日の方向を向いてしまった。
「…………よし――行こうか」
もし人間に戻れずに困っているのだとしたら、どうにかしないといけない。
けれども、ユリアが人間で過ごすのに嫌気がさしたのだとしたら……。
(どんな姿のユリアでも……俺は愛してみせる……)
妙な決意を胸にヴァレンスは白猫とともに王妃の部屋を立ち去った。
夫婦になって初めての至福の時を過ごす二人のことを、黒い何かが見ていることには気づかないまま――。