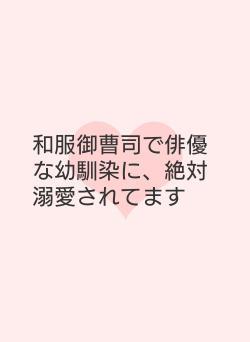3回表 sideユリア
夫ヴァレンスとばっちり目が合ってしまい、白猫姿になったユリアは動揺を隠せない。
(代々魔力持ちの王族……もし、ヴァレンス様が魔力持ちなのだとしたら、私が白猫になってしまったことに気づくはず……)
けれども――。
「冷血王」ヴァレンス様は生粋の軍人だ。
残念ながら、魔力持ちではないからこそ、魔力持ちの私を聖女扱いして娶ることになってしまったのだ。
以前は王城の中も魔術師たちがたくさん闊歩していたそうだが、残念ながら近年では絶滅危惧種に近い。
魔術商法のような怪しい詐欺が横行したり、自称魔術師のような輩はたくさん存在するが……。
(エセ魔術師に頼んだところで、人間がネコに変身なんてするはずがないでしょうし……)
だとしたら魔力を持たないヴァレンスが自分の存在に気づくはずはない。
――そのはずなのだけれど……。
「――ユリア……!?」
先ほどまで恐ろしい形相をしていたヴァレンスだったのに、こちらを見るとなんだか泣きそうな表情に見えた。
そうして――。
(え……嘘……嘘よ、そんな……)
なぜか私の存在に気づいた彼は――こちらに近づいてくるではないか――!!
(だって、ヴァレンス様には魔力はないはずで……)
近くに来たヴァレンスがしゃがみ込む。
相手の無骨で大きな手が、私の両脇にぬっと伸びてきた。
(ガシッと来る……!?)
乱暴に扱われるのかもしれないと思って、ぎゅっと目を瞑る。
けれども――。
――ふわり。
被毛に覆われた私の身体に、少しだけゴツゴツした指先が柔らかく触れてきた。
足元が床から離れ、宙に浮いた感覚がある。
その時、幼少期に高い高いをされた時の記憶がふっと蘇ってきた。
『魔力持ちなんて珍しいな……』
不思議な力を持って生まれたユリアは、出身の村では相当な奇人変人扱いを受けたり、嘘つき呼ばわりされたり、魔物の生まれ変わりだと嫌がらせにあったりしてきた。
だけれど、唯一ユリアのことを高い高いしてくれたのは、父でも母でもなく――。
そこで記憶はふっと途絶えた。
(なんだろう、今のは……?)
そうして――そろうりそろりと瞼を持ち上げる。
「……ユリア……?」
ヴァレンス様の不思議そうな紫水晶の瞳と出会った。
なんだかやけに熱っぽく感じて、心臓がドキドキと落ち着かない。
(ヴァレンス様、まさか本当に私の正体に気づいてくださっているの?)
再びまた、ふわり――。
白猫姿の私を、逞しい腕で抱きしめてくれたのだった。
「にゃあ……」
(ネコの姿とは言え)夫から抱きしめられるのは初めてなので、心臓がドキドキと高鳴っていく。
(細身な見た目にそぐわず、騎士服の中の腕はがっちりしてる……柑橘系と森林の良い香り……)
抱きしめられただけでも感激なのに、頭を優しくなでなでされて、きゅうっと胸が疼く。
何も言わずに、しばらく彼の腕の中で過ごすのは、とても夢見心地で――まるで揺りかごの中にいるかのように幸せだった。
(ネコの姿とはいえ、こんな日が来るなんて……)
――神様に感謝したい。
そう思って、人間時代の癖でお祈りをしようと両手を合わせる。
だけれど、組むことはできずに、肉球同士がふにふにと重なり合っただけだった。
ちょうど、その時――。
ヴァレンスの口の端がにやりと上がった気がした。
「にゃ……?」
何かの気のせいだろうか――?
ごしごしと目を擦る動作をして、もう一度相手を見る。
そこには、冷血王はどこへやら、とても柔和な笑みを浮かべるヴァレンスの端麗な顔立ちがあったのだ。
(ドキドキが落ち着かない……)
そうして――。
「……すまないな……白猫がユリアだなんて……そんなはず、あるわけないな……」
(あ……)
彼の言葉に――今度はちくりと胸が痛んだ。
膨れ上がっていた期待が、まるでシャボン玉のようにパチンと消えてしまったような気持ちがする。
(そうよね、人間がネコになるなんて、そんなおかしな話、生真面目なヴァレンス様が信じるはずはないわ……)
生粋の人間であるヴァレンスが、魔力持ちで気味が悪い自分のことを受け入れてくれるはずなんてないのだ。
(だからこそ、二年間も私に触れようとなさらなかったのでしょうし……)
ネコになったことのある人間だと知られれば、いよいよヴァレンスから嫌われて――離縁を言い渡されて、王城から追放されてしまうかもしれないのだ。
(それぐらいなら、ずっとネコの姿のまま、こうやって優しくされたりするのも悪くないかもしれない……)
ふと――ヴァレンスの表情が一瞬青ざめて見えたものの、瞬時にキリリとしたものに変わる。
そうして――。
「妻がいなくなってしまった……前々から俺に愛想をつかしているようでもあったから、こうなってしまったのは仕方ないだろうし……ひとまず捜索を願い出すとしよう……」
(ひとまず……ヴァレンス様はあまり私のことを心配してはくれていないのね……)
ずきずきと胸が痛む。
だけれど――彼があんまりにも優しい手つきで喉ぼとけに触れてくるものだから――ゴロゴロと鳴き声が出てくるし――。
「にゃあん(気持ちが良い……)」
――身も心も猫になりかけているのか至極幸福でしょうがない。
「お前が妻の捜索の手がかりになるかもしれない……。だから、俺についてきてはくれないか? 白猫のユリアよ」
今までに見たことのない慈愛の笑みを浮かべるヴァレンスの腕に、ゆっくりとしなだれかかる。
すると、ヴァレンスがそっぽを向いた。
「…………よし――行こうか」
公爵令嬢と結婚したい彼の罠かもしれないとかそんな気持ちはどこかに吹き飛んでしまっていた。
神様、もう少しだけで良いから――。
(ネコのままでいさせてください……)
――そんなことを思いながら彼の腕の中に身を委ねたのだった。