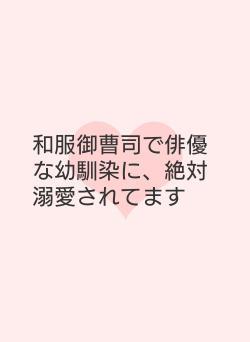1回裏 sideヴァレンス
夜、王城の離れにて。
王妃の部屋の窓辺に一人の愛らしい女性――部屋の主であるユリアが天にいる最高神へと向かって祈りを捧げていた。
そんな彼女の後方、少しだけ開いた扉の向こうには……
世間では冷血王と呼ばれるヴァレンス・セルツェの姿があった。
軍人達の中でも目立つ高身長の彼だが、隠密行動を得意としていることもあり、彼是小一時間ほどこんな調子で扉の前に佇んでいる。
ユリアが祈りを捧げることを毎日の日課とするならば、ヴァレンスにとっての日課は今の状況であろう。
(ユリア……我が妻は今日も美しい……)
ふと、空を見れば月が中天にかかろうとしている。
このままずっと彼女を見つめているのも幸せだが、そろそろ夜の時間だ。
ヴァレンスはぎゅっと拳を握ると決意を固める。
そう、決意。
彼にとっては重大な決意だ。
かれこれ二年ほどヴァレンスが苦慮している事案と言っても過言ではないのだ。
武術大会で優勝するよりも、入り乱れた戦場の指揮よりも難しいと言っても過言ではないだろう。
それは……
(今日こそは、ユリアとしっかり目を合わせて挨拶をしてみせる……!)
ユリアと挨拶を交わすというものだった。
ヴァレンスの脳内シミュレーションは完璧だ。
強敵に挑む前のように深呼吸をした後、背筋を伸ばすと扉を開き、妻のいる方向へと一歩踏み出す。
もちろん、扉の隙間から覗いていたことを気取られぬように細心の注意を払った上でだ。
そうして、ものすごく緊張したことを悟られないようにして、今まさに現れたかのような振る舞いで、ヴァレンスは口を開いた。
「ユリア、今日も祈りか?」
目標である挨拶は攻略することができた。
そうして、妻である聖女ユリアがこちらを振り向いてくる。
(…………!)
まるで銀糸を紡いだような、とても美しい白髪が揺れる。
紅くて神秘的な瞳には月光が宿り神聖さを高めていた。
まだ幼さを宿す愛らしい顔立ち。
香水などつけているはずもないのに漂う花の香。
華奢な体躯は、薄衣でできた寝衣に包まれている。
まるで女神のような出で立ちだ。
「あ」
あどけない少女のような可憐な声を聞いて、ヴァレンスは立ち眩みを起こしかけた。
だが、こんなところで倒れるなど武人の恥である。
彼は必死に自分を律して、その場に立ち留まった。
(このままだと、ユリアに不審がられるかもしれない)
思い切って、彼はまた一歩、彼女に向かって歩を進めた。
「ヴぁ、ヴァレンス様におかれましては……」
か細い訴えに、ヴァレンスの心は千々に乱れた。
(なぜだろう、まだ一言声をかけただけだというのに、ユリアが俺に怯えている)
まだ大人になりたてのユリアにとって、「冷血王」と呼ばれる自分の風貌はひどく恐ろしいものに見えているのかもしれない。
「ご機嫌麗……」
このまま嫌われたくないし、なんとか打ち解けたい。
(どうにかして、怯えるユリアの心をやわらげないといけない)
そう思ったヴァレンスの口から吐いた言葉は……
「ユリア、慣れない口上を使って、俺の機嫌を取る必要はない」
すると、ユリアの瞳が揺らめいた。
(ユリアにとっては俺は政略で出来た夫でしかない。ならばせめて、ユリアの心が穏やかなままに暮らせるように気遣うだけだ)
ユリアの心の負担を減らすべく、ヴァレンスは次の言葉を紡ぐ。
「修道女時代の癖がまだ抜けないようだな」
「あ……ご、ごめんなさ……」
「理由もないのに謝る必要もない」
ヴァレンスなりにユリアに安らぎを与えようと試みてみたのだが……
真面目な妻がしゅんと項垂れてしまっているではないか……!
(なぜ……だ……どうして、俺はいつもこうなのだ……)
動揺したヴァレンスは、けれども大人の貫録を見せたくて一度大きく深呼吸をした。
「ユリア、お前というやつは……本当に……」
(俺のことが嫌いで嫌いでたまらないんだな)
……冷血王ヴァレンス・セルツェは心の中で泣いた。
けれども、どうにかして夫婦としての交流をおこないたい。
ヴァレンスは妻ユリアの髪に口づけを落とした後、自身のサラリとした黒髪をかき上げながら告げる。
「お前は俺の妃となり、この国の王妃になったんだ。もっと堂々と振舞うと良い」
ユリアの反応はどうだろうか?
「はい、主君であり夫君であるヴァレンス様の仰せの通りに……」
そう答える彼女は妙に顔色が悪かった。
(これ以上ユリアに嫌われる前に離れなければならない)
間髪入れずにヴァレンスはユリアから離れた。
「俺は今晩も執務で忙しい。それでは」
「あ」
そうして、心の中で涙しながらヴァレンスはその場を離れた。
彼は歩きながら考える。
(なぜだろう? どれだけ脳内で訓練をしたところで、魔物の討伐のようにうまくいくことはない)
近年、「魔力持ち」が稀少になってきている。
元は魔力持ちが多い王家だったが、近年生まれてくる王族たちが引き継いだ力はごくわずかなものであり、この数代で王族の権威が揺るぎはじめていた。
そこで白羽の矢が立ったのが、魔力持ちの若い娘である。
(未来の国王である私に相応しい女性だと連れてこられたのがユリアだった)
王国の治世を盤石なものとするために、当時王太子だったヴァレンスの元にユリアが嫁いでくることになった。
けれども、修道女から還俗させられた妻はよほど夫のことが嫌いなのだろう。
毎晩部屋を訪ねても目すら合わせてはくれなかった。
(愛のない政略的な結婚だったせいか、ユリアはとことん俺のことを嫌っている)
軍人たるもの嫌がる女性に無理強いはできない。
そうして、子どもに恵まれないまま結婚二年の月日が経とうとしている
そんな中、ヴァレンスには側室として従妹の公爵令嬢を娶ってはどうかとの話が挙がってしまったのだった。
同じ場で話を聞いていたはずのユリアだったが、夫が側室を迎えることに対して全く関心がなさそうだった。
(ユリアは嫌っている俺の子など欲しくはないのだ。もしかしたら今回の側室の件も、俺に側室を娶ってもらって、どうにかして俺に触れられないようにと、聡いユリアが考えたことなのかもしれない)
ヴァレンスの悪い想像はどんどん膨らんでいく。
悶々としながら王城の執務室へと帰っていると、たまたま足元に何かががすり寄ってきた。
「ああ、黒猫か。今日もお前は一人か?」
ヴァレンスは同じ境遇の黒猫のことを、そっと抱きしめた。
柔和な笑顔を見せると、子ネコも嬉しそうににゃあと泣いた。
冷酷王と称されるヴァレンスからも自然と笑みが零れる。
(どうしてユリアの前では、こうやって自然に振舞えないのだろうか?)
武芸にばかり秀でて、女性の扱いなどよくわからないまま年を重ねてしまった。
「嫌われてはいるが、妻であるユリアやお前が心穏やかに暮らせるように、精を出さねばなるまいな」
そう呟いたけれども、彼の心の靄が晴れることはなかったのだった。
***
ネコと別れた後、ヴァレンスは一人寂しく部屋の窓辺に佇んでいた。
(俺が通り名の通りの冷血な男だったのなら、こんなに悪い想像はしなかったかもしれないのに……)
側室の話が上がっても気にも留めないユリアと、これから先どう距離を詰めて良いのかいよいよ分からなくなってきた。
(ユリアは俺のことを嫌っているのだ)
年頃の可愛らしい妻。
もう彼女の笑顔を数年見ていない。
だけれど、もしかして真に愛する男性に対してだけは、柔和な笑顔を浮かべたり、優しい言葉を掛けたりするのだろうか?
「ユリアをあのネコだと思えば良いのだろうか? ああ、ユリアがネコだったら、俺はこんなに苦しい思いはしなくて良かったのだろうか?」
夜に考え事をすると、どんどん暗くなってしまう。
「もう寝よう」
一人で眠るには広いベッドへと向かう。
自分のことを嫌っている妻のことをくよくよ考えるのをやめるためにも、ヴァレンスは床に就いたのだった。
かくして、すれ違う夫婦二人に神のイタズラが起こるのだった。
夜、王城の離れにて。
王妃の部屋の窓辺に一人の愛らしい女性――部屋の主であるユリアが天にいる最高神へと向かって祈りを捧げていた。
そんな彼女の後方、少しだけ開いた扉の向こうには……
世間では冷血王と呼ばれるヴァレンス・セルツェの姿があった。
軍人達の中でも目立つ高身長の彼だが、隠密行動を得意としていることもあり、彼是小一時間ほどこんな調子で扉の前に佇んでいる。
ユリアが祈りを捧げることを毎日の日課とするならば、ヴァレンスにとっての日課は今の状況であろう。
(ユリア……我が妻は今日も美しい……)
ふと、空を見れば月が中天にかかろうとしている。
このままずっと彼女を見つめているのも幸せだが、そろそろ夜の時間だ。
ヴァレンスはぎゅっと拳を握ると決意を固める。
そう、決意。
彼にとっては重大な決意だ。
かれこれ二年ほどヴァレンスが苦慮している事案と言っても過言ではないのだ。
武術大会で優勝するよりも、入り乱れた戦場の指揮よりも難しいと言っても過言ではないだろう。
それは……
(今日こそは、ユリアとしっかり目を合わせて挨拶をしてみせる……!)
ユリアと挨拶を交わすというものだった。
ヴァレンスの脳内シミュレーションは完璧だ。
強敵に挑む前のように深呼吸をした後、背筋を伸ばすと扉を開き、妻のいる方向へと一歩踏み出す。
もちろん、扉の隙間から覗いていたことを気取られぬように細心の注意を払った上でだ。
そうして、ものすごく緊張したことを悟られないようにして、今まさに現れたかのような振る舞いで、ヴァレンスは口を開いた。
「ユリア、今日も祈りか?」
目標である挨拶は攻略することができた。
そうして、妻である聖女ユリアがこちらを振り向いてくる。
(…………!)
まるで銀糸を紡いだような、とても美しい白髪が揺れる。
紅くて神秘的な瞳には月光が宿り神聖さを高めていた。
まだ幼さを宿す愛らしい顔立ち。
香水などつけているはずもないのに漂う花の香。
華奢な体躯は、薄衣でできた寝衣に包まれている。
まるで女神のような出で立ちだ。
「あ」
あどけない少女のような可憐な声を聞いて、ヴァレンスは立ち眩みを起こしかけた。
だが、こんなところで倒れるなど武人の恥である。
彼は必死に自分を律して、その場に立ち留まった。
(このままだと、ユリアに不審がられるかもしれない)
思い切って、彼はまた一歩、彼女に向かって歩を進めた。
「ヴぁ、ヴァレンス様におかれましては……」
か細い訴えに、ヴァレンスの心は千々に乱れた。
(なぜだろう、まだ一言声をかけただけだというのに、ユリアが俺に怯えている)
まだ大人になりたてのユリアにとって、「冷血王」と呼ばれる自分の風貌はひどく恐ろしいものに見えているのかもしれない。
「ご機嫌麗……」
このまま嫌われたくないし、なんとか打ち解けたい。
(どうにかして、怯えるユリアの心をやわらげないといけない)
そう思ったヴァレンスの口から吐いた言葉は……
「ユリア、慣れない口上を使って、俺の機嫌を取る必要はない」
すると、ユリアの瞳が揺らめいた。
(ユリアにとっては俺は政略で出来た夫でしかない。ならばせめて、ユリアの心が穏やかなままに暮らせるように気遣うだけだ)
ユリアの心の負担を減らすべく、ヴァレンスは次の言葉を紡ぐ。
「修道女時代の癖がまだ抜けないようだな」
「あ……ご、ごめんなさ……」
「理由もないのに謝る必要もない」
ヴァレンスなりにユリアに安らぎを与えようと試みてみたのだが……
真面目な妻がしゅんと項垂れてしまっているではないか……!
(なぜ……だ……どうして、俺はいつもこうなのだ……)
動揺したヴァレンスは、けれども大人の貫録を見せたくて一度大きく深呼吸をした。
「ユリア、お前というやつは……本当に……」
(俺のことが嫌いで嫌いでたまらないんだな)
……冷血王ヴァレンス・セルツェは心の中で泣いた。
けれども、どうにかして夫婦としての交流をおこないたい。
ヴァレンスは妻ユリアの髪に口づけを落とした後、自身のサラリとした黒髪をかき上げながら告げる。
「お前は俺の妃となり、この国の王妃になったんだ。もっと堂々と振舞うと良い」
ユリアの反応はどうだろうか?
「はい、主君であり夫君であるヴァレンス様の仰せの通りに……」
そう答える彼女は妙に顔色が悪かった。
(これ以上ユリアに嫌われる前に離れなければならない)
間髪入れずにヴァレンスはユリアから離れた。
「俺は今晩も執務で忙しい。それでは」
「あ」
そうして、心の中で涙しながらヴァレンスはその場を離れた。
彼は歩きながら考える。
(なぜだろう? どれだけ脳内で訓練をしたところで、魔物の討伐のようにうまくいくことはない)
近年、「魔力持ち」が稀少になってきている。
元は魔力持ちが多い王家だったが、近年生まれてくる王族たちが引き継いだ力はごくわずかなものであり、この数代で王族の権威が揺るぎはじめていた。
そこで白羽の矢が立ったのが、魔力持ちの若い娘である。
(未来の国王である私に相応しい女性だと連れてこられたのがユリアだった)
王国の治世を盤石なものとするために、当時王太子だったヴァレンスの元にユリアが嫁いでくることになった。
けれども、修道女から還俗させられた妻はよほど夫のことが嫌いなのだろう。
毎晩部屋を訪ねても目すら合わせてはくれなかった。
(愛のない政略的な結婚だったせいか、ユリアはとことん俺のことを嫌っている)
軍人たるもの嫌がる女性に無理強いはできない。
そうして、子どもに恵まれないまま結婚二年の月日が経とうとしている
そんな中、ヴァレンスには側室として従妹の公爵令嬢を娶ってはどうかとの話が挙がってしまったのだった。
同じ場で話を聞いていたはずのユリアだったが、夫が側室を迎えることに対して全く関心がなさそうだった。
(ユリアは嫌っている俺の子など欲しくはないのだ。もしかしたら今回の側室の件も、俺に側室を娶ってもらって、どうにかして俺に触れられないようにと、聡いユリアが考えたことなのかもしれない)
ヴァレンスの悪い想像はどんどん膨らんでいく。
悶々としながら王城の執務室へと帰っていると、たまたま足元に何かががすり寄ってきた。
「ああ、黒猫か。今日もお前は一人か?」
ヴァレンスは同じ境遇の黒猫のことを、そっと抱きしめた。
柔和な笑顔を見せると、子ネコも嬉しそうににゃあと泣いた。
冷酷王と称されるヴァレンスからも自然と笑みが零れる。
(どうしてユリアの前では、こうやって自然に振舞えないのだろうか?)
武芸にばかり秀でて、女性の扱いなどよくわからないまま年を重ねてしまった。
「嫌われてはいるが、妻であるユリアやお前が心穏やかに暮らせるように、精を出さねばなるまいな」
そう呟いたけれども、彼の心の靄が晴れることはなかったのだった。
***
ネコと別れた後、ヴァレンスは一人寂しく部屋の窓辺に佇んでいた。
(俺が通り名の通りの冷血な男だったのなら、こんなに悪い想像はしなかったかもしれないのに……)
側室の話が上がっても気にも留めないユリアと、これから先どう距離を詰めて良いのかいよいよ分からなくなってきた。
(ユリアは俺のことを嫌っているのだ)
年頃の可愛らしい妻。
もう彼女の笑顔を数年見ていない。
だけれど、もしかして真に愛する男性に対してだけは、柔和な笑顔を浮かべたり、優しい言葉を掛けたりするのだろうか?
「ユリアをあのネコだと思えば良いのだろうか? ああ、ユリアがネコだったら、俺はこんなに苦しい思いはしなくて良かったのだろうか?」
夜に考え事をすると、どんどん暗くなってしまう。
「もう寝よう」
一人で眠るには広いベッドへと向かう。
自分のことを嫌っている妻のことをくよくよ考えるのをやめるためにも、ヴァレンスは床に就いたのだった。
かくして、すれ違う夫婦二人に神のイタズラが起こるのだった。