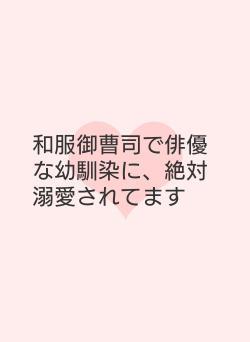我が国の皇帝は他国からの評判がすこぶる悪い人物だ。
十年前、父を殺して政権をくつがえした狂将軍オスカー・オベリウス。
残虐非道の通称通り、人を殺して愉悦に浸る。金の髪が紅い血で光る様は、魔王のようだと噂されている。
彼のお城に住んだら最後、生家に顔を出すことさえできず、残酷な死に方をする。
……そんな恐ろしい噂のある人物。
そして、か弱い乙女であるはずの私ビアンカは、かの人物の元へと馬車でガラガラと送り込まれていた。
***
事の発端は、半年ほど前に遡る。
帝国で革命が起こった後に孤児になって以来、十年ほど住み込みで働いていた宿屋。
そこに、高級な衣類を纏った人物が現れた。ふさふさの白い髭に白くて短い髪の毛。ちょっとだけお腹が出ていて、手で撫でまわす癖があるようで、しきりとお腹を撫でていた。
どうやら伯爵様だという。
「ねえ、そこの君、伯爵家に滞在して仕事をしないかね?」
宿屋の仕事は嫌いじゃなかったが、宿屋の主の息子に言い寄られてうんざりしていた。
心機一転、伯爵家のメイドの仕事なら楽しくやれそうだ。
軽い気持ちで伯爵家を訪ねたところ、なんと現れた伯爵令嬢は、双子の姉妹もかくやといわんばかりに私そっくりな女性だったのだ。
自分で言うのもなんだけど、毛先のちょっとだけ跳ねた赤毛、ちょっぴり低いけれどチャーミングな鼻、少しだけ小さめの桜色の唇、パーツも可愛らしいし全体的に整っている。まあしかし、品格みたいなものがないから、可愛い雰囲気しかないって感じ。
相手のお嬢様の方がもちろん綺麗なドレスに身を包んでいて、同じ顔立ちなのに愛らしく感じた。どうやら病弱らしくか弱い雰囲気で庇護欲をそそる感じの見た目。
ついでに言えば、お嬢様の名前はビビアン。
名前が似てるねって二人でさっそく盛り上がった。
「ビアンカは元気で明るくて逞しくて素敵だわ。どんな立場の人間にもしっかり意見を言うことができる」
「ビビアンは私の昔仲良くしてた幼馴染に似てる、すごく穏やかで優しくて、身分の差で人を馬鹿にしたりしない」
なんて心の優しいお嬢様なんだろう。
年の近い私たちはすぐに仲良しになった。
「ビアンカは私の知らない外の世界のことをとっても知ってて、すごいなって思ってる」
「何言ってるのよ、ビビアンの方こそ、色んなことを知っていて尊敬しちゃう」
けれども、ひと月ほど前のこと。
愛娘を溺愛している伯爵様から、私はとんでもない依頼を受ける。
「ビアンカよ、良ければ我が娘の代わりに、皇帝陛下オスカー様の元へと嫁いではくれないか?」
「はい……?」
素っ頓狂な声が出たのは言うまでもない。
「今度我が国を上げて、皇帝陛下のお妃選びが三か月間だけ開催されるんだ。各家から一人女性を差し出せと陛下は仰った。だが、儂は娘ビビアンのことを愛している。体も弱い子だし、寿命が縮まっては大変だ。恐ろしい噂のある陛下の元へはやれんのだよ」
「確かにビビアン様が城に行ったら、食い殺されてしまうかも?」
私は眉根を寄せて顎に手を当てながら唸った。
「そうじゃろう? だ・か・ら」
突然、伯爵様が私に向かってビシッと指を差してくる。
「ビアンカ、お前に代わりに言ってもらいたいんじゃ。何、お前は見た目は悪くないが、礼儀というものを知らん。皇帝陛下の目に留まるはずもなかろう。皇妃選びの三か月の期間中、皇帝陛下の目に留まりさえしなければ、お城で楽に暮らすことができる。つまり、黙ってさえいれば何もおきないんじゃ!」
「私に黙って……?」
「そうじゃ! 頼んだよ、ビアンカ! 幸せお城ライフを楽しんでくるんだよ」
伯爵様の言い回しに引っかかりは合ったけれど、要は名前を偽ってお妃選びに参加すれば良いだけだ。
とりあえず、なんとなくの淑女教育みたいなものを教え込まれたのだけれど、付け焼刃もいいところで、焼け石に水って感じで必死になって頑張った。
「ビアンカ、私の代わりにありがとう! ごほごほ」
仲良しのビビアンの代わりなら、気合を入れてやるしかない。
「頑張ってくるから、ビビアンは身体を大事にしておくのよ」
こうして、私はビビアン伯爵令嬢の代わりに、超絶恐ろしいと噂の皇帝陛下オスカー・オベリウスの住まう城へと向かうことになったのだった。
***
そうして、迎えたお妃候補になる当日。
ちょっとだけ香水くさい白粉を顔に塗られまくり、ここぞとばかりに頬紅や口紅を塗られた状態で、ここぞとばかりに愛らしいフリルたっぷりの桃色のドレスを着せられると、それなりに伯爵令嬢感のある女性に仕上がっていた。
(意外と私って可愛いんじゃなあい?)
ちょっぴり舞い上がりながら、豪奢な二頭立ての馬車に乗り込んで、皇帝の住まうお城へと向かうことになった。
ガラガラと駆け抜ける中、外の景色を見ると、初夏らしく新緑がキラキラ輝いている。
(国中の女性が集められているんだったら、もしかしたら幼馴染のあの子にも会えるかもしれないし、前向きに行きましょう)
まだ帝国内で革命が起こる前、私は兄と一緒に暮らしていた。私たち二人の共通の幼馴染。すごく綺麗な女性だった。
もしかしたら、今回彼女も城に来ているかもしれないのだ。
そうは思ったものの……
(っていうか、超絶悪名高い皇帝陛下様なわけでしょう? 私が偽物だってバレたら首でも斬られちゃったりして?)
想像したらゾッとしてしまった。だが、首を横にぶんぶんと振る。
(……か弱いビビアンのためにも、とにかく皇帝陛下の目に留まらないように三か月間乗りきれば良いわけよね? 覚悟を決めなさい、ビアンカ、女は度胸よ、私は舞台女優、舞台女優……)
馬車の中、私はビビアン伯爵令嬢を演じるべく、謎の呪文を唱えて暗示をかける。
皇帝オスカーの女除けのために皇妃として選ばれる未来が待ち受けているとは、この時の私は想像さえもしていなかったのだった。
***
そんなこんなでお妃選びが開催されている城に辿り着いた。
「うわあ……!」
巨大な正門を抜け、豪奢な薔薇の蔦で出来たアーチを馬車が潜り抜けると、向こう側に巨大なお城が見えてきた。
停車すると、扉がゆっくりと開かれると、ステップへ足をかけてゆっくりと地面に降り立つ。
目の前には、薔薇の花々が絡む純白の柱と壁。衛兵たちがズラリと門を大事に守っている。
「すごい……!」
私は田舎育ちなので、城の美麗さに衝撃を受けて、思わず感嘆の声を上げてしまった。
(いけない、いけない、田舎者だってバレてビビアンに迷惑かけちゃあ台無しね)
とりあえず伯爵家で教えこまれた礼儀作法に則って振舞ってみることにした。
(伯爵さまとビビアンは、とりあず背筋を伸ばして黙っておけば何とかなるって教えてくれたわよね?)
ひとまず言うことを聞くことにして、私は背筋を伸ばして腹筋に力を込めて前を見据えて、赤い絨毯の敷かれた階段へと一歩足を踏み入れた。
ゆっくりと登ると、大きな正面玄関の中へと慣れないヒールで進む。
天井まで届きそうなほど高い扉が開け放たれる。
大広間の中では、皇妃候補たちがひしめきあっていた。色とりどりのドレスが綺麗で、まるで花々が躍っているようだ。
(若い女性ばかりだと思っていたら、わりと年配の女性もいるのね)
とにかく国中の独身女性が集められているといったところだろう。
きゃっきゃっと小鳥のように会話する女性達も一部存在はするようだが、大半の女性達が皇帝の悪評を恐れてどんよりしているようだった。
ちょうど、その時、衛兵たちがどよめきはじめる。
「オスカー様、まだお時間ではございません……!」
だが、衛兵たちの制止も聞かずに、扉の向こうから高身長の男性が姿を現わした。
「俺に指図するな」
色香を孕んだ低い声音には、聞いたもの全てがひれ伏すような、そんな圧倒的な存在感があった。
ビアンカの背筋にもゾクリとした感覚が駆けあがる。
(この人が狂将軍と呼ばれた皇帝……オスカー)
サラサラの金糸のような髪、鋭く獰猛な獣のような紫水晶の瞳。
凛々しくも雄々しい眉に、すっと通った鼻筋、凛々しく引き結ばれた唇。
元々将軍であるからか、黒い帝国騎士団の制服を身に纏っており、腰には皇帝だけが許される竜の紋章が描かれた剣を下げていた。
紅いマントを翻しながら颯爽と歩く姿は、まるで雄々しき百獣の王のようだ。
彼の出で立ちに、広間にいた皆が魅了されると同時に圧倒されてしまう。
(あれ? なんだろう、私、この人のこと、どこかで……?)
思い出そうとするけれど、どうにも思い出すことが出来ない。
ふと、オスカーの元へと一人の令嬢が近づいた。黒髪を夜会巻きにして真紅のドレスに身を包んだ女性だ。
「オスカー様、お会いしとうございました。わたくしは将軍の娘の……」
すると……
「黙れ、誰が近くに寄って良いと言った?」
「……ひっ……」
オスカーに睥睨された令嬢が、ぶるぶると身体を震わせる。
「大臣たちが国中の女を集めたようだが、俺は誰も皇妃に迎えるつもりはない。三か月間、民たちの血税を使って城の中で暮らされても迷惑だ。即刻立ち去れ」
広間にいた皆がざわざわりとざわめきはじめた。
私は意味を理解すると同時に、相手に対して沸々と怒りが生じはじめる。
(何? この人、ちゃんと皇帝陛下としての役割を果たす気があるの……?)
そりゃあ確かに血税がかかっているかもしれないが、皇族の血を残すのだって皇帝としての役割の一つだろうに。
(そもそもここに皆を集めるのにお金がかかったでしょうに。揃えられた女性達みんなが自費で参加したわけじゃないでしょう?)
すると、また別の令嬢がオスカーの前に躍り出た。今度は、緩いブラウンの髪に橙色のドレスを身に纏った女性だ。
「そんなっ、オスカー様、お妃選びには三か月の期間がございます。どうか私たちとの時間を作ってはくださいませんか? そうでなければ、辺境にいる父に叱られてしまいます!」
オスカーが呆れたように溜息を吐いた。
「それはお前たちの都合だろう。俺は知らない」
「ですが……」
「俺は私利私欲のために皇妃を狙うような女をそばに置くつもりはない」
なおも縋りつこうとする令嬢のことを無情にもオスカーが腕で振り払う。
そのせいで、令嬢は尻餅をついた。
「きゃっ……!」
周囲の皆のざわつきは止まない。
そこで……私の堪忍袋の緒はプチンと切れた。
「ちょっと、あんた! 黙って聞いてれば、皇帝陛下だかなんだか知らないけれど、調子に乗りすぎなんじゃない!」
「誰だ? お前こそ誰に向かって口を聞いている?」
オスカーが振り返って私の方を見てきた。
瞬間、彼の瞳が本当に一瞬だけ揺れ動く。
「お前は……」
私は相手を指さしながら叫んだ。
「女性に対して横暴すぎるわよ! 文句があるんだったら、集める前に大臣に文句言いなさいよ! 色んな事情があって集まってんのよ、皆!」
「今言っただろう、俺には関係のない話だと」
「あんたのために集まってやってんの!」
すると、オスカーがはっと息を吐く。
「この俺に口答えするとは良い度胸だ。だが、場はわきまえてもらいたい」
「はあ? まだ話の途中で……!」
目の前の彼がパチンと指を鳴らした。
すると、私の周りに一斉に衛兵たちが集結する。
「きゃあっ、いたたっ、何するのよっ……! ちょっと、髪の毛引っ張らないで!」
私のことを衛兵たちが取り押さえ始めた。
そんな中、オスカーは不遜な態度を崩さずに問いかけてくる。
「お前、名は何という?」
「は? あんたに名乗る名前なんて持ち合わせてなんかないんだけど!」
すると、オスカーが不敵に笑んだ。
「俺に歯向かうとは、とんでもない女がいたものだ。連れて行け」
「は!」
そうして、衛兵たちがオスカーに向かって問いかけた。
「この娘、連れて行くのは牢屋でしょうか?」
そこで私は内心マズい事態に陥ったことに気付く。
(やばい! 伯爵様とビビアンに迷惑かけちゃう! 城に来て早々に牢屋行きになるなんて……)
焦っていたら、私はちょうどオスカーとばっちり目が合ってしまった。
彼は口の端をゆるりと吊り上げる。
「牢屋ではない、俺の寝室だ」
周囲にどよめきが走る。
「しつけがいがありそうな見た目と体つきをしている。悪くない」
私の全身をだらだらと汗が滝のように流れる。
(ま、まずい)
こちらを見下ろすオスカーの表情は喜悦に歪んでいた。
そうして、彼がこれみよがしに私に手を差し出してくる。
「さあ、俺を愉しませてくれよ、名無しのご令嬢」
城に到着して早々、やらかした私は貞操の危機に見舞われたのだった……!
***
私は桃色の薄絹に着替えさせられると、皇帝オスカーの寝室とやらに連れてこられていた。
とてつもなく豪奢な部屋だ。
真紅の絨毯の上には、金で縁どられた木製の調度が立ち並ぶ。
部屋の絨毯には、これまた豪華な天蓋付きのベッドが備えられており、大人三人ぐらいは悠々自適に眠れそうだ。
ふわふわの寝具の上、薄絹に着替えさせられた私は、大広間での出来事を思い出して後悔していた。
「ううう、やらかした、どうにかして脱出しないと……!」
ベッドの上でピョンピョン跳びはねながら、天窓の位置を確認していると、入り口の扉がギギイっと開く。
カツカツと軍靴を鳴らしながら現れたのは……
「名無しの令嬢、会いに来てやったぞ」
「あんた!」
皇帝オスカーだった。
私の前に立つと不遜な態度で見下ろしてくる。
「この俺がお前に皇妃としての役割を果たさせてやるんだ。光栄に思え」
「何よ、偉そうに! まだ皇妃選びの最中でしょう! 皇妃の役割なんて果たしたくなんかないっての! それに私以外のご令嬢たちがいっぱいいたでしょう!? あの人たちから選びなさいよ!」
すると、オスカーがふんと鼻を鳴らした。
「お前、やはり気概は良いが、何も分かってないようだな」
「は? 何が言いたいのよ?」
「あの令嬢たち、手に暗器を持っていたのに気づいていなかったのか?」
「え?」
オスカーから思わぬことを告げられ、私の中に動揺が走る。
「あの令嬢二人は共謀していた。俺が触れてもいないのに尻餅をついていた令嬢がいただろう? お前は勇猛果敢に俺の前に立ちふさがったが……俺が衛兵たちを呼んでいなかったら、お前は暗器に貫かれて命を落としていたぞ」
「え……?」
私は衝撃を受けると共に、オスカーを見上げてハッとする。
(まさか、この人、私のことを助けてくれたの……?)
彼は続けた。
「革命から十年。国の中には俺のことを嫌う連中も多い。皇帝の首の座はいつも狙われているといっても過言ではない」
「皇帝の首を……」
「そうじゃなくても、自分こそが正妃になろうと、他の貴族の令嬢たちを蹴落とそうと必死な貴族連中たちで溢れている。妃選びの場だと言っても、血なまぐさいものだよ。ここに来た以上、お前だっていつく寝首をかかれるか……」
お妃選びに来て静かに過ごすだけのつもりだったのに……
(とんだバトルロワイヤルじゃない……ビビアンが来てたらと思うとぞっとするわ……っていうか……)
「まさか……! 下手したら、私も殺されちゃうの……?」
私は自分の顔から血の気が引いていくのを感じた。
(何よ! 伯爵様の嘘つき! 全然のんびり過ごすどころか殺されちゃうんじゃないのよ!)
その時。
ギシリ。
ベッドが軋む音が聞こえたかと思うと、オスカーが騎士団の上衣を脱ぎながら、私の身体の上に跨ってくる。
「さて、お前の命を守ってやる礼を身体で払ってもらおうか……妃としてな」
「は……? 何言って、まだお妃さまは選んでる途中でしょう!? ひゃっ……!」
彼の大きな手が私の頬に許可なく触れてくる。あまりにもひんやりしていたものだから、びっくりして声を上げてしまった。
紫水晶の瞳に射抜かれると心臓がドクンと跳ねる。
(何? 私、この瞳、どこかで……)
私の耳元に彼が唇を寄せると、色香を孕んだ声音で囁いてくる。
「この国では俺が絶対だ。お前の指図は受けない」
「なっ……!」
すると、オスカーが私の頬にかかっていた髪を耳にそっとかけてきた。
「ひゃっ、何して、くすぐったいっ……」
彼の指の腹は剣凧ができているせいもあってか硬くて、肌の上をなぞられると、少しだけざらつきを感じてしまう。なぜだか妙に気恥ずかしくなってしまった。
「もう、ちょっと……! 辞めてってば……!」
「黙って俺の言うことを聞いておけ」
どうにかして逃げようと身体を捻ろうとするのだが、オスカーの大きな体に阻まれてしまって出来そうもない。
「あんた……友達いないでしょう……絶対……」
すると、オスカーが答えた。おかげで熱い吐息が耳の穴にかかって、ゾクゾクとした感覚が駆けあがってくる。
「……どうかな。昔はいた気もするが……残念ながら、十年前に俺は皇帝の位についた。それ以来、対等な立ち位置で俺に物を言える者なんて存在しない」
「……おかげで残念ながら社交性が育たなかったみたいね……こんな風に女性を乱暴に扱ってくるなんて……あっ……」
「乱暴とは聞き捨てならないな……俺はお前に妃教育を施しているだけだよ」
「あんたの妃なんて、お断りだっての……!」
そうして、気付いた時には、彼の手が私の太腿に伸びてきていた。
「やあっ、何してっ……!」
「さあ、俺の命令を聞け。生きたままこの城を出たいんだったらな」
だがしかし。
「嫌よ」
ビアンカが両脚をぴっちり閉じたままキッパリと告げると、オスカーがうんざりした表情を浮かべたままぼやく。
「ふん、あの令嬢たちが俺を狙った刺客だと言えばすぐに信じたから、簡単に絆されてくれるかと思ったが、なかなかしぶとい女だ」
「え?」
(こいつ、今なんて言ったの? 先ほどの令嬢たちの話は嘘だったということ?)
騙されていたのだと思うと、全身がわなわなと震えた。
「この俺に抱かれたがる女は万といたが、こんなに抵抗されるのは初めてだな。どれ、俺がお前に得意の……」
オスカーが何か続けかけたが、私の堪忍袋の緒はブチ切れた。
「嘘つくなんてサイテー! 女性だなんだってモノ扱いみたいな態度もあり得ない! こういうことは、本当に好きな者同士がしないと意味がないんだから!」
嘘ついているのは私もなのだが、そんなことは忘れて……
特大ブーメラン発言が跳ね返ってくるのを内心で受け止めつつ、私は相手をキッと睨みつける。
すると……
オスカーが口の端をにやりと吊り上げた。
「気に入った」
「へ?」
そうして、泰然とした態度でオスカーが告げてくる。
「俺の正妃になってもらおうか」
「は……?」
私は思わず固まってしまった。
「もちろん、三か月後の妃選びが終わる頃には離婚前提、でな。おかげで側妃狙いの女が俺に寄って来なくてすむというものだ」
相手の言い分を理解するのに時間がかかる。
「そんなあんただけが得する契約、結ぶわけないじゃない! ふざけないで!」
私が眉を吊り上げて抗議すると、オスカーが嘆息した。
「この俺の話を平然と断るなんて……とんでもない女がいたものだ」
「は? あんたの……あなたの方がとんでもないのでは? 妻に出会って早々、『この結婚は離婚前提だ』とかいうなんて……ロマンス小説の読みすぎなんじゃありませんこと?」
だがしかし、オスカーは私の話を華麗にスルーした。
「さて、一応調べはついている。お前はどうやら伯爵家の娘ということになっているそうだが、間違えはないか?」
「ないわよ……!」
そこまで話して、私はハッとする。
(そうだった、私は今ビビアン伯爵令嬢なんだった……!)
内心冷や汗をかきつつ取り繕うことにする。
「ほほ……ごめんあそばせ。皇帝陛下様のお願いは聞けませんことよ。良ければ、他の女性達にお願いしてはいかがでしょう?」
すると、オスカーがフンと鼻を鳴らした。
「お前が俺の皇妃になるのを断るというのなら、伯爵家を取り潰しにしようか」
「な……!」
このままだと伯爵様とビビアンに迷惑がかかってしまう。
それだけは、どうしても避けないといけない。
「さ……サイテー!」
「誉め言葉として受け取っておこう」
そうして、オスカーが悠然と微笑んだ。
「三か月の間、俺をたっぷり満足させてくれよ、ビビ」
ビビ。
(私の小さい頃のあだ名……なんで知ってるの?)
そこでハッとなった。
(って、今の私がビビアンだからビビなのか……!)
とりあえず想定外の事態に陥ったことだけは理解できた。
もうこうなったらヤケだ。
「上等よ、あんたの正妃とやらになって、この三か月で、あんたの腐った性根を叩き直してやるから!」
不遜な態度のオスカーを私はきっと睨みつける。
(そういえば、私、ビビアンだって名乗ったっけ?)
かくして――三か月限定の、私の偽の皇妃生活が始まったのだった。
***
しばらく経って、夜更け頃。
ものすごい勢いで啖呵を切っていたビアンカだったが、オスカーのそばですやすやと寝息を立てて眠っていた。
「むにゃあ……」
「昔から破天荒だったが、あのまま俺のそばで呑気に眠るとは、とんでもない女に成長したものだ……」
オスカーは眠りに就いたビアンカの姿を見ながら独り言ちた。
「妃選びで、お前を探せたらと思っていたが、こんなに早く見つかるとはな……」
「……ん」
その時、淑女とは思えない勢いでビアンカが寝返りを打った。
驚いて体を仰け反らせたオスカーだったが……
「むにゃ…………そばにいて……スカーレット…………」
オスカーの胸の前、まるで猫のように彼女は丸まった。
なんとなく落ち着かないが、彼女が身体を擦り寄せてくるものだから、オスカーはベッドの上で逃げ場を失ってしまう。
……スカーレット。
オスカーは空にかかる月を眺めた。
ありし日の記憶が蘇ってくる。
『兄さま! スカーレット! ビビを探してごらんなさいよ!』
今は亡き親友とその妹の声が、オスカーの脳内に響いてくる。
「懐かしい名前だな」
そうして、オスカーは眠るビアンカを優しく抱き寄せた。
「やっと探し出せたんだ。俺はもうお前を逃すつもりはないよ……ビビ」
「……む、なんか、スカーレットなのに硬い……」
文句を言うビアンカのことを眺めながら、その夜、ずっと孤独だった皇帝は久しぶりに幸せな夜を過ごした。
まさか三ヶ月経っても正妃のまま過ごす運命にあるとは露知らず……ビアンカは懐かしい夢を見ていたのだった。