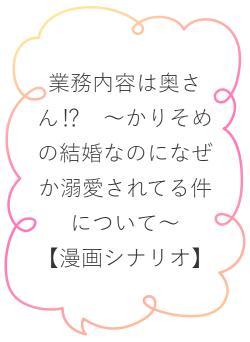紫苑がいるから、安心できて温かかった。
もちろん、葉奈と世津の存在も大きかった。
それでも、紫苑のおかげで芹香は寂しい夜も一人にはならずに済んだ。
離縁を申し出た日、紫苑が霊狐だと知らされた時は、驚いたし正直腹立たしさもあった。
華狐としてそばにいてほしいと言われたときは、胸がずきりと痛んだ。
けれども……、そんなことはどうでもよくなるくらい、紫苑と過ごす時間は芹香にとって大切で……芹香の心は、紫苑がそばにいるだけで満ち足りていた。
たとえ、紫苑が望むのが自分ではなく華狐であっても、そばにいられるのなら構わないと思っていた。なのに、叔父に騙され鵺に力を吸われ、それすらも失ってしまったとき、芹香を襲ったのは、死を望んでしまうほどの絶望。
紫苑のそばに、温かいみんなの元に帰れないのなら、いっそのこと死んでしまいたい。
鵺に殺してと願ったのは、本心だった。
だけど、
『ほかの華狐など要らない! 俺は、芹香を迎えにきた』
紫苑の優しさは、いとも簡単に絶望を喜びに塗り替えてしまう。
あのとき芹香は、自分にとって紫苑がどれほど大きな存在になっていたかを思い知ったのだ。
あの絶望を知り、紫苑に心を明け渡された今、手にした存在を失うことなど芹香は考えられなかった。
自分も、思いを伝えなければと思うのに、上手く言葉が出ない芹香に紫苑は優しいまなざしを向ける。
「俺の知る芹香は、いつもひたむきで、葉奈や世津たちにも優しく、感謝の気持ちを忘れない誠実で綺麗な心を持っていて……そんな芹香のそばは、霊狐の俺にいつも心の安らぎを与えてくれた」
瞬きと共に、溜まっていた涙が落ちていく。濡れた頬を、紫苑の指がそっと拭う。細められた瞳から悲し気な色は消え、とても穏やかな表情をしていた。
「芹香が華狐だからじゃない。芹香だからそばにいたいし、そばにいてほしい」
まっすぐな紫苑の思いは、ずたずたに傷つき疲れ果てた芹香の心を真綿のように優しく包み込んでいく。
「芹香じゃないと、だめなんだ。……──だから、俺のそばにいてくれるか?」
穏やかに、けれども熱を孕んだ懇願に芹香は頷き、言葉を紡ぐ。
「私も、紫苑じゃなきゃ、だめ。紫苑と家族になりたい」
「芹香」
重ねられていた紫苑の手を握り返した。途端に、もう片方の手が重なり、挟まれるようにぎゅっと閉じ込められる。
恥ずかしさに耐えながら見上げた先には、優しさを宿した紫苑の顔があった。琥珀色の瞳に愛おし気にみつめられる。芹香のことが大切で仕方がないと訴えているのがその表情から見て取れて、胸が高鳴る。
紫苑が自分に言葉を尽くして思いを伝えてくれたように、自分の思いを言葉でちゃんと伝えたかった。
「紫苑のことがすき。私の心も、とっくに紫苑のものだよ」
大切なものを失う恐怖を芹香は知っていた。
手に入れてしまえば、失う恐怖と隣り合わせになるとわかっていた。
わかった上で、手に入れたいと思えるものが、今、この手の中にある。壊したくないから触れないのではなく、触れたいほど大切だから手を伸ばすのだ。その勇気を、芹香は紫苑からもらった。
「私を、選んでくれてありがとう、紫苑」
笑顔でなんとか言い切ったけど、細まった目尻からは堪えきれずに涙が零れ落ちた。
つぎの瞬間には、手を引かれて紫苑に抱きしめられ、甘く名前を呼ばれる。
「し、紫苑、苦しいよ」
恥ずかしさを紛らすように苦笑しながら抗議する芹香の耳元で、紫苑が愛を囁いた。
──愛している、と。
固まる芹香に、紫苑は何度も言葉を重ねる。
「愛しい俺のつま。もう二度と、離縁するなどと言わないでくれ」
抱きしめていた腕を緩めて、紫苑が芹香を下から覗き込む。紫苑の膝の上に半ば膝立ちの恰好になり、芹香が紫苑を見下ろす体勢になった。冗談半分、本気半分のその声音に、芹香は目を丸くして堪らず噴き出してしまう。
「笑いごとじゃない。約束してくれ、もう俺のそばから決して離れないと」
真剣なまなざしに、胸が打たれる。
「約束する。この先、なにがあっても紫苑のそばから離れない。──紫苑のほうこそ覚悟して? 離縁してくれって頼まれても泣きつかれても、絶対離縁してやらないんだから」
ふふんと茶目っ気に言うと、頬を両手で包みこまれた。まっすぐに見つめられて、芹香も見つめ返す。
「大丈夫だ。そんな日は、永遠に訪れない」
琥珀色の瞳に見惚れているうちに芹香の視界は紫苑で一杯になり、どちらからともなく瞼を閉じれば、唇が優しく重ねられた。
甘く優しい口づけに、とてつもない幸福感が込み上げ、閉じたままの芹香の眦からは幸せの涙が溢れた。
― 了 ―
もちろん、葉奈と世津の存在も大きかった。
それでも、紫苑のおかげで芹香は寂しい夜も一人にはならずに済んだ。
離縁を申し出た日、紫苑が霊狐だと知らされた時は、驚いたし正直腹立たしさもあった。
華狐としてそばにいてほしいと言われたときは、胸がずきりと痛んだ。
けれども……、そんなことはどうでもよくなるくらい、紫苑と過ごす時間は芹香にとって大切で……芹香の心は、紫苑がそばにいるだけで満ち足りていた。
たとえ、紫苑が望むのが自分ではなく華狐であっても、そばにいられるのなら構わないと思っていた。なのに、叔父に騙され鵺に力を吸われ、それすらも失ってしまったとき、芹香を襲ったのは、死を望んでしまうほどの絶望。
紫苑のそばに、温かいみんなの元に帰れないのなら、いっそのこと死んでしまいたい。
鵺に殺してと願ったのは、本心だった。
だけど、
『ほかの華狐など要らない! 俺は、芹香を迎えにきた』
紫苑の優しさは、いとも簡単に絶望を喜びに塗り替えてしまう。
あのとき芹香は、自分にとって紫苑がどれほど大きな存在になっていたかを思い知ったのだ。
あの絶望を知り、紫苑に心を明け渡された今、手にした存在を失うことなど芹香は考えられなかった。
自分も、思いを伝えなければと思うのに、上手く言葉が出ない芹香に紫苑は優しいまなざしを向ける。
「俺の知る芹香は、いつもひたむきで、葉奈や世津たちにも優しく、感謝の気持ちを忘れない誠実で綺麗な心を持っていて……そんな芹香のそばは、霊狐の俺にいつも心の安らぎを与えてくれた」
瞬きと共に、溜まっていた涙が落ちていく。濡れた頬を、紫苑の指がそっと拭う。細められた瞳から悲し気な色は消え、とても穏やかな表情をしていた。
「芹香が華狐だからじゃない。芹香だからそばにいたいし、そばにいてほしい」
まっすぐな紫苑の思いは、ずたずたに傷つき疲れ果てた芹香の心を真綿のように優しく包み込んでいく。
「芹香じゃないと、だめなんだ。……──だから、俺のそばにいてくれるか?」
穏やかに、けれども熱を孕んだ懇願に芹香は頷き、言葉を紡ぐ。
「私も、紫苑じゃなきゃ、だめ。紫苑と家族になりたい」
「芹香」
重ねられていた紫苑の手を握り返した。途端に、もう片方の手が重なり、挟まれるようにぎゅっと閉じ込められる。
恥ずかしさに耐えながら見上げた先には、優しさを宿した紫苑の顔があった。琥珀色の瞳に愛おし気にみつめられる。芹香のことが大切で仕方がないと訴えているのがその表情から見て取れて、胸が高鳴る。
紫苑が自分に言葉を尽くして思いを伝えてくれたように、自分の思いを言葉でちゃんと伝えたかった。
「紫苑のことがすき。私の心も、とっくに紫苑のものだよ」
大切なものを失う恐怖を芹香は知っていた。
手に入れてしまえば、失う恐怖と隣り合わせになるとわかっていた。
わかった上で、手に入れたいと思えるものが、今、この手の中にある。壊したくないから触れないのではなく、触れたいほど大切だから手を伸ばすのだ。その勇気を、芹香は紫苑からもらった。
「私を、選んでくれてありがとう、紫苑」
笑顔でなんとか言い切ったけど、細まった目尻からは堪えきれずに涙が零れ落ちた。
つぎの瞬間には、手を引かれて紫苑に抱きしめられ、甘く名前を呼ばれる。
「し、紫苑、苦しいよ」
恥ずかしさを紛らすように苦笑しながら抗議する芹香の耳元で、紫苑が愛を囁いた。
──愛している、と。
固まる芹香に、紫苑は何度も言葉を重ねる。
「愛しい俺のつま。もう二度と、離縁するなどと言わないでくれ」
抱きしめていた腕を緩めて、紫苑が芹香を下から覗き込む。紫苑の膝の上に半ば膝立ちの恰好になり、芹香が紫苑を見下ろす体勢になった。冗談半分、本気半分のその声音に、芹香は目を丸くして堪らず噴き出してしまう。
「笑いごとじゃない。約束してくれ、もう俺のそばから決して離れないと」
真剣なまなざしに、胸が打たれる。
「約束する。この先、なにがあっても紫苑のそばから離れない。──紫苑のほうこそ覚悟して? 離縁してくれって頼まれても泣きつかれても、絶対離縁してやらないんだから」
ふふんと茶目っ気に言うと、頬を両手で包みこまれた。まっすぐに見つめられて、芹香も見つめ返す。
「大丈夫だ。そんな日は、永遠に訪れない」
琥珀色の瞳に見惚れているうちに芹香の視界は紫苑で一杯になり、どちらからともなく瞼を閉じれば、唇が優しく重ねられた。
甘く優しい口づけに、とてつもない幸福感が込み上げ、閉じたままの芹香の眦からは幸せの涙が溢れた。
― 了 ―