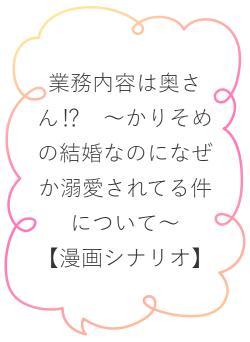「私……華狐として、紫苑の役にたてなくなっちゃって……ごめんなさい……」
自分には、もう華狐としての資格がない。
憎しみに支配されて、霊力を使い切ってしまった己の愚かさを謝った。
「だから、」
「──誰がなんと言おうが、俺の華狐は芹香しかいない」
芹香の言葉を言わんとすることを察したように、厳しい顔つきで紫苑が言う。
「でも、私にはもう力が……」
目の前の紫苑は、その整った顔を苦し気に歪めた。まるで傷ついたような顔をしていた。
「芹香は……ここに……俺のそばにいるのが嫌か?」
嫌なはずがない。
ここには、芹香が失ったものがあった。
家族のように温かい紫苑たちと、絶えない笑顔と優しさ。同じ時を過ごす内に、いつしか彼らは芹香にとって失いたくないと思える、代えのきかない存在になっていた。
しかし、それを素直に口にだすことはどうしても憚られた。
浮かんでくるのは、屋敷に訪れた霊狐の一族の人たちの顔。
みんな一心に、「霊狐を支えてくれ」と華狐の芹香に願っていた。霊力を失った今、自分には紫苑を支えることはきっとできないだろう。それをわかった上で己の望みを口にするのは、裏切りではないだろうか。
逡巡して言葉が出ないでいると、紫苑の手が伸びてきて芹香の手を包む。するりと触れる肌は滑らかで温かくて、思わず握り返したくなる。
涙の溜まった目で見上げると、琥珀色の瞳と視線が合わさった。ふるふると揺れる視界の中でも、その瞳に悲痛な色が見て取れて苦しさが増す。
紫苑を傷つけてしまった。
自分には、もう華狐としての資格がない。
憎しみに支配されて、霊力を使い切ってしまった己の愚かさを謝った。
「だから、」
「──誰がなんと言おうが、俺の華狐は芹香しかいない」
芹香の言葉を言わんとすることを察したように、厳しい顔つきで紫苑が言う。
「でも、私にはもう力が……」
目の前の紫苑は、その整った顔を苦し気に歪めた。まるで傷ついたような顔をしていた。
「芹香は……ここに……俺のそばにいるのが嫌か?」
嫌なはずがない。
ここには、芹香が失ったものがあった。
家族のように温かい紫苑たちと、絶えない笑顔と優しさ。同じ時を過ごす内に、いつしか彼らは芹香にとって失いたくないと思える、代えのきかない存在になっていた。
しかし、それを素直に口にだすことはどうしても憚られた。
浮かんでくるのは、屋敷に訪れた霊狐の一族の人たちの顔。
みんな一心に、「霊狐を支えてくれ」と華狐の芹香に願っていた。霊力を失った今、自分には紫苑を支えることはきっとできないだろう。それをわかった上で己の望みを口にするのは、裏切りではないだろうか。
逡巡して言葉が出ないでいると、紫苑の手が伸びてきて芹香の手を包む。するりと触れる肌は滑らかで温かくて、思わず握り返したくなる。
涙の溜まった目で見上げると、琥珀色の瞳と視線が合わさった。ふるふると揺れる視界の中でも、その瞳に悲痛な色が見て取れて苦しさが増す。
紫苑を傷つけてしまった。