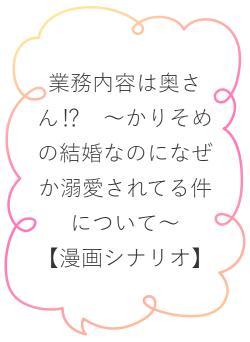まるでやきもちを焼いているように聞こえて、喜びを感じそうになる自分を芹香は内心で窘めた。
紫苑は、芹香のそばが落ち着けると言ってくれたが、それだけだ。きっと、それ以下でもそれ以上でもない。
芹香はなんとなく、霊狐にとって華狐という存在がもともとそうなのではないかと思い始めていた。
これまで華狐に選ばれた娘が帰ってきたことはないと言われているのも、つまりはそういうことなのだろう。端から霊力の相性がよい娘が選ばれて、番うように仕向けられている気がしてならない。
──だって、自分には紫苑にそう感じてもらえるような特別なものをなに一つ持っていないから。
だから、紫苑が自分といて心地よいと感じるのは、いわば自然の摂理のようなもので、芹香だからではないと、勘違いをしてはならないと自分に言い聞かせていた。
「違うわ紫苑。みんな、私が紫苑の華狐だからよくしてくれるの。みんなと話してると、紫苑が慕われてるのがよくわかる」
会いにきた狐たちは、口々に紫苑のことを褒めちぎっていた。
さっき来た弥助も、きょろきょろと紫苑の姿を探していたし、結局最後まで会えなかったため肩を落として帰っていった。
「……慕われてるのは、俺が先代の霊狐の息子だからだろうな」
ふいに、紫苑の声音が暗くなり、芹香は振り向いた。至近距離に見えた紫苑の顔は、俯いていてどこか物思いにふけっているのか焦点の定まらない目をしていた。
「芹香の言葉を借りるなら、それこそ、俺だからではないんだ。先代の息子だから慕ってくれているんだ」
かける言葉が見つからない。芹香はここのことをまだよく知らないから、紫苑の言うことが事実なのかそうじゃないのかまで判断がつかない。いい加減なことを言っても、紫苑の慰めにすらならないと思った。
それくらい、紫苑の表情は暗かった。今までに見たことがないほどに。
「紫苑……」
「……ん」
名前を呼ぶと、ようやく視線が芹香を捉えた。
「……わ、私は……、先代の霊狐さまのことは知らないけど……、紫苑の華狐になれて、その、嬉しいと思ってるよ」
「芹香」
悲しいとも苦しいともつかない瞳が、徐々に色を取り戻していくのが見て取れてホッとしたのも束の間、美しい紫苑の顔が近づいてきた。
「あ! も、もうこんな時間! お昼の支度しなくちゃ! これ葉奈に届けてくるわねっ」
視界一杯に紫苑が映り、それがなにを意味するのかに気付かないほど子どもでもなかった芹香は、慌てて紫苑の腕の中から逃げ出したのだった。
紫苑は、芹香のそばが落ち着けると言ってくれたが、それだけだ。きっと、それ以下でもそれ以上でもない。
芹香はなんとなく、霊狐にとって華狐という存在がもともとそうなのではないかと思い始めていた。
これまで華狐に選ばれた娘が帰ってきたことはないと言われているのも、つまりはそういうことなのだろう。端から霊力の相性がよい娘が選ばれて、番うように仕向けられている気がしてならない。
──だって、自分には紫苑にそう感じてもらえるような特別なものをなに一つ持っていないから。
だから、紫苑が自分といて心地よいと感じるのは、いわば自然の摂理のようなもので、芹香だからではないと、勘違いをしてはならないと自分に言い聞かせていた。
「違うわ紫苑。みんな、私が紫苑の華狐だからよくしてくれるの。みんなと話してると、紫苑が慕われてるのがよくわかる」
会いにきた狐たちは、口々に紫苑のことを褒めちぎっていた。
さっき来た弥助も、きょろきょろと紫苑の姿を探していたし、結局最後まで会えなかったため肩を落として帰っていった。
「……慕われてるのは、俺が先代の霊狐の息子だからだろうな」
ふいに、紫苑の声音が暗くなり、芹香は振り向いた。至近距離に見えた紫苑の顔は、俯いていてどこか物思いにふけっているのか焦点の定まらない目をしていた。
「芹香の言葉を借りるなら、それこそ、俺だからではないんだ。先代の息子だから慕ってくれているんだ」
かける言葉が見つからない。芹香はここのことをまだよく知らないから、紫苑の言うことが事実なのかそうじゃないのかまで判断がつかない。いい加減なことを言っても、紫苑の慰めにすらならないと思った。
それくらい、紫苑の表情は暗かった。今までに見たことがないほどに。
「紫苑……」
「……ん」
名前を呼ぶと、ようやく視線が芹香を捉えた。
「……わ、私は……、先代の霊狐さまのことは知らないけど……、紫苑の華狐になれて、その、嬉しいと思ってるよ」
「芹香」
悲しいとも苦しいともつかない瞳が、徐々に色を取り戻していくのが見て取れてホッとしたのも束の間、美しい紫苑の顔が近づいてきた。
「あ! も、もうこんな時間! お昼の支度しなくちゃ! これ葉奈に届けてくるわねっ」
視界一杯に紫苑が映り、それがなにを意味するのかに気付かないほど子どもでもなかった芹香は、慌てて紫苑の腕の中から逃げ出したのだった。